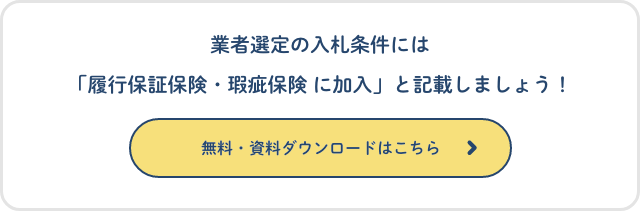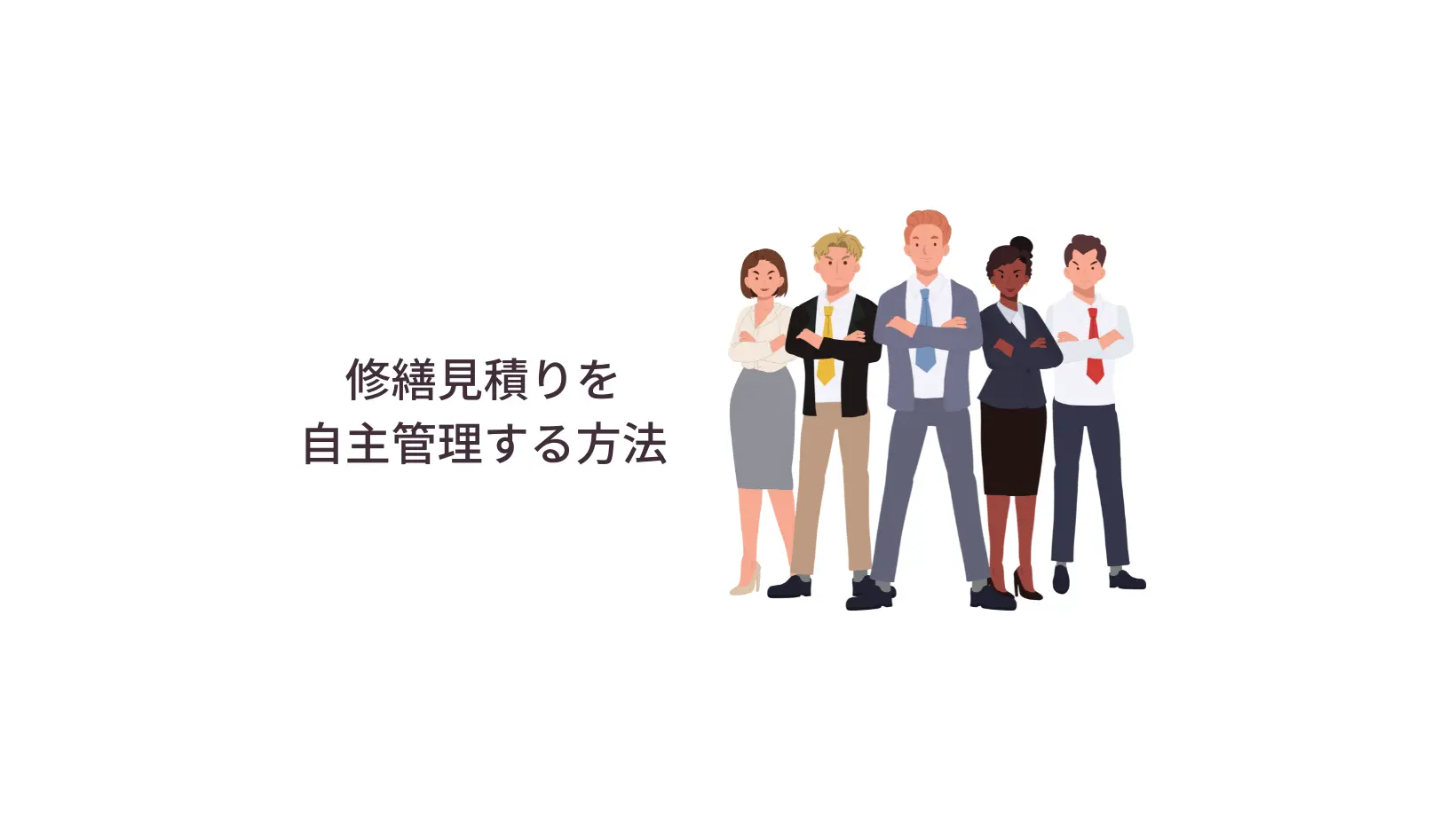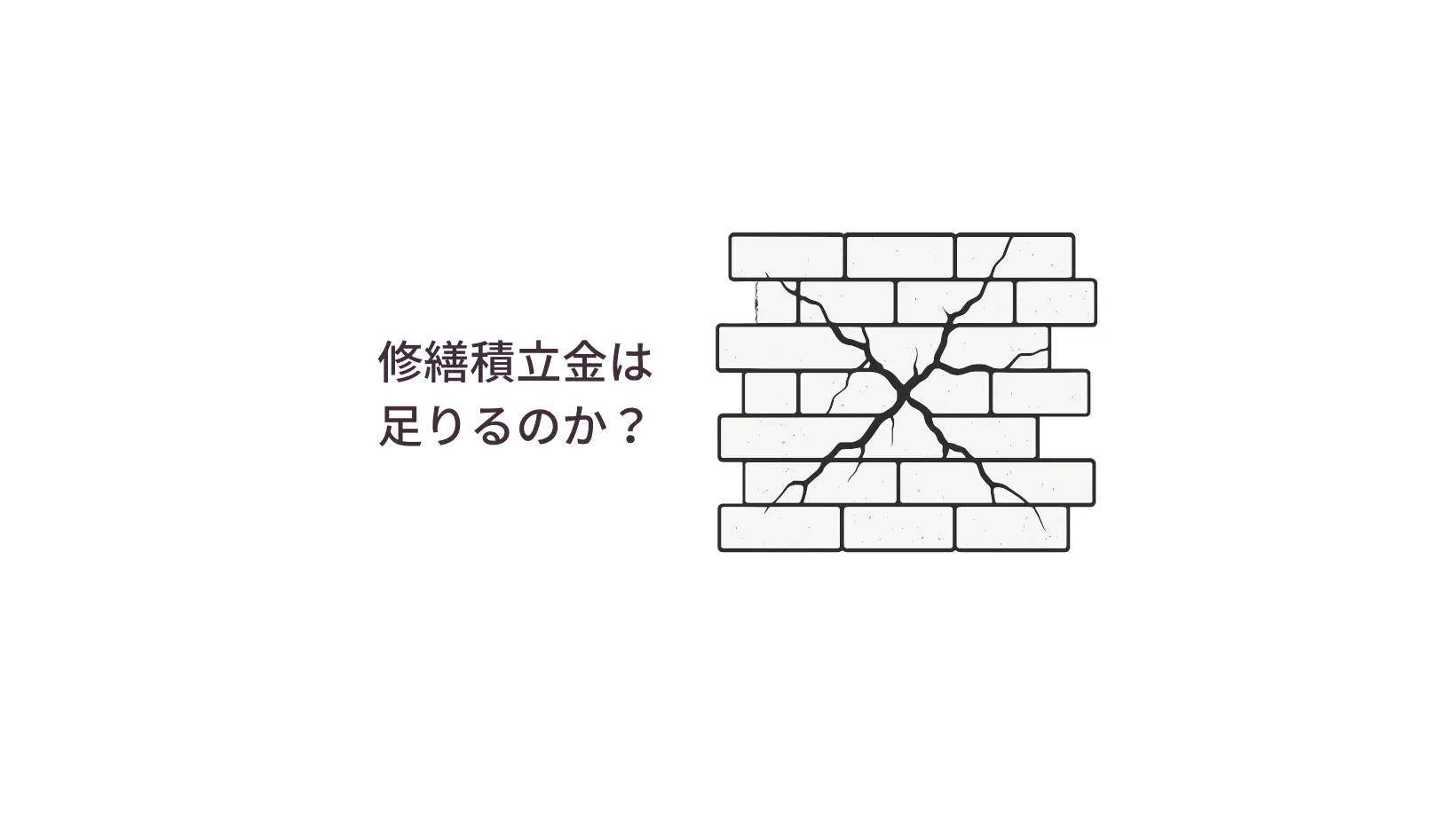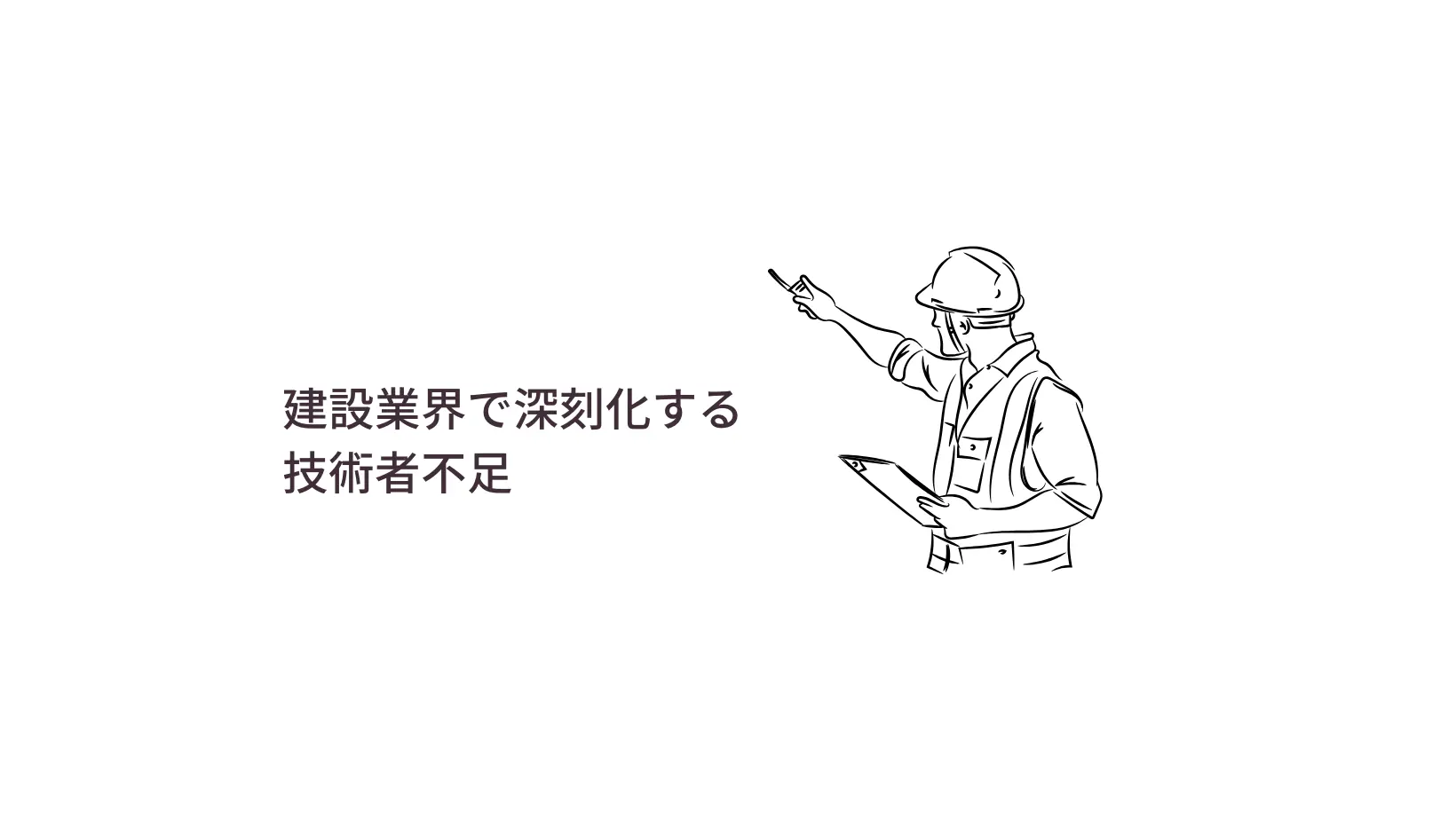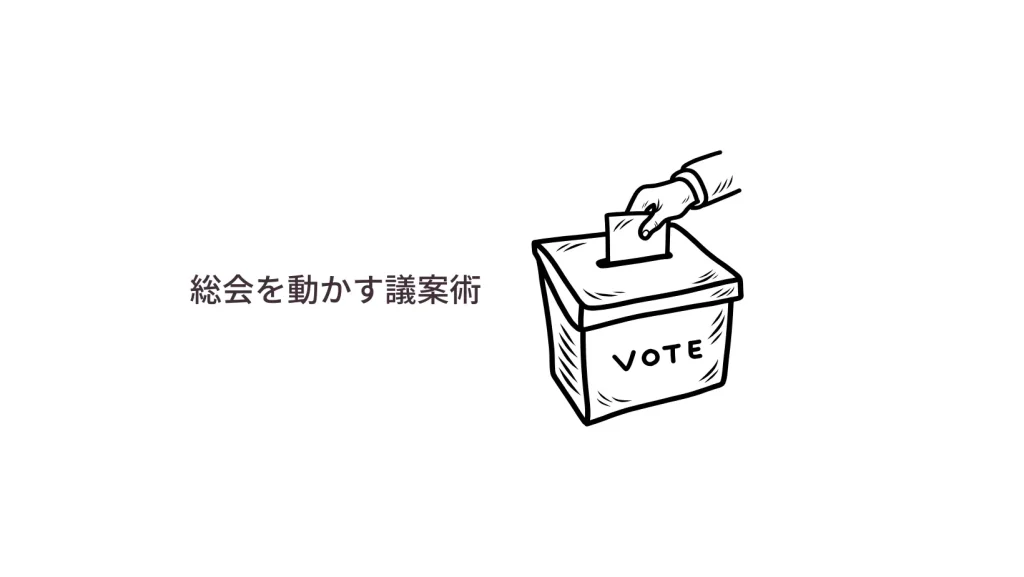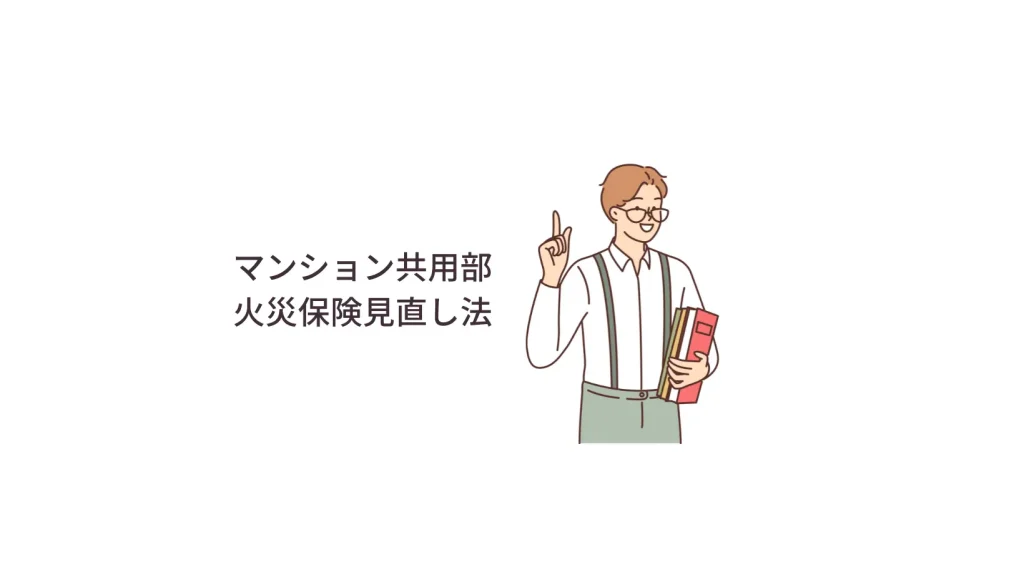皆さま、こんにちは!事務所が渋谷にある、渋谷貴博です。
35年間マンション業界一筋、またプライベートでは、埼玉県さいたま市の総戸数800戸のマンションに住んで、修繕委員、副理事長、理事長経験があります。そんな私が管理組合役員の皆さまの役に立つ情報を発信します。
「完璧な完成保証制度は存在しない」という現実
マンションの大規模修繕工事は、築12~15年を目安に行われ、その後もおおよそ12年前後ごとに繰り返される重要な事業です。外壁や屋上防水、鉄部塗装、共用廊下や階段、バルコニー、給排水設備など、多岐にわたる工事が含まれ、その規模は数千万円から数億円に及ぶことも珍しくありません。
しかし、工事を請け負った施工業者が工事途中で倒産してしまうケースは実際に存在します。その場合、工事は中断し、管理組合は多大な負担と混乱に直面することになります。本記事では、大規模修繕工事中に施工業者が倒産した場合のリスク、そして対応策について詳しく解説します。さらに、「完成保証制度」に関する誤解とその実態についても注意喚起を行います。
出来高より多い着手金は回収できない
大規模修繕工事契約の慣習として、工事開始時に「着手金」や「前渡金」を支払うケースがあります。しかし、これが施工業者倒産時の最大のリスクです。
工事の出来高分については、たとえ施工業者が倒産しても正当な工事の対価として支払う義務がありますが、出来高を超えて支払ってしまった着手金や前渡金は、ほぼ回収不可能です。破産管財人に債権として届け出ても、配当が行われることは稀で、実際には戻らないと考えるべきです。
したがって、契約段階で高額な着手金を設定してしまうと、施工業者が倒産した瞬間に大きな損失となります。このリスクを避けるために、着手金や前渡金の支払いをやめ、出来高に応じて少額ずつ支払う契約方式に切り替えることが有効です。
工事の中断と追加費用発生の現実
施工業者が倒産すれば、工事は一旦中断します。足場や仮設資材は放置され、建物は中途半端な状態でストップし、管理組合は「どうやって工事を再開するか」という重大な課題に直面します。
再開には多くの費用が発生します。一般的に総工事費の10%程度の追加費用が必要になるといわれ、その内訳は以下の通りです。
- 弁護士費用(契約関係や倒産処理対応)
- 建築士費用(品質確認や設計調整)
- 工事中断中の安全管理費
- 新しい施工業者を選定するための費用
- 足場の撤去・再架設費用
これらは全て管理組合が負担することになります。つまり、倒産は単なる「工事の一時停止」ではなく、想定外の大きな出費と手間を伴う事態なのです。
出来高払いと残工事費の仕組み
施工業者倒産時の費用処理を整理しておきましょう。
まず、施工業者が施工済みの出来高分は支払義務があります。倒産後は破産管財人などを通じて精算されます。
その一方で、残工事については次のようになります。
- 当初計画していた総工事費から、
- 出来高分として支払った工事費を差し引いた残額が残工事費用
この残額の範囲で新しい施工業者が工事を引き継いでくれれば理想的ですが、実際には足場の再設置や工事仕様の変更によって、残額を超える見積もりが提示されるケースも多くなります。これが「増嵩費用(追加工事費)」です。
履行保証保険によるリスク回避
こうしたリスクに備える有効な制度が、「履行保証保険(日新火災海上保険)」です。施工業者が倒産した場合、工事費の約10%が管理組合に保険金として支払われる仕組みで、この保険金は工事再開に必要な弁護士費用や足場再架設費用などに充当できます。
ただし、補填されるのはあくまで工事費の10%程度であり、それを超える費用は管理組合が負担する必要があります。したがって、「履行保証保険を付ければ全て安心」というわけではない点に注意が必要です。
入札条件に「履行保証保険への加入」を明記しておくことで、施工業者に確実に加入してもらうことができます。さらに、工事中断時の段取りや再契約の調整は、マンションあんしんセンターに依頼することでスムーズに進めることが可能です。
履行保証保険URL
https://mansion-anshin.com/system/

完璧な「完成保証制度」は存在しない
ここで最も重要な注意点を述べます。
「完成保証制度」という言葉から、施工業者が倒産しても管理組合が一切費用負担をせず、保証団体が工事を最後まで完成してくれると誤解されることがあります。しかし現実には、そのような「完璧な完成保証制度」は存在しません。
実際には次のような問題があります。
- 名ばかりの完成保証制度
「完成保証」と称しながら、その保証内容は限定的で、仮設足場の再架設費用のみ、しかも上限100万円までしか支払われない制度が存在します。これでは実際の工事完成には全く足りません。 - 保証団体の資金不足
「管理組合が費用を負担しなくても保証団体が完成を担う」と宣伝している団体もありますが、実際には保証のための準備金が十分に積み立てられておらず、いざ倒産が発生すると完成保証に必要な資金が確保できないという実態があります。 - 同業者間の保証の限界
一部では「工事完成保証人」という仕組みがあり、同業者同士で保証をし合うケースもあります。しかし、資本関係のない会社同士が、倒産した工事の全てを負担して完成まで保証するという仕組みは存在しません。現実には「一部の支援」に留まり、完全な保証は不可能なのです。
つまり、「完成保証制度」といっても、実際には管理組合が追加費用を負担せざるを得ない状況が必ず残るのが現実です。
マンションあんしんセンターブログ
https://mansion-anshin.com/archives/kansei/
管理組合が準備しておくべき3つのポイント
このようなリスクを踏まえ、管理組合が倒産リスクに備えるための具体的なポイントは以下の3つです。
- 着手金・前渡金を廃止し、出来高払い方式に切り替える
倒産時の回収不能リスクを避けるために不可欠です。 - 施工業者に履行保証保険の加入を義務付ける
工事中断時の追加費用の一部を保険でカバーできます。 - 残工事費の増加に備えて予算を確保する
修繕積立金や予備費を準備しておき、万一に備えることが重要です。
また、残工事を引き継ぐ施工業者の選定や、段取りの再構築については、専門機関であるマンションあんしんセンターのサポートを受けることで、安心して進めることができます。
まとめ|「完璧な保証はない」と理解して備える
大規模修繕工事の途中で施工業者が倒産するリスクは、決して珍しいことではありません。出来高以上の着手金は戻らず、工事再開には総工事費の10%程度の追加費用が必要となり、残工事費が増嵩する可能性もあります。
履行保証保険を活用すれば一定の補填は可能ですが、それでも管理組合の負担をゼロにすることはできません。さらに「完成保証制度」をうたう制度や団体も存在しますが、実際には保証が限定的だったり、資金が不足していたり、同業者間保証にも限界があります。
つまり、「完璧な完成保証制度は存在しない」のです。
だからこそ管理組合は、
- 契約条件で着手金を避けること、
- 履行保証保険を必須とすること、
- 万一に備えた予算を準備すること、
- 専門機関の支援を受けること
を組み合わせ、リスクを前提にした現実的な備えを行う必要があります。また、こういった保証制度については施工業者任せにせず、管理組合が主体的にリクエストをして進めましょう。
「大規模修繕工事の成功は段取り8割」といわれます。倒産リスクもまた、事前の備え次第で被害を最小限に抑えることが可能です。管理組合は冷静にこの現実を受け止め、住民の安心と建物の資産価値を守るために、しっかりと準備を進めていきましょう。
また、私どもマンションあんしんセンターでは、このように管理組合の皆さんが万全の大規模修繕工事を実施できるよう、様々なサポートをしています。特に業者の倒産や瑕疵問題に関する対応力は業界一位の専門集団といえます。ぜひ一度、当センターのホームページをご覧ください。
マンションあんしんセンター・ホームページ
https://mansion-anshin.com/