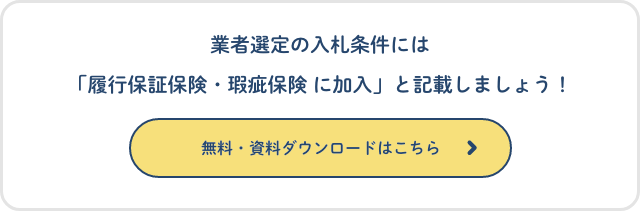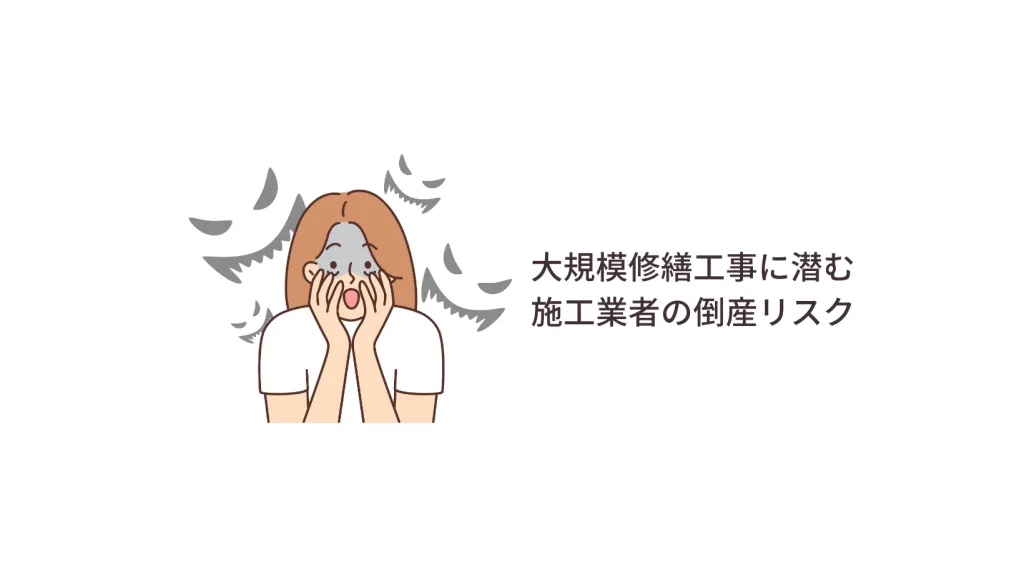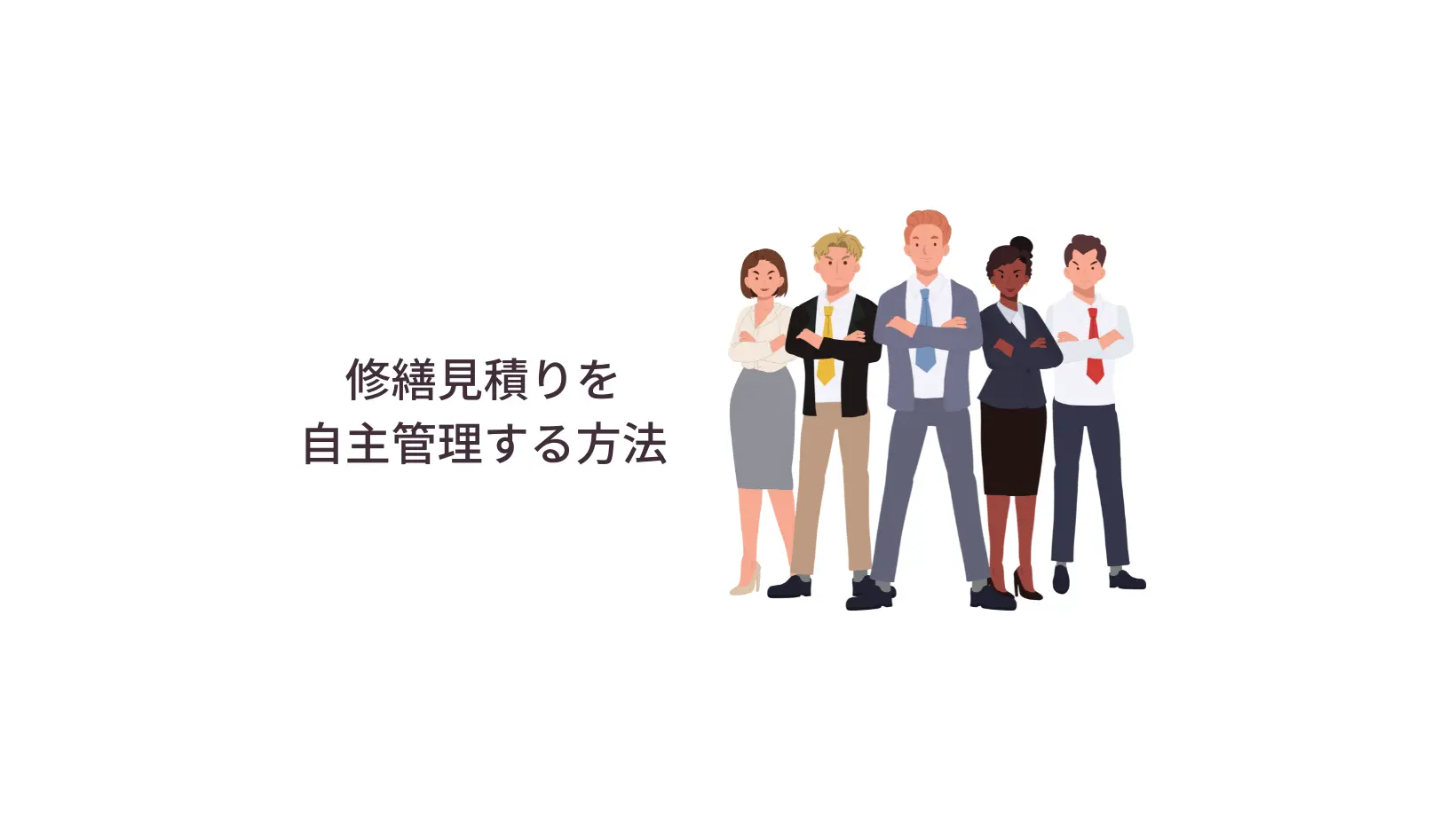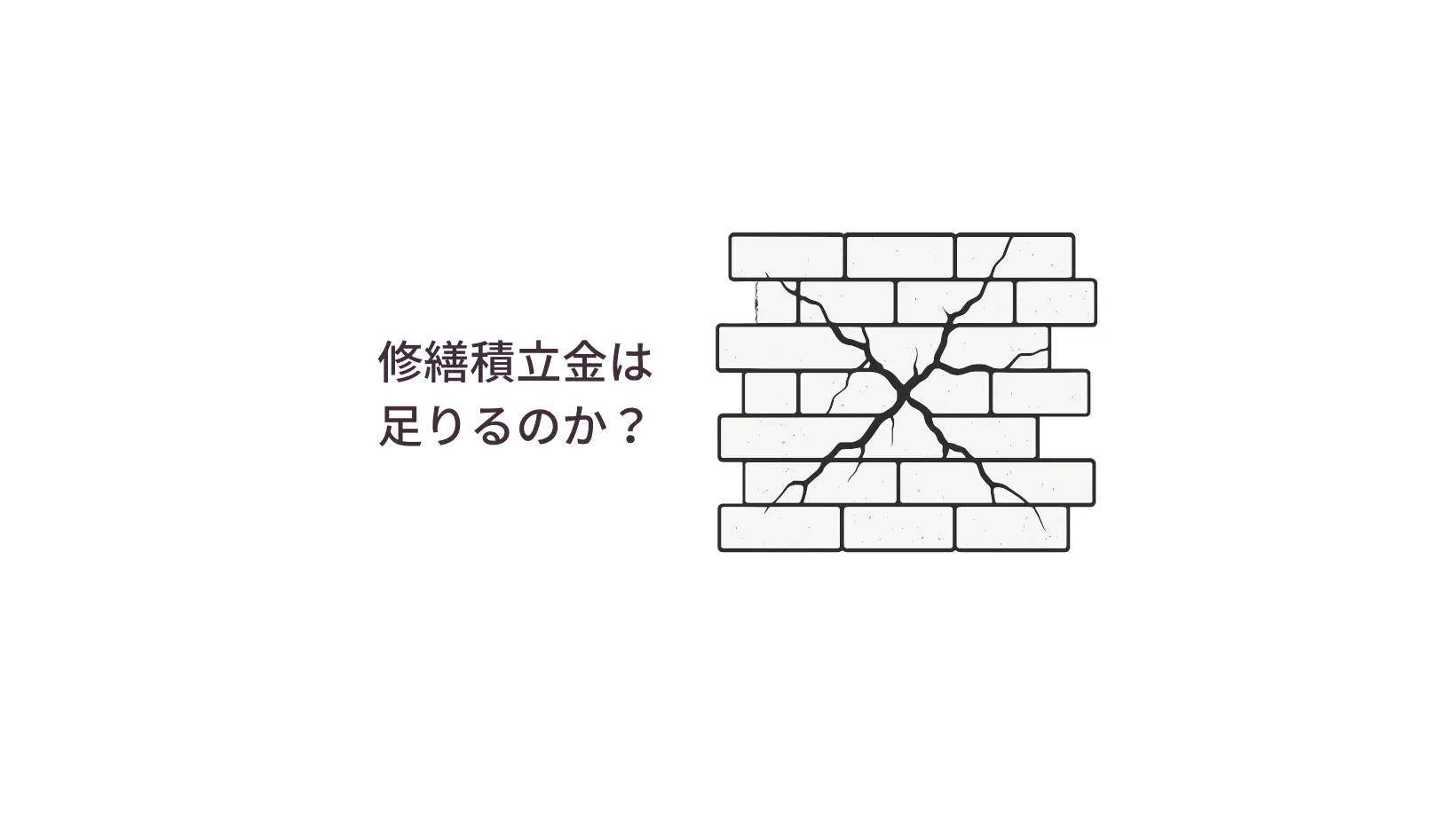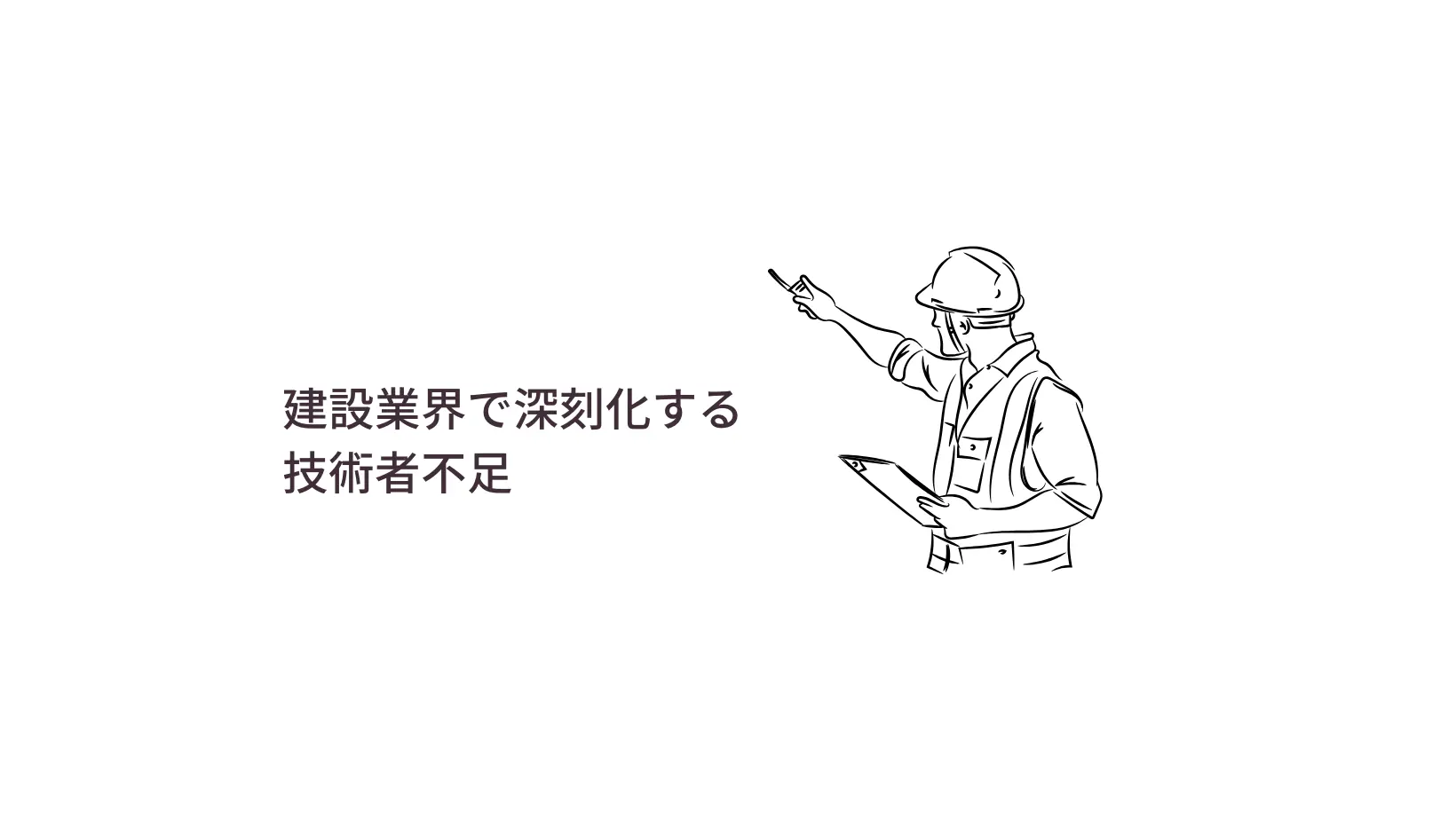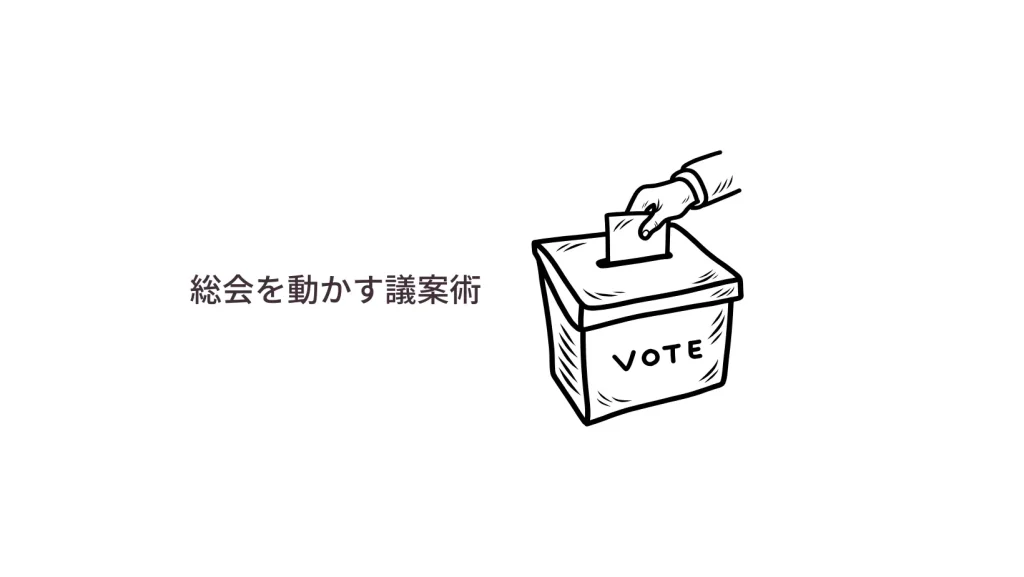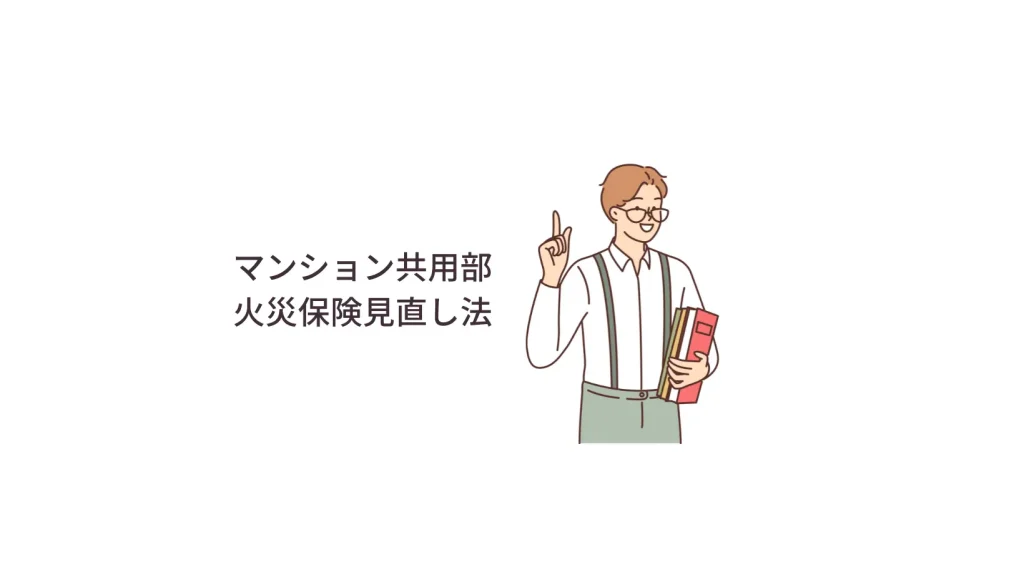こんにちは!事務所が渋谷にある、渋谷貴博です。
私は35年間マンション業界で働いてきました。またプライベートでは、マンション(埼玉県さいたま市・総戸数812戸)に住んで、修繕委員、副理事長、理事長経験があります。そんな私が管理組合役員の皆さまの役に立つ情報を発信します。
近年、マンション管理組合が抱える最大の課題のひとつとして、「大規模修繕工事における施工業者の倒産リスク」が顕在化しています。とりわけ2025年は、建設業界全体において過去10年でも類を見ないほどの倒産件数が観測されており、大規模修繕工事を予定するマンションにとっても決して無関係ではありません。
帝国データバンクの調査によれば、2025年上半期に倒産(負債1000万円以上、法的整理)した建設業者は986件にのぼり、前年同期の917件を上回って4年連続の増加。これは今後も継続する見通しで、年間倒産件数は2013年以来初めて2000件を超える可能性が高まっています。中でも中小零細の施工業者を中心に倒産が続出しており、マンション修繕の現場にも深刻な影響を及ぼす恐れがあります。
【帝国データバンクニュース】https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/20250708-bankruptcyh12025/
本記事では、なぜ今、施工業者の倒産が増えているのかという実態と、それがマンションの大規模修繕にどのようなリスクをもたらすのか、またそのリスクにどう備えるべきかについて解説します。
建設業倒産が過去最高水準へ──大規模修繕工事にも迫る「物価高騰」と「人手不足」の現実
2025年の建設業界では、かつてないほどの倒産ラッシュが現実のものとなりつつあります。帝国データバンクの最新調査によれば、2025年上半期に発生した建設業の倒産件数は986件と、前年同期を上回って4年連続の増加。年間では2013年以来となる2000件台突入の可能性も指摘されています。こうした激震は、戸建て住宅や商業施設の建設分野に限らず、マンションの大規模修繕工事にも深く影を落としています。
とりわけ、築30年を超えるマンションが急増しているなか、長期修繕計画に基づく周期的な大規模修繕が増加する現代において、管理組合が発注する数千万円から数億円に及ぶ修繕工事は、いまや中小建設業者の収益源であると同時に、資金繰りの綱渡りでもあります。施工業者の倒産リスクは、もはや一部の話ではなく、どの管理組合にとっても直面しうる現実的な課題となっています。
施工業者の倒産が相次ぐ主な要因のひとつは、言うまでもなく「資材価格の高騰」です。鉄骨やアルミ建材、防水材、塗料、さらには給排水管や住設機器に至るまで、ほぼすべての建材価格が上昇基調にあります。これらはすべて大規模修繕工事に不可欠な部材であり、特に2020年代に入ってからはウッドショックやエネルギー価格の高騰、海外物流の混乱などを背景に、見積額にも大きな影響を与えています。
ところが、多くの施工業者は、工事請負契約時の金額で工事完了までの責任を負う固定契約が一般的です。契約時の材料価格が後に大きく変動しても、その差額を発注者に転嫁することは難しく、赤字工事を強いられるケースが後を絶ちません。これが積み重なることで、体力のない中小業者は資金ショートを起こし、結果として倒産に至るのです。大規模修繕では数ヶ月から1年以上にわたる長期工程が多く、途中での資材高騰が工事全体の収益構造を一変させてしまう危険性があります。
次に、「人手不足による施工能力の低下」も深刻な問題です。特にマンション大規模修繕では、防水、外壁補修、足場仮設、塗装、設備改修など専門分野ごとに高度な技能を持った職人の手作業が不可欠であり、経験の浅い人員では品質確保が困難です。しかし現在、こうした熟練職人は高齢化により引退が進み、若手の担い手も建設業界に参入してきません。2024年の残業規制や労働環境の厳格化も影響し、職人の確保は一段と難しくなっています。
施工業者が必要な人材を自社で確保できない場合、下請け・孫請けに頼らざるを得ず、結果として外注比率が上がりコストも上昇します。そのうえ、技能水準や工程管理もばらつきが出やすくなり、クレームややり直しのリスクが高まります。山口県の管工事業者「SHINKI」の事例のように、人手不足を補うための外注費用が重荷となり、赤字連鎖から倒産するパターンは、今後の大規模修繕工事にも起こりうる事態です。
三つ目の大きな要因は、「受注不振」による資金繰りの悪化です。特にコロナ禍以降、先行きの不透明感から多くの建築需要が後ろ倒しとなり、工事が減少しています。また、物価上昇によって工事費が高くなりすぎ、理事会や総会で予算承認が得られず、工事そのものが延期・縮小される例も増えています。これにより施工業者は案件獲得の競争が激化し、受注が減少、資金の流入が鈍化して経営基盤が不安定になるという連鎖に陥っているのです。
大阪の注文住宅会社「さつまホーム」は、健康志向の注文住宅を中心に展開し、拡大路線で一時は年商19億円を超えたものの、資材高騰と顧客の買い控えにより受注が激減。売上は6億円まで落ち込み、ついには自己破産に追い込まれました。この事例は、同様に工事件数や予算調整の影響を受けやすい大規模修繕工事業者にも当てはまります。
このように現在の建設業界は、「材料価格の転嫁ができない」、「人材確保が困難」、「受注が安定しない」という三重苦に直面しており、特に中小の修繕専門業者には極めて厳しい経営環境が続いています。その結果として、倒産リスクは誰の目にも明らかな形で高まり続けていますが、工事発注時にはその兆候が外から見えにくく、理事会や管理会社が気づいた時にはすでに手遅れというケースも少なくありません。
実際に、工事契約後や着工後に施工業者が音信不通となり、現場が放置されたままになる事例も全国で発生しています。マンション管理組合としては、こうした“まさか”の事態を前提としたリスクマネジメントが不可欠であり、業者選定段階から倒産リスクを視野に入れた戦略的判断が求められる時代に入っているのです。
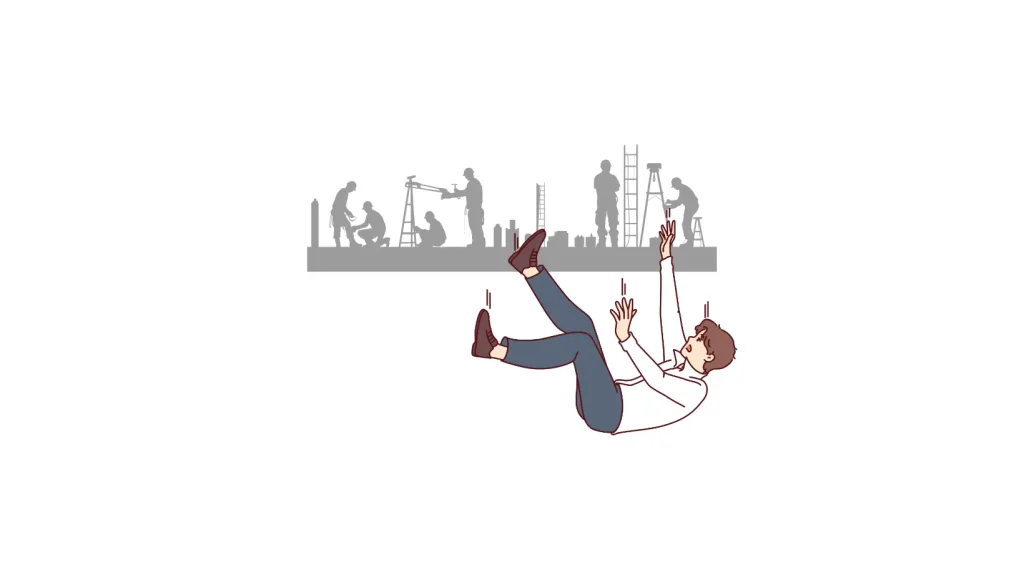
倒産リスクがもたらす修繕工事への実害と、その対策
こうした施工業者の倒産リスクが、マンションの大規模修繕工事に与える影響は、単なる業者の都合では済まされないほど深刻です。マンションという集合住宅の性質上、一度工事が始まれば数十世帯、あるいは数百世帯に影響が及ぶため、施工業者の経営破綻は居住者の生活基盤にまで直結する事態となります。とくに居住者が住みながら工事を行う「居住継続型工事」が主流である現在、工事の中断や遅延、トラブルは住民の生活環境と信頼関係そのものに影を落とします。
まず最も大きな影響として挙げられるのが、「工事の中断によるスケジュールの遅延」です。大規模修繕工事は、仮設足場の設置から外壁補修、防水、塗装、設備改修など、多くの工程が緻密なスケジュールで連動して進行します。施工業者が突然倒産してしまえば、工事は即座にストップし、その後の対応に長期間を要する可能性が高まります。新たな施工業者の選定、引継ぎ、再契約といった手続きに数ヶ月単位の時間がかかることは珍しくありません。中断期間中も足場や仮設トイレ、養生シートは設置されたままで、住民にとっては生活の不便さが長引くだけでなく、安全管理や防犯上の問題も増大します。
次に、実害として多く報告されているのが「前払い金(着手金)の損失」です。大規模修繕工事では、その総工費が数千万円から億単位に及ぶため、契約時に着手金として総額の10~30%程度を支払うケースが一般的です。ところが、万が一その時点で業者が経営破綻した場合、この前払い金が返還される保証はほとんどなく、管理組合にとっては実質的な損失になります。この損失を補うためには、追加の予算措置や修繕積立金からの緊急取り崩しが必要になり、他の修繕計画にも悪影響を及ぼします。最悪の場合、住民からの臨時徴収を余儀なくされる可能性もあり、管理組合への不信感や内部対立につながる懸念も無視できません。
さらに見過ごせないのが、「工事品質の担保が失われる」という問題です。大規模修繕工事では施工期間が長期に及ぶため、倒産が起きるタイミングによっては外壁の補修途中、防水層の施工不完全、配管更新の中断などが発生し、建物の保全機能そのものが損なわれる危険性もあります。また、新たに引き継いだ施工業者が、それまでの施工箇所に不具合や手抜きがあっても「自分たちの責任ではない」と補修を拒否するケースも多く、やむを得ずやり直しや追加工事が必要となることも。これによって当初予算を大幅に超える追加費用が発生する場合もあり、財政面での再検討を余儀なくされます。
では、このような深刻な倒産リスクに対し、マンションの管理組合はどのように備えるべきなのでしょうか。第一に実施すべきは、「施工業者の選定時に財務状況や経営基盤を徹底的に確認すること」です。単に過去の工事実績だけでなく、直近の決算書や借入金の比率、営業キャッシュフローなどから企業体力を判断し、場合によっては帝国データバンクや東京商工リサーチなどの外部信用調査を活用することも推奨されます。口頭での説明や営業トークに惑わされず、客観的な数値と情報に基づいた選定こそが、倒産リスクを未然に察知する第一歩です。
次に講じるべき対策は、「契約条件の工夫」です。たとえば、支払い方法を出来高払いとすることで、工事の進行に応じて支払額を段階的に分け、万一倒産しても支払済額を最小限に抑えることが可能です。また、着手金を原則として支払わない、または支払っても極めて少額に抑えることで、損害の回避につながります。さらに、契約書に履行保証保険の加入を義務付けることも重要です。この保険は、施工業者が倒産などで工事を継続できなくなった場合に、保険会社が管理組合に工事再開・完成のために活用する保険金を支払う制度であり、リスクヘッジとしては非常に有効です。
【日新火災海上保険の大規模修繕工事向け履行保証保険】https://mansion-anshin.com/system/
また、「設計監理方式の導入」も倒産リスクに備える有効な手段です。これは、設計者や建築士など第三者の専門家を設計・監理者として独立して起用し、施工業者とは契約を分離する方式で、透明性が高く、万一施工業者が倒れても工事の品質や設計意図を継承して進めることができます。特に最近では、コンサルタントによる施工業者への技術的指導や検査・監督を通じて、手抜きや瑕疵の抑止にもつながっており、修繕工事の質の担保とリスク回避の両立が可能です。この件に関しては、マンションあんしんセンターの過去のブログ「【完全解説】大規模修繕工事コンサルタントの役割と選び方」も参考にしてみてください。
そして何より大切なのは、理事会・管理会社・修繕コンサルタントといった関係者全体が、施工業者の倒産を「起こらないはずの例外」ではなく、「起こりうる現実のリスク」として常に認識しておくことです。経済情勢や業界動向によって業者の経営は容易に変動し、安易な価格競争や短期間での選定が命取りになる可能性すらあります。発注のたびにゼロから業者探しをするのではなく、信頼関係を構築できるパートナー的な施工業者やコンサルタントと中長期的に連携し、常に予防的な視点で体制を整えておくことが、結果として「損をしない修繕」への第一歩となるのです。
今や、建設業者の倒産はニュースの中の話ではありません。マンションの管理組合が自らの身に引き寄せて考えるべき、非常に現実的で差し迫った課題です。事前の調査、制度の活用、そしてプロの知見との連携を通じて、最悪の事態に備えるという姿勢が、修繕の成功と安心なマンション運営を支える鍵となります。
まとめ|倒産リスクは「他人事」ではない。備えることで被害を最小限に
建設業界における倒産件数の増加は、決して業界の一部で起きている特殊な出来事ではなく、全国のマンション管理組合が今まさに直面すべき切実な問題です。2025年現在、施工業者の倒産は「稀なケース」ではなく、「日常的に起こりうるリスク」として認識されるべき段階に突入しています。物価の高騰、人手不足、受注減少という三重苦の中で、多くの中小施工業者が経営的な限界に追い込まれているのが実態であり、そのあおりを直接受けるのが、まさに大規模修繕工事を発注する管理組合なのです。
もしも契約相手の施工業者が工事途中で倒産してしまった場合、着手金の損失、工事の長期中断、未完成部分の補修責任の所在不明、追加費用の発生、理事会の信頼喪失など、あらゆる面で深刻なダメージを被ることになります。住民間での不和や理事会へのクレーム増加、管理会社への責任追及といった二次的な混乱も起きやすく、管理組合運営そのものにも大きな影響を与えかねません。
こうした事態を防ぐには、あらかじめ「倒産を想定した備え」を講じておくことが欠かせません。その第一歩としては、「施工業者の選定を慎重に行うこと」が最重要です。実績や価格だけでなく、財務基盤や過去の工事履歴、信用情報などをしっかりと調査したうえで、信頼できる業者との契約を目指すべきです。また、工事代金の支払いは「出来高払い方式」を採用し、進捗に応じた支払いとすることで、途中倒産による損失を最小限に抑えることが可能になります。
加えて、倒産時の損害補填や工事の引き継ぎを保証する「履行保証保険」の活用も極めて有効です。この保険により、施工業者が工事途中で業務継続不能となった場合でも、保険会社が費用の一部を補填したり、代替業者を紹介することで、工事の中断を最小限に食い止めることができます。また、工事完了後の品質トラブルに備えて「瑕疵保険(かしほけん)」に加入させることも有効です。瑕疵保険は、竣工後一定期間内に欠陥や施工不良が見つかった場合に、保険によって修補費用がカバーされる制度であり、施工業者の保証能力に依存しない安心を得られます。これらの保険は、マンション管理組合が安心して修繕計画を進めるうえでの心強いセーフティネットとなります。詳しい補償内容や加入条件については、当センターのホームページにて詳しくご案内しておりますので、ぜひご覧ください。
【日新火災海上保険の大規模修繕工事向け履行保証保険と瑕疵保険情報】https://mansion-anshin.com/system/
さらに、第三者の設計監理者を置くことで、技術的な視点から施工の品質と進捗を監視し、業者任せにしない体制を整えることも重要です。設計監理方式を採用すれば、万が一施工業者が倒産しても、設計の連続性が保たれ、新たな業者へのスムーズな引き継ぎが可能になります。
そして何より、管理組合として忘れてはならないのは、「安心・安全な修繕工事を実現する」という根本目的を常に意識し続けることです。価格や納期だけに目を奪われず、長期的な視点で信頼性とリスク管理を重視した選定・契約・体制づくりを徹底することで、万が一の事態にも慌てることなく対応できる体制が整います。
倒産リスクを他人事と捉えず、自分たちのマンションでも起こりうる現実として受け止め、あらかじめ適切な備えを講じること。それはマンションの資産価値を守り、そこに住むすべての人々の安心と暮らしを支えるために、いま管理組合が取るべき“当たり前の判断”です。トラブルは、未然に防ぐための知識と行動があるかどうかにかかっています。後悔しない大規模修繕のために、ぜひ今から備えを始めてください。