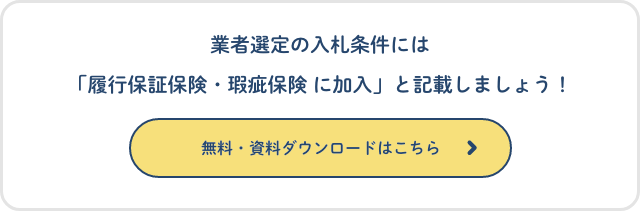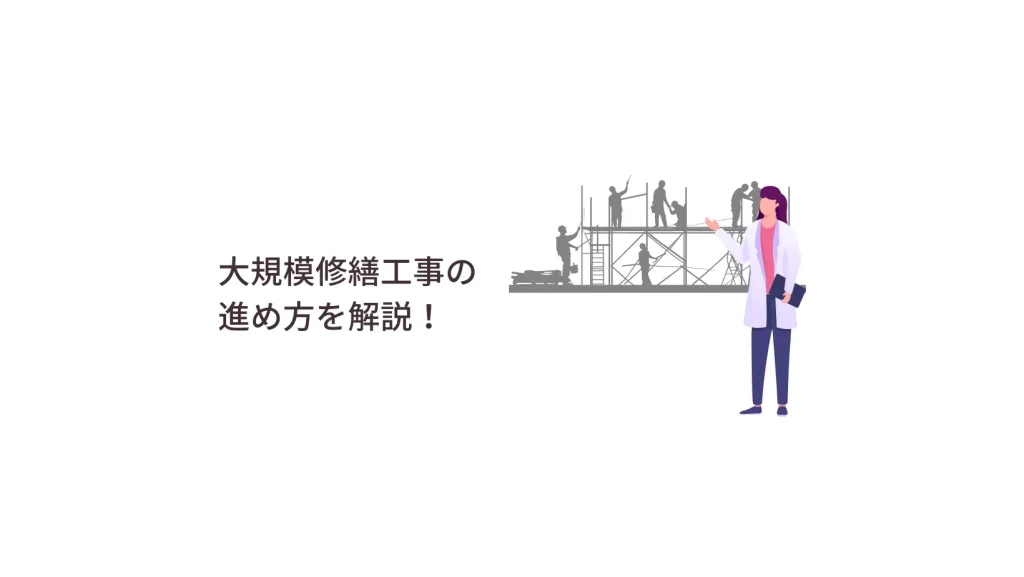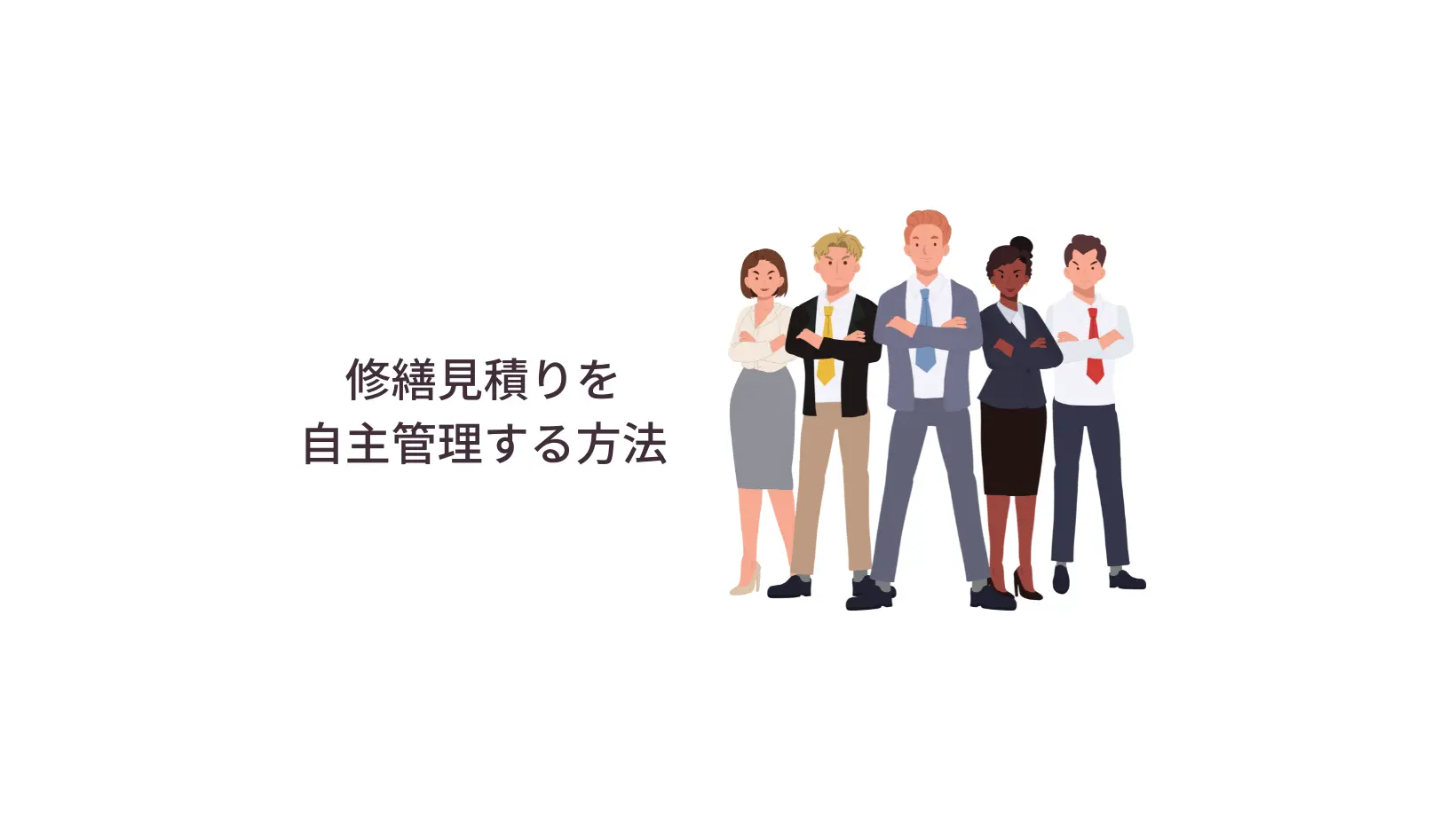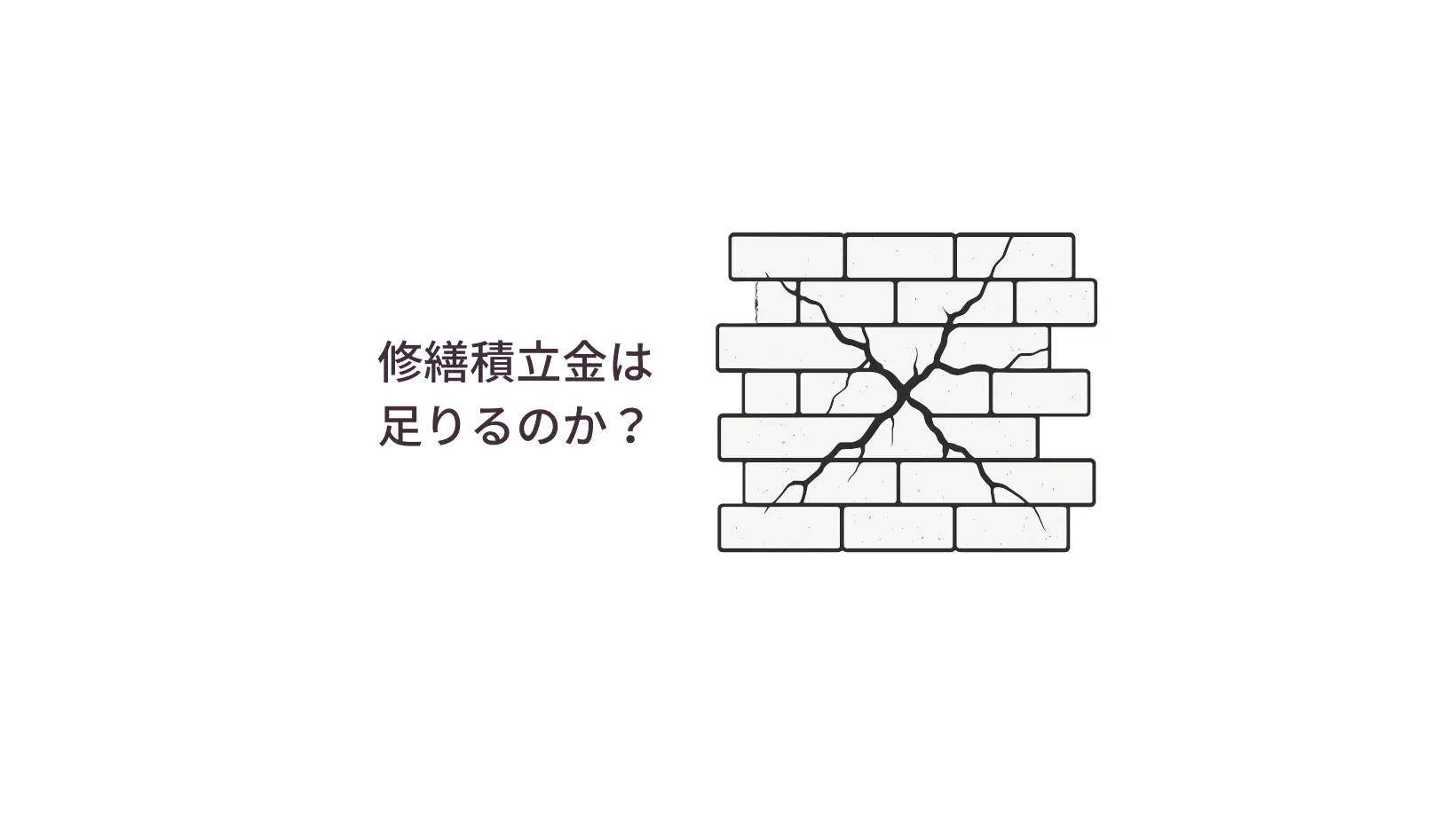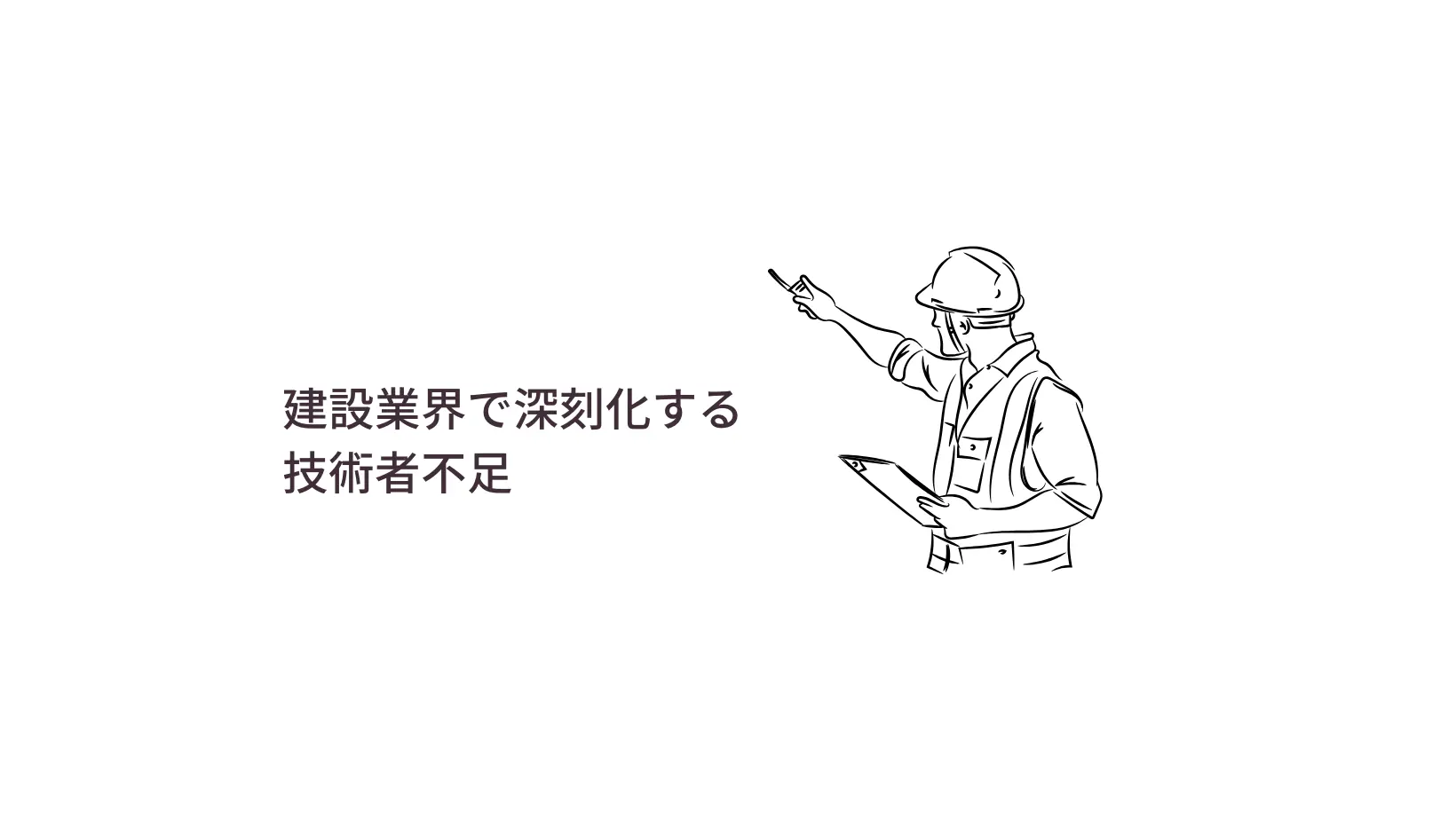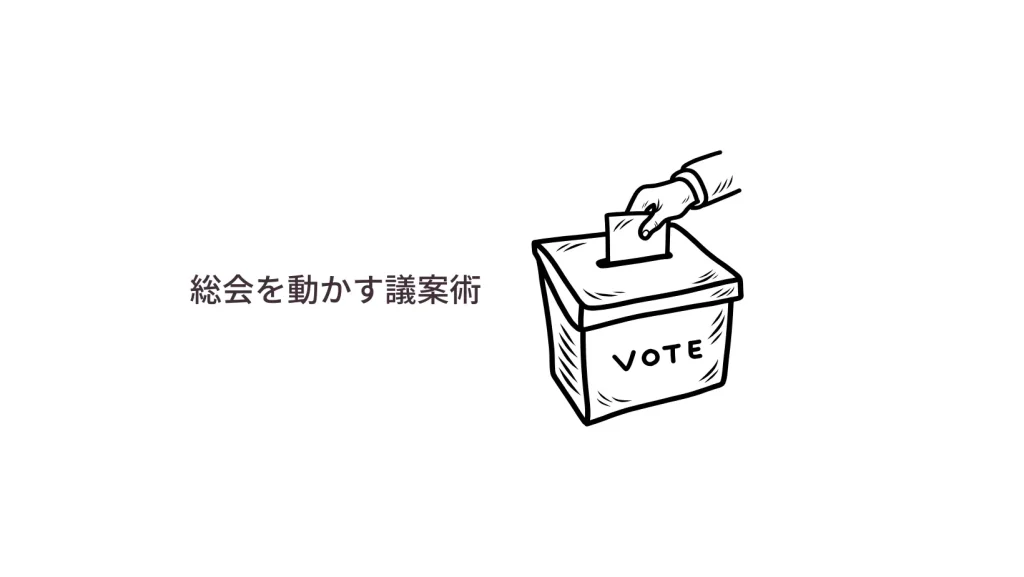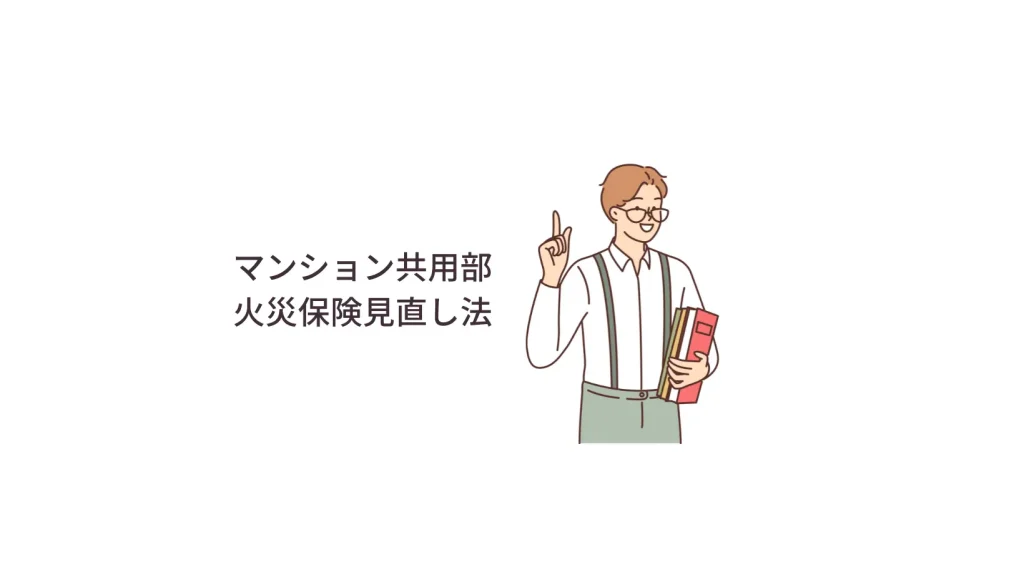皆さま、こんにちは!事務所が渋谷にある、渋谷貴博です。
35年間マンション業界一筋、またプライベートでは、埼玉県さいたま市の総戸数800戸のマンションに住んで、修繕委員、副理事長、理事長経験があります。そんな私が管理組合役員の皆さまの役に立つ情報を発信します。
マンションの大規模修繕工事は、12〜15年ごとに行われる大事業です。外壁、屋上防水、給排水設備、鉄部塗装など、建物全体の共用部分を一括して修繕することで、機能の回復や美観の維持、事故防止を図ります。しかしその実施には長期的な準備と専門的な判断が必要であり、多くの管理組合では「何から始めれば良いのかわからない」という声が少なくありません。
本ブログでは、マンション管理組合の役員や修繕委員の方々に向けて、大規模修繕を成功に導くための具体的な進行プロセスを、事前準備から調査・設計、施工会社の選定、工事着手から引き渡しまで、時系列に沿ってわかりやすく解説します。初めての修繕でも安心して取り組めるよう、各工程での注意点やポイントも併せてご紹介します。
修繕計画の立案から業者選定までの準備段階
大規模修繕工事のプロジェクトは、すぐに工事に取りかかるのではなく、まず「準備フェーズ」からスタートします。この段階は、全体計画の骨組みを築くと同時に、住民の理解と協力を得るための土台作りとして非常に重要です。ここでの対応が甘ければ、後々の工事運営や住民対応に支障が出る可能性があります。したがって、この準備段階をいかに丁寧に進めるかが、プロジェクト全体の成否を左右するといっても過言ではありません。
最初に取り組むべきは、「現状把握」です。まず管理組合として、今の建物がどのような状態にあるのかを正確に知る必要があります。一般的には管理会社や建築士などの専門業者に依頼し、「建物劣化診断調査(予備調査)」を実施します。外壁にクラック(ひび割れ)や浮き、タイルの剥落兆候がないか、屋上やバルコニーの防水層が正常に機能しているか、鉄部に錆が発生していないか、給排水管の劣化が進行していないかなど、目視だけでなく打診検査や赤外線カメラ、サンプル採取による中性化試験など、多角的な診断を行うのが一般的です。
こうした診断により、本当に修繕すべき箇所・今すぐ対応が必要な箇所・次回以降に回しても問題ない箇所などの分類が可能になります。結果として、不要な工事を省き、予算の最適化にもつながります。診断報告書には写真付きの劣化状況一覧や、部位別の推奨修繕時期・優先度が明記されるため、これを基に修繕の方針を検討するのが一般的です。
次に、「長期修繕計画」の再確認と見直しが行われます。マンション管理組合では、築年数に応じて25年〜30年程度の長期修繕計画を策定していることが一般的ですが、その内容が最新の建物状況や市況に合っているとは限りません。例えば、想定より劣化が進んでいる場合は工事時期を前倒しする必要があり、逆に劣化が軽微であれば一部内容を次回に先送りすることも可能です。また、建設資材の価格上昇や人件費高騰など、外的要因によって予算見積もりも大幅に変動していることが多くあります。現実との乖離を放置したまま進めると、資金不足や工事中のトラブルにつながるため、見直しは必須です。
さらに、修繕積立金の残高や今後の収支予測も確認する必要があります。現在の残高で全ての工事を賄えるのか、それとも借入や一時金が必要かといった、資金面のシミュレーションもこの時点で行っておくべきです。その結果によっては、段階的な工事への切り替えや、費用抑制のための仕様見直しなども検討対象となります。自分のマンションだけではなく、国土交通省や各種機関が発信している情報を参考にすることも視野を広げたり、業界標準を知ることにつながるため重要です。
<相談窓口>
〇(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/reform/consult.html
(電話番号)住まいるダイヤル0570(016)100
※施工費用については「見積チェックサービス」(無料)も行っています。
○ (公財)マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/06_consult/tel.html
(電話番号)建物・設備の維持管理のご相談03(3222)1519
<その他情報掲載先>
○ 大規模修繕の手引き~マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計 画のポイント~(独立行政法人 住宅金融支援機構)【住宅金融支援機構ホ ームページ】
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/mansionreform/shuzen_guidebook.html
○ マンションライフサイクルシミュレーション【住宅金融支援機構ホームペ ージ】
https://www.jhf.go.jp/simulation_loan/m-simulation/index.html
○ 「長期修繕計画・修繕積立金算出サービス(公財 マンション管理センタ ー )」【マンション管理センター ホームページ】 https://www.mankan.or.jp/07_skillsupport/skillsupport.html
続いて必要なのが、「修繕方針の確立」です。修繕の目的を明確にし、どのような考え方で工事を進めるのかを理事会として定めていきます。例えば、「今回の修繕では基本的な劣化対策に留めるのか、それとも将来を見据えて省エネや防災、防犯、バリアフリーといった機能向上も含めるのか」といった選択です。住民の年齢層や生活様式の変化、空室対策なども踏まえた長期的視野が求められます。
また、修繕方針と並行して、「プロジェクト体制の検討」も重要です。工事を誰が主導して進めるのかという視点で、管理会社主導で行うのか、あるいは中立的な第三者である「設計監理方式のコンサルタント(設計事務所)」を導入するかどうかの判断が必要になります。設計監理方式を採用すれば、施工業者との利害関係が排除されるため、設計・見積り・工事監理などが公平かつ専門的に進められ、談合や手抜き施工のリスクが減少します。
コンサルタントを導入する場合は、プロポーザル(提案募集)による選定が一般的です。複数の事務所から提案を募り、それぞれの実績、専門性、報酬体系、対応姿勢、説明のわかりやすさなどを比較・評価します。ヒアリングやプレゼンを通じて理事会と価値観の合うパートナーを見つけることが、数年に及ぶプロジェクトの成功に直結します。
その後、設計・仕様書の作成が完了したら、「施工業者選定」のフェーズに入ります。ここでは、複数の施工会社に見積もりを依頼し、価格だけでなく、施工実績、建設業許可の有無、元請比率、安全体制、現場監督の配置状況、保証制度など、総合的な観点から評価を行います。コンサルタントが入っていれば、形式だけでない技術的な比較や、入札方式の適正化も支援してくれるため、より質の高い選定が可能です。
また、最近は建設業者の倒産リスクが無視できないため、「履行保証保険」の導入が常識化しつつあります。これは、契約途中で業者が倒産して工事が中断した場合に、保険会社が工事再開や完成に必要な費用を保険金として一定負担してくれる仕組みです。費用は工事金額の0.6~0.8%程度ですが、管理組合にとっては非常に有効なリスク回避策となります。大規模修繕工事のように数千万円〜数億円単位の契約では、このような保険の有無が業者選定の評価基準にもなっています。
〈履行保証保険の概要〉
https://mansion-anshin.com/system/
〈履行保証保険など保険制度を使って工事を成功させるブログ紹介〉
https://mansion-anshin.com/archives/20250714/
最終的に業者が決定したら、理事会内で協議のうえ、管理規約に基づき総会での承認を得る必要があります。そのため、住民説明会を複数回開催し、工事の必要性、工法、費用、施工期間、影響範囲などを丁寧に説明し、疑問点に真摯に対応する姿勢が求められます。
住民の中には、工事費用や生活への影響を不安に思う方もいます。そうした声にしっかり耳を傾け、計画内容の見直しも視野に入れた柔軟な対応が信頼構築には不可欠です。合意形成が十分に図られないまま工事を進めると、後のトラブルや不信感の火種となるため、初期段階での丁寧な対話と情報開示が成功の鍵になります。

工事開始から完了・引渡しまでの施工段階
総会で大規模修繕工事の計画が正式に承認されると、いよいよ実際の施工フェーズに移行します。ここからは、理事会や修繕委員会が中心となって、現場の進行管理や住民対応など、実務的な運営力が問われる段階となります。特に、居住者が生活を続けながら工事が進行するため、日常生活への影響を最小限に抑えるための配慮や、円滑なコミュニケーション体制の構築が極めて重要です。工事に対する住民の理解と協力が得られなければ、クレームや不信感の拡大につながり、プロジェクト全体の評価にも関わるため、準備以上に気を配るべき期間ともいえます。
工事に着手する前には、関係者による「着工準備会議」が開催されます。この会議には、理事会(または修繕委員会)、施工業者、設計監理者であるコンサルタント、管理会社の担当者が集まり、実際の施工スケジュールや仮設計画、安全対策、周知方法などについて詳細な確認とすり合わせを行います。足場の設置位置や作業エリアの確保、工事車両の動線、資材置き場の場所、共用スペースへの影響、作業時間帯の設定、住民の動線確保、さらには夜間の安全対策に至るまで、多くの検討項目があります。また、騒音や粉じん、臭気といった生活上のストレス要因にも十分な配慮が必要です。特に高齢者や乳幼児を抱える世帯には、事前に個別の配慮が求められる場合もあります。
工事開始後は、住民への定期的かつ的確な情報提供が極めて重要です。具体的には、工事の進捗状況、各工区の施工予定、洗濯物の干し制限、窓の開閉制限、一時的な通行制限、断水・停電予定、バルコニーへの立ち入り不可期間など、日常生活に直接関係する情報を漏れなく周知する必要があります。情報提供の手段としては、掲示板への掲示、各戸へのチラシ配布、マンション内の回覧板、エレベーター内の張り紙、さらにはLINEやマンション専用アプリを使ったデジタル通知など、複数のチャネルを併用することが効果的です。また、特定の工事区画が住民の移動動線や生活空間と重なる場合には、仮設の通路や防護ネットなどを事前に設け、安全かつストレスの少ない動線を確保する工夫も欠かせません。
現場では、施工業者による施工管理と同時に、コンサルタントによる第三者監理が並行して行われます。設計図や仕様書に従って正確に工事が進められているか、材料の品質や施工技術に問題がないか、作業員の安全管理が適切に行われているかなど、さまざまな視点から現場の品質を監視する役割を担います。理事会や修繕委員会は、こうした監理状況を把握するため、定例会議に参加し、進捗報告を受けるとともに、現場で発生した課題への対応や、住民から寄せられた意見・苦情のフィードバックを行います。とくに梅雨や台風、猛暑といった天候の影響によって工程に遅れが生じた場合には、計画の再調整が必要となるため、柔軟な対応力と迅速な判断が理事会に求められます。
また、工事中には予期せぬ問題が発生することも珍しくありません。例えば、外壁タイルを剥がした際に下地のコンクリートが著しく劣化していたり、図面にない配管が現場で見つかるなど、図面と実物との乖離が明らかになる場合があります。こうした場合、仕様変更や追加工事が必要となり、費用の増加や工期の延長が避けられないこともあります。これらに対応するためには、事前に「設計変更時の承認手続き」や「追加費用発生時の理事会決議の要否」などをルール化しておくことが重要です。変更の必要性やコストに対して合理的な根拠があるかを理事会で慎重に検討し、住民に対する丁寧な説明を行ったうえで決定を下すことが、信頼の維持につながります。
工事がすべて完了したら、最後に「竣工検査」が行われます。これは、仕様書や設計図に従って正しく施工が行われたかどうか、仕上がりに不備や問題がないかを最終的に確認する重要なプロセスです。検査には理事会、コンサルタント、施工会社の代表が立ち会い、共用廊下、階段、屋上、バルコニー、外壁など、工事対象となった部位を一つ一つ丁寧に目視・計測しながら確認します。もし不具合や未施工箇所が発見された場合は、その場で指摘し、施工業者に是正を求めたうえで、必要に応じて再検査を行います。問題がすべて解消されたことが確認された段階で、正式に「引渡し」となり、工事は完了します。
引渡しに際しては、各種書類の受領・保管も極めて重要です。具体的には、防水工事や外壁補修などの保証書、竣工図面や施工記録をまとめた竣工図書、各工種ごとの工事報告書、保証期間一覧表、使用部材の製品情報などがあります。これらは今後の維持管理や次回修繕時の重要な資料となるため、ファイルやデジタルデータとして整理し、次期理事会への確実な引き継ぎが求められます。引渡し後も工事が完全に終わったわけではなく、「アフターサービス」の管理も理事会の重要な役割となります。通常は工事内容に応じて1年、2年、5年、10年と保証期間が設定されており、万一の不具合発生時には、迅速に対応を依頼できるよう、施工業者との連絡体制や相談窓口を明確にしておく必要があります。
最後に、工事の全記録を整理し、理事会議事録、住民向け報告書、図面、写真資料などを一元化して保管することで、次回以降の修繕を担当する役員や修繕委員会への「知識と経験の継承」が可能になります。マンションの修繕は一度きりではなく、長期的なサイクルで繰り返し行われるものです。したがって、今回のプロジェクトで得た知見を共有し、持続可能な管理体制を築くことが、将来の大規模修繕の円滑な運営と、マンションの資産価値維持につながっていくのです。
まとめ|段取り8割、行動2割の精神で
大規模修繕工事は、単なる建物の補修作業ではなく、マンションという共同住宅の将来を見据えた「住まいの再生プロジェクト」とも言える、管理組合にとって最も大きな責任と判断が求められる一大事業です。その成否は、実際の工事そのものよりも、工事に至るまでの準備段階、つまり理事会が主体的に取り組む計画立案・意思決定・住民との合意形成といった“段取り”に大きく左右されます。
現状調査や長期修繕計画の見直しから始まり、修繕方針の確立、信頼できるコンサルタントの選定、施工業者の比較・評価、そして総会での承認に至るまで、各段階での判断はすべてが連動しており、どれか一つでも曖昧になれば、工事の品質や住民の満足度に直結するリスクを伴います。工事が始まってからは、住民の日常生活への影響を最小限に抑える工夫や、施工の透明性・品質を担保する監理体制の整備、トラブル時の柔軟な対応など、現場対応力が問われますが、こうした運営の質も、準備段階での段取りがしっかりしていればこそ機能するものです。加えて、修繕には技術的な判断や専門的な知見が求められる場面が多いため、経験豊富なコンサルタントや責任感のある施工業者との協働体制を築くことは、品質確保だけでなく理事会の負担軽減、住民からの信頼確保にもつながります。
大規模修繕は決して一度きりの対応で終わるものではなく、マンションが長く快適に維持されるための持続的な取り組みの一部であり、その姿勢次第でマンションの将来的な資産価値にも大きな影響を与えることになります。だからこそ、工事を単なる義務や負担として捉えるのではなく、これを機に建物の性能や居住性を高め、住民同士の理解と連帯感を育む「未来づくりのチャンス」と前向きにとらえ、理事会と住民が一体となって進めていくことが、結果として満足度の高い修繕工事の成功に結びついていくのです。