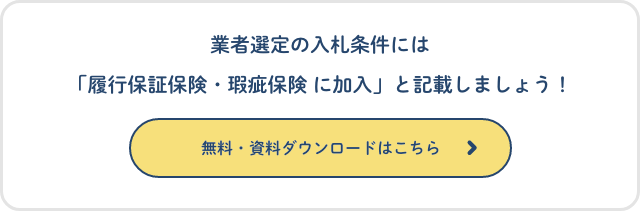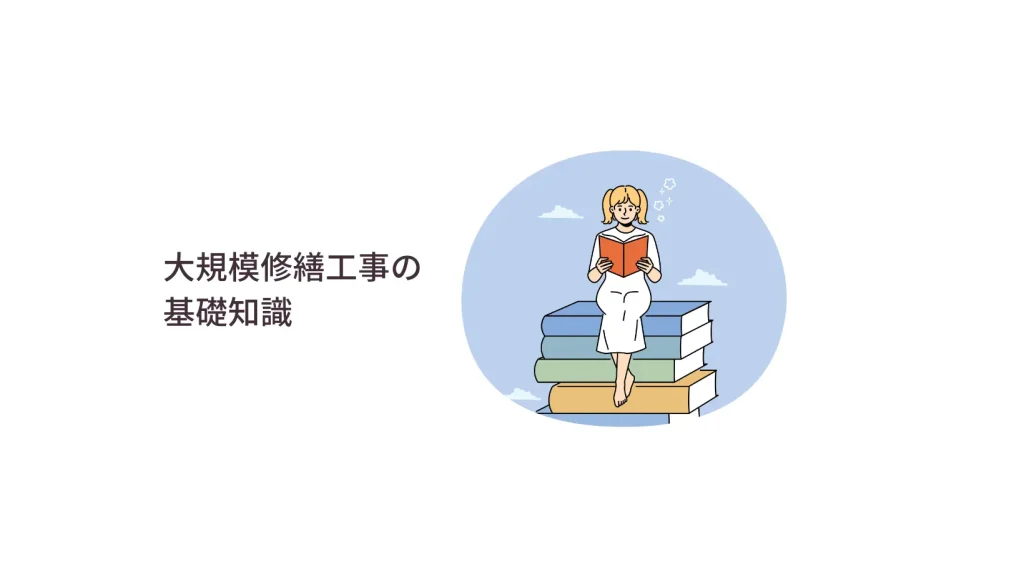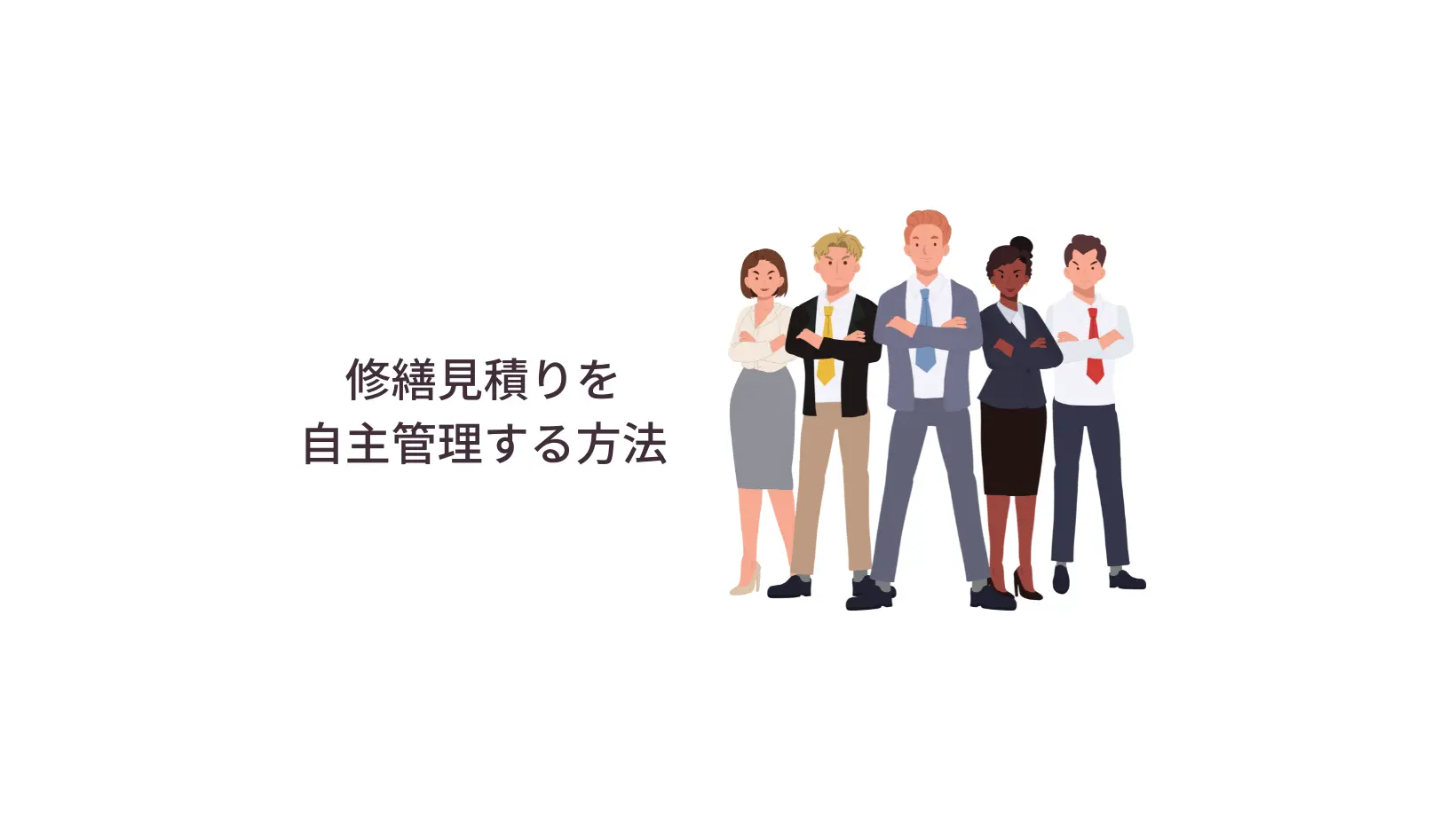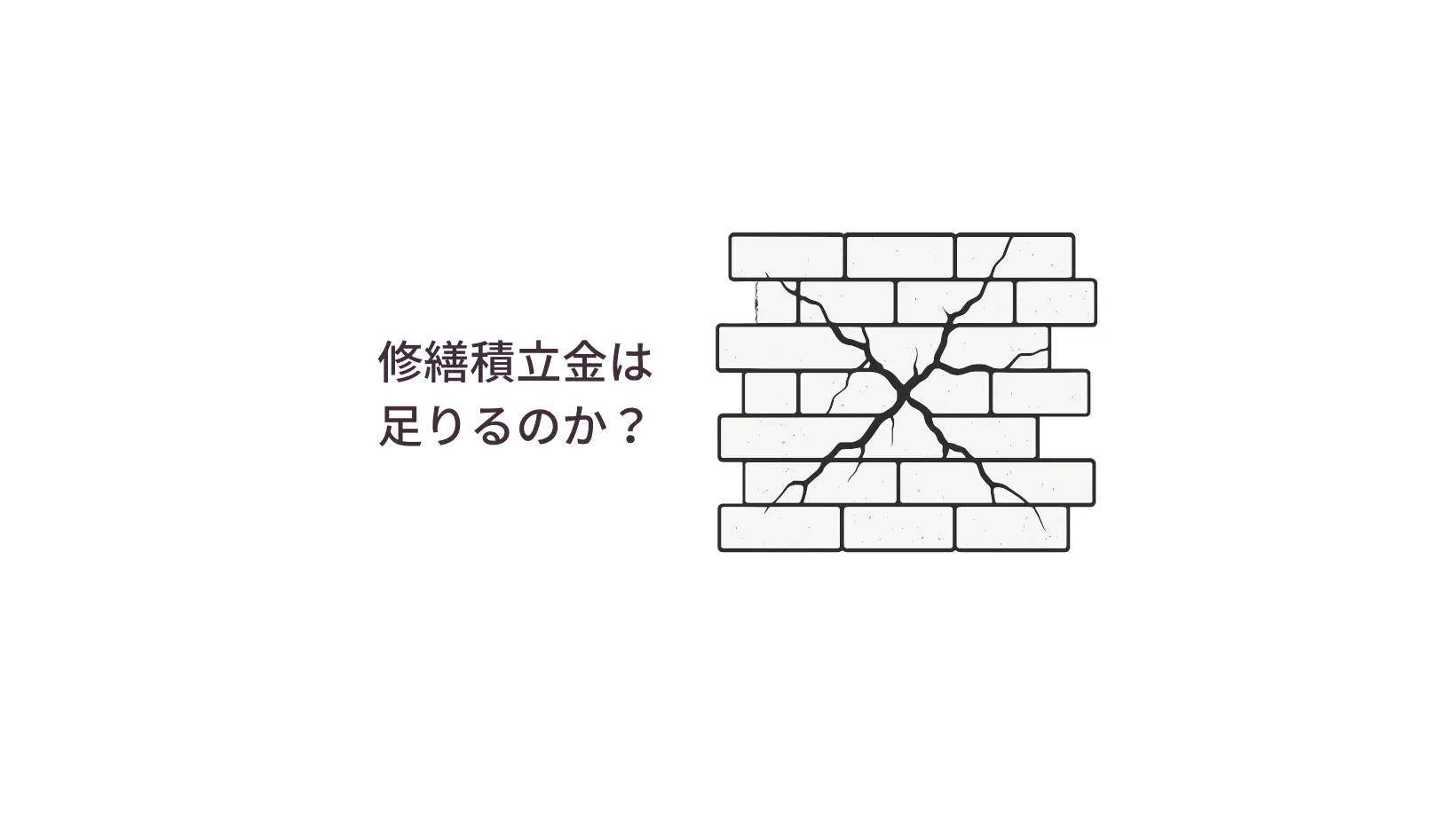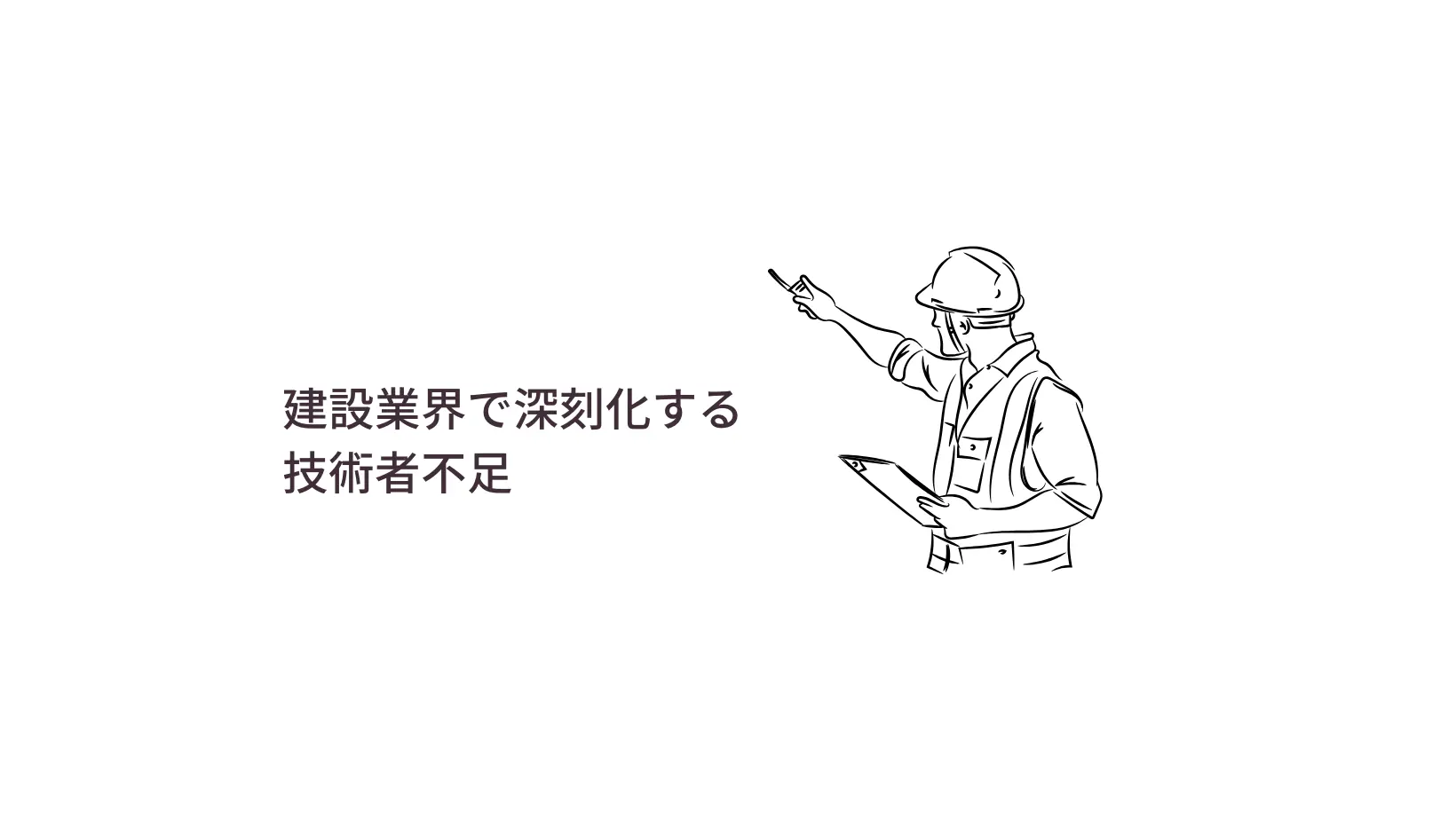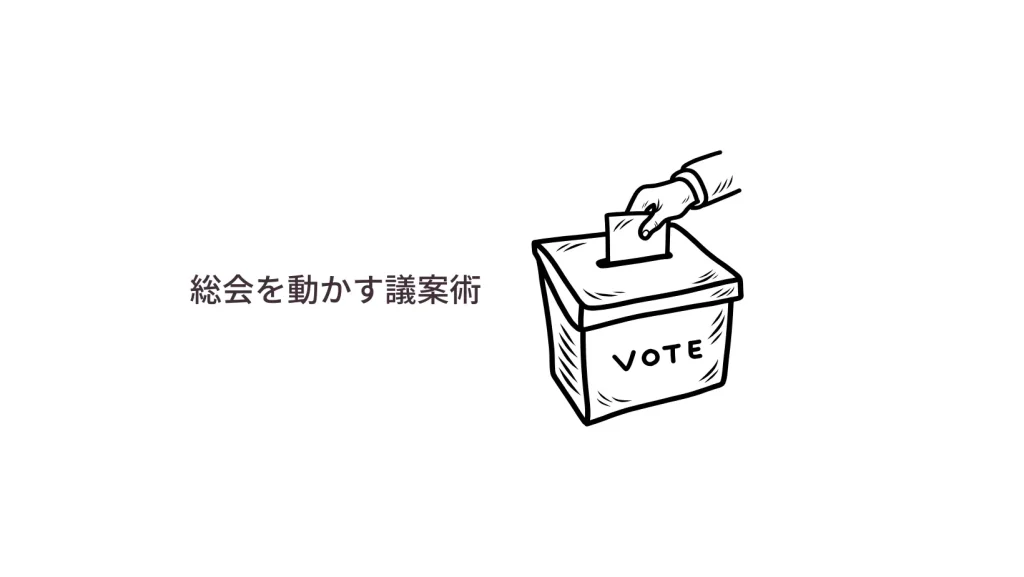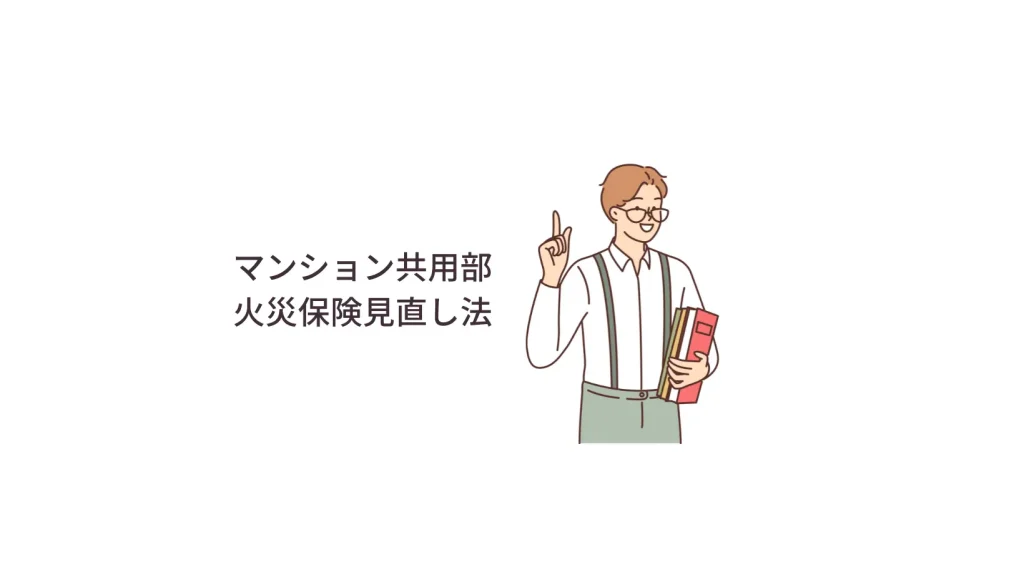こんにちは!事務所が渋谷にある、渋谷貴博です。
私は35年間マンション業界で働いてきました。またプライベートでは、マンション(埼玉県さいたま市・総戸数812戸)に住んで、修繕委員、副理事長、理事長経験があります。そんな私が管理組合役員の皆さまの役に立つ情報を発信します。
マンションにおける「大規模修繕工事」は、建物の価値と安全性を維持するために欠かせない重要なイベントです。しかし、実施は12~15年に一度とされ、しかも数千万円から数億円規模の費用を伴うため、多くの理事にとって「初めて経験する未知の業務」となります。特に管理組合の新任役員にとっては、何から着手すれば良いのか、何に注意すればよいのか、不安も大きいのではないでしょうか。
本ブログでは、これから大規模修繕工事を計画・実施しようとするマンション管理組合の役員の皆さまに向けて、「大規模修繕とは何か?」という基本的な部分から、その目的、進め方、費用、実施時期の目安までを体系的に解説します。正しい知識を身につけ、理事会が主導して修繕工事を成功に導けるよう、実践的な視点でまとめました。
大規模修繕工事の目的と実施サイクルを理解する
大規模修繕工事とは、マンションにおける共用部分の機能を回復・維持し、将来にわたって安全・快適な居住環境を保つために定期的に行う大規模な改修作業を指します。建物は年数の経過とともに確実に劣化していきますが、適切なタイミングで的確な修繕を施すことにより、劣化の進行を抑制し、マンション全体の資産価値を維持・向上させることが可能となります。
対象となるのは主に「共用部分」です。具体的には、外壁や屋上、バルコニー、廊下、階段、エントランスホール、給排水管、鉄部、駐車場、防水層、シーリング材などが含まれます。これらの部位は、風雨・紫外線・温度変化・経年使用などによって徐々に劣化していくため、一定の周期で点検・補修・更新が求められます。居住者の目につきやすい美観の維持だけでなく、目に見えない部分の機能維持が重要な目的です。
一般的に、大規模修繕工事は新築後12~15年で第1回目を実施し、その後は約12~15年ごとに周期的に行うことが望ましいとされています。この目安は国土交通省のガイドラインや長期修繕計画のモデルに基づいており、劣化進行の傾向、材料の耐用年数、過去の施工実績を踏まえて策定されています。ただし、このスケジュールは絶対的なものではなく、建物の構造・立地環境・管理状態・施工履歴など、それぞれのマンションによって前後することもあります。
実際には、管理組合が策定する「長期修繕計画」に基づいて、大規模修繕のタイミングや内容、必要な修繕積立金の見込みを調整しながら計画的に進めるのが一般的です。しかし、計画通りに資金が積み立てられていなかったり、劣化が想定以上に進んでいたり、逆に劣化が軽微だったりするケースもあります。そのため、定期的な建物診断を通じて状況を客観的に把握し、必要に応じて修繕の時期や範囲を柔軟に見直すことが求められます。
大規模修繕工事の最大の目的は適切な建物維持管理を行うことにより「資産価値の維持・向上」と「居住者の安心・安全・快適な暮らしの確保」をすることです。外壁タイルが劣化して剥離すれば落下事故の危険があり、防水層の劣化が進行すれば、雨水が建物内部に浸入し、鉄筋の腐食やコンクリートの爆裂を引き起こす恐れがあります。また、給排水管の劣化によって漏水事故が発生すれば、上下階の居住者とのトラブルに発展することも考えられます。このような事態を未然に防ぐためにも、定期的な修繕は欠かせないのです。
さらに、こうした物理的な機能回復に加えて、近年の大規模修繕工事では「価値を高める工事」への関心が高まっています。たとえば、外壁塗装の色味を変更してマンション全体の印象を刷新したり、共用廊下やエントランスをLED照明に切り替えて省エネ性能を高めたり、防犯カメラやオートロック設備を更新してセキュリティ性能を向上させるといった、「性能向上型」の修繕です。
また、高齢化が進む中で、スロープや手すりの設置などバリアフリー対応を含めた工事を実施する事例も増加しています。これらの取り組みは、単なる修繕の枠を超えて、建物の“進化”を目指すものと言えるでしょう。築年数が経過しているマンションでも、こうした工事を実施することで、新築と変わらない魅力を維持することができ、将来的な空室リスクや資産価値の低下を防ぐうえでも有効です。
したがって、大規模修繕工事は単なる「延命措置」ではなく、マンションを再生させる絶好の機会と捉えるべきです。将来の住環境や資産価値をどのように維持・発展させていくのかという視点を持ち、12年~15年先、さらにその先を見据えた中長期戦略的な意思決定を行うことが、管理組合の大きな役割となります。そのためには、居住者全体での合意形成を丁寧に行いながら、将来を見据えた修繕計画を着実に実行していくことが何よりも重要です。
《出典》国土交通省ガイドライン 80ページ「外壁の塗装や屋上防水などを行う大規模修繕工事の周期は、一般的に12~15年程度」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001747006.pdf

大規模修繕工事の進め方と理事会の役割
大規模修繕工事は、通常1~2年にわたる準備期間を要する長期的なプロジェクトです。理事会が中心となって主体的に計画を立て、段階を踏んで進めていくことが求められます。経験の少ない理事が中心となるケースも多いため、適切な助言者の活用や、外部専門家との連携も重要です。ここでは、大規模修繕工事の一般的な進行ステップを、時系列に沿って詳しく解説します。
1. 現状調査と長期修繕計画の見直し
まず最初に着手すべきは、建物の現状を正確に把握することです。これには、目視点検だけでなく、外壁タイルの打診調査、コンクリートの中性化試験、屋上やバルコニーの防水層の浸水検査など、専門的な調査も必要となります。調査は管理会社や設計事務所などに依頼し、報告書として劣化状況を可視化することが重要です。
この調査結果に基づき、既存の長期修繕計画の見直しも検討されます。多くのマンションでは築年数とともに劣化の速度や状況が変化しているため、計画時点の予想と現実が乖離していることも少なくありません。また、建築資材や施工単価の上昇、法改正、住民ニーズの多様化なども考慮すべき要素です。
加えて、修繕の対象範囲を限定するのではなく、「将来のトラブル予防」や「性能向上」も視野に入れて、今行うべき修繕と次回以降に回せるものを精査する必要があります。ここでの判断がその後の全体予算やスケジュールに大きく影響を与えるため、理事会の的確な判断が求められます。
2. コンサルタント(設計監理者)の選定
調査結果をもとに修繕計画を策定する段階では、外部の専門家である「修繕コンサルタント(一級建築士事務所)」の活用が強く推奨されます。中立的な立場で理事会を支援し、談合の排除や工事品質の担保、住民説明の補助など、工事全体の透明性を高める役割を担います。
特に近年は「設計監理方式」を採用する管理組合が増えています。これは、設計(調査・仕様書作成・業者選定支援)と監理(工事中の品質・工程管理)を専門家に任せ、施工業者とは分離する方式です。この手法を用いることで、コストの透明化、公正な業者選定、第三者による品質管理が実現できるため、工事全体の信頼性が飛躍的に向上します。
コンサルタントの選定は、複数の設計事務所やコンサル会社からプレゼンテーション(プロポーザル)を受ける「コンペ方式」が一般的です。選定基準としては、過去の実績、マンション規模や築年数に応じた対応経験、報酬体系の明瞭性、質疑への対応力などが挙げられます。また、理事会との相性やレスポンスの速さも長期間の協働において非常に重要なポイントとなります。
コンサルタントの存在は、理事会にとって心強い助けとなるだけでなく、住民の信頼感を高める要素にもなります。「第三者の専門家が関与している」という事実が、修繕工事の正当性を担保し、理事会の意思決定の裏付けとなるのです。
しかし、昨今では施工業者やコンサルタント、管理会社などが関係する談合問題がニュースとなって、一部では管理組合の大切な修繕積立金を掠め取るようなトラブルが発生しています。こういったリスク、トラブルには巻き込まれないように十分に注意をしてコンサルタントの選定を行いましょう。
コンサルタント選びについて詳しく説明している当センターのブログを以下に紹介しますので参考にご覧ください。
【完全解説】大規模修繕工事コンサルタントの役割と選び方
https://mansion-anshin.com/archives/2050620/
3. 工事内容の決定と業者選定
次のステップは、どの範囲を修繕するか、どの工法を用いるかといった「工事内容の精査」です。ここでは、コンサルタントと共に調査結果と住民ニーズ、予算のバランスを取りながら、仕様書と設計図を固めていきます。
例えば、防水工事ひとつとっても、アスファルト防水・ウレタン塗膜防水・シート防水などの工法があり、それぞれ耐用年数やコストが異なります。また、外壁改修では、全面補修と部分補修の選択、シーリング材の種類、塗装仕上げのグレード選定など、数多くの技術的判断が必要となります。
仕様書が決定したら、複数の施工業者に見積もりを依頼する業者選定の入札を実施します。このとき、単なる価格比較ではなく、施工体制、管理体制、過去の施工実績、施工中の安全対策、アフターサービスの内容など、総合的な視点での評価が求められます。
加えて、現在は建設業界全体で倒産リスクが増加しているため、工事契約時には「履行保証保険」の活用が強く推奨されます。これは、施工業者が工事途中で経営破綻した場合に備えて、第三者機関(損害保険会社)が、残工事の完成や追加費用の補償を行う保険制度です。また、「瑕疵保険」も推奨します。これは国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、工事完了後に施工した部分から雨漏りやタイル剥落など瑕疵・施工ミスが発生した場合に、その修補費用の補償を行う保険制度です。この二つの保険制度に加入するのは施工業者ですが、任意保険のため、管理組合など発注者側から加入リクエストをすることでスムーズに保険加入がされます。また、これらはマンションあんしんセンターなどが保険代理店として提供しているサービスです。こうした制度を導入することで、管理組合は万一の事態に備えた安全装置を確保できます。
履行保証保険や瑕疵保険についての詳しい情報は、以下の公式ページからご確認いただけます。
- 一般社団法人マンションあんしんセンター:
https://mansion-anshin.com/ - 日新火災 履行保証保険:
https://www.nisshinfire.co.jp/sustainability/initiatives/mansion-sale/ - 住宅あんしん保証 瑕疵保険:
https://www.j-anshin.co.jp/service/daikibo/
4. 総会決議と工事契約
工事内容と施工業者が決定した後は、管理規約に基づいて総会での承認を得る必要があります。大規模修繕工事は特別決議事項に該当するケースもあるため、事前の住民説明会を通じて丁寧に情報提供を行い、理解と賛同を得るプロセスが不可欠です。
説明会では、専門的な図面や見積もりをわかりやすく噛み砕いて説明し、質疑応答の時間を十分に確保することが成功の鍵となります。住民からの不安や反対意見には真摯に向き合い、必要に応じて計画の一部を見直す柔軟性も持つことが大切です。
総会で承認が得られたら、正式な契約書を交わし、契約条件や保証内容、支払いスケジュール、瑕疵対応などを明文化します。これにより、理事会と施工業者との間の責任関係を明確にし、トラブル予防につながります。
5. 工事開始と施工監理
工事が始まると、日々の現場対応や住民対応が本格化します。特に居住中工事では、足場の設置、仮設設備、工事車両の出入りなどが日常生活に影響を与えるため、丁寧な周知とクレーム対応が求められます。
掲示板やチラシの活用、LINEやウェブ掲示板などのITツールによる情報発信も有効です。施工会社との定例会議を通じて進捗や課題を共有し、理事会が住民と施工側の橋渡し役となって円滑な運営を図りましょう。
工事中はコンサルタントが監理者として現場に関与し、設計通りの施工が行われているか、工程が守られているかを定期的に確認します。こうした第三者の監理が入ることで、品質の担保はもちろん、万一のトラブルや施工不良の早期発見にもつながります。
6. 完了検査と引渡し、アフター対応
工事が完了したら、竣工検査を実施します。ここでは、仕様書通りに施工が完了しているか、不具合がないか、保証書や施工記録の整備状況を確認します。必要に応じて補修を指示し、最終的な検収と引渡しを行います。
引渡し後も重要なのが「アフターサービス」です。保証期間や補修体制の内容を理事会で把握し、住民に周知しておくことが大切です。また、定期的な点検や補修をスケジュールに組み込むことで、長期的な維持管理の基礎が整います。
理事会はこのタイミングで全体の記録を整理し、次回以降の理事や修繕委員会に向けて引き継ぎ資料を作成しておくと、マンションとしての管理力向上にもつながります。
まとめ|理事会主導で修繕の成功を
大規模修繕工事は、単に建物を直すだけではなく、マンションの価値や住民の生活の質を左右する重要なイベントです。そして、その成功は「理事会がどれだけ主体的に取り組むか」にかかっています。
本ブログでご紹介したように、大規模修繕工事には明確な目的があり、実施には入念な準備と計画、そして住民との合意形成が必要です。特に、設計監理方式の導入や、履行保証保険などの活用は、近年の複雑化する修繕事情において理事会の負担を軽減し、リスクを回避する有効な手段です。
初めて理事となり不安を抱えている方も、基本的な流れと考え方を理解すれば、自信を持って対応できるようになります。必要に応じて信頼できる専門家の支援を得ながら、住民の信頼を得て、安心・安全・快適なマンション環境を将来へとつなげていきましょう。