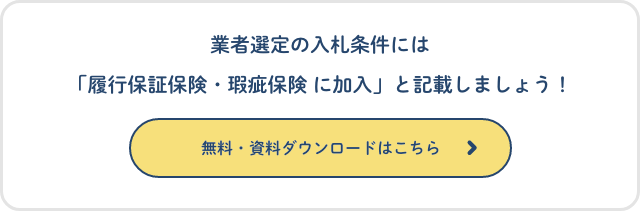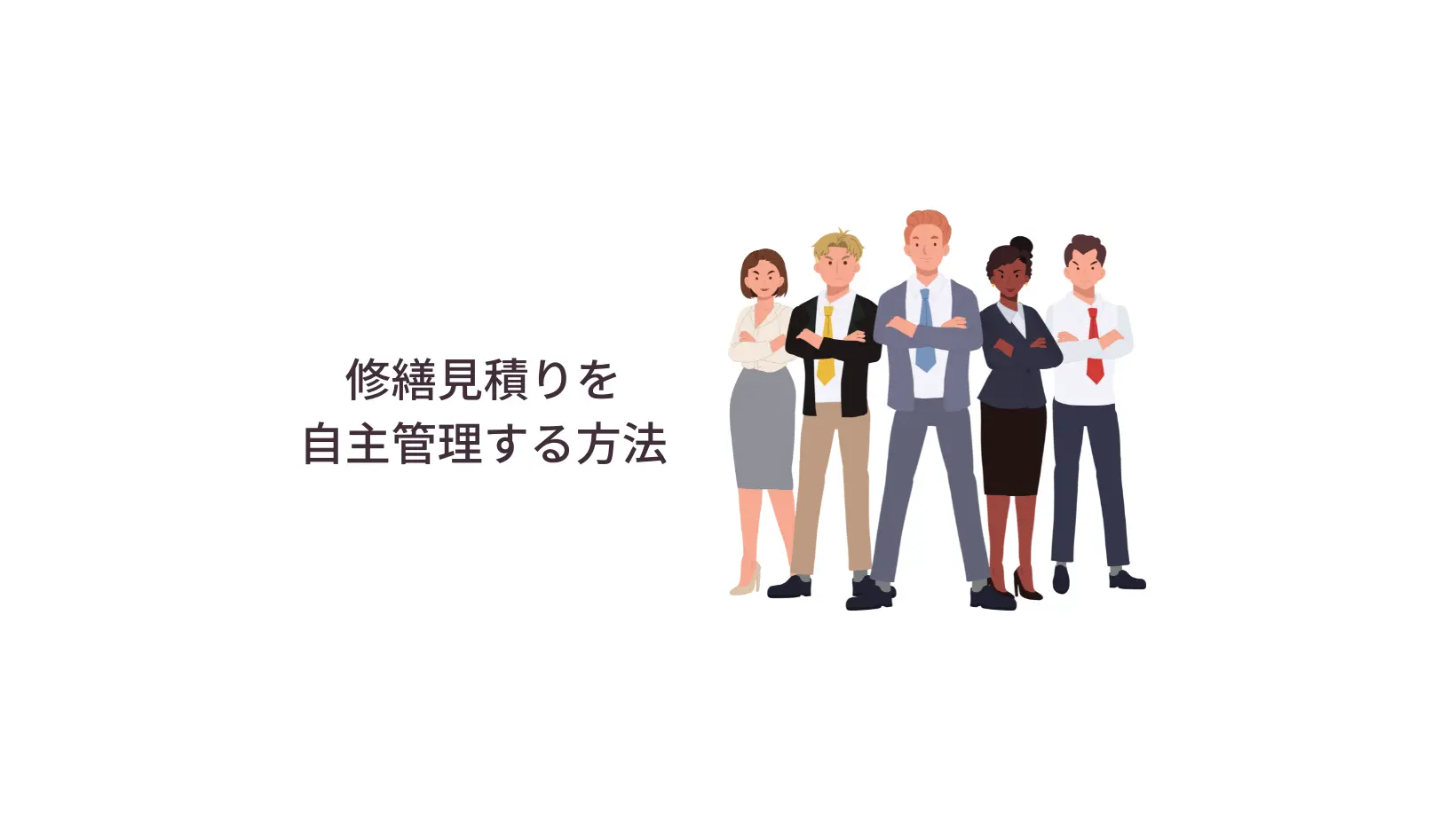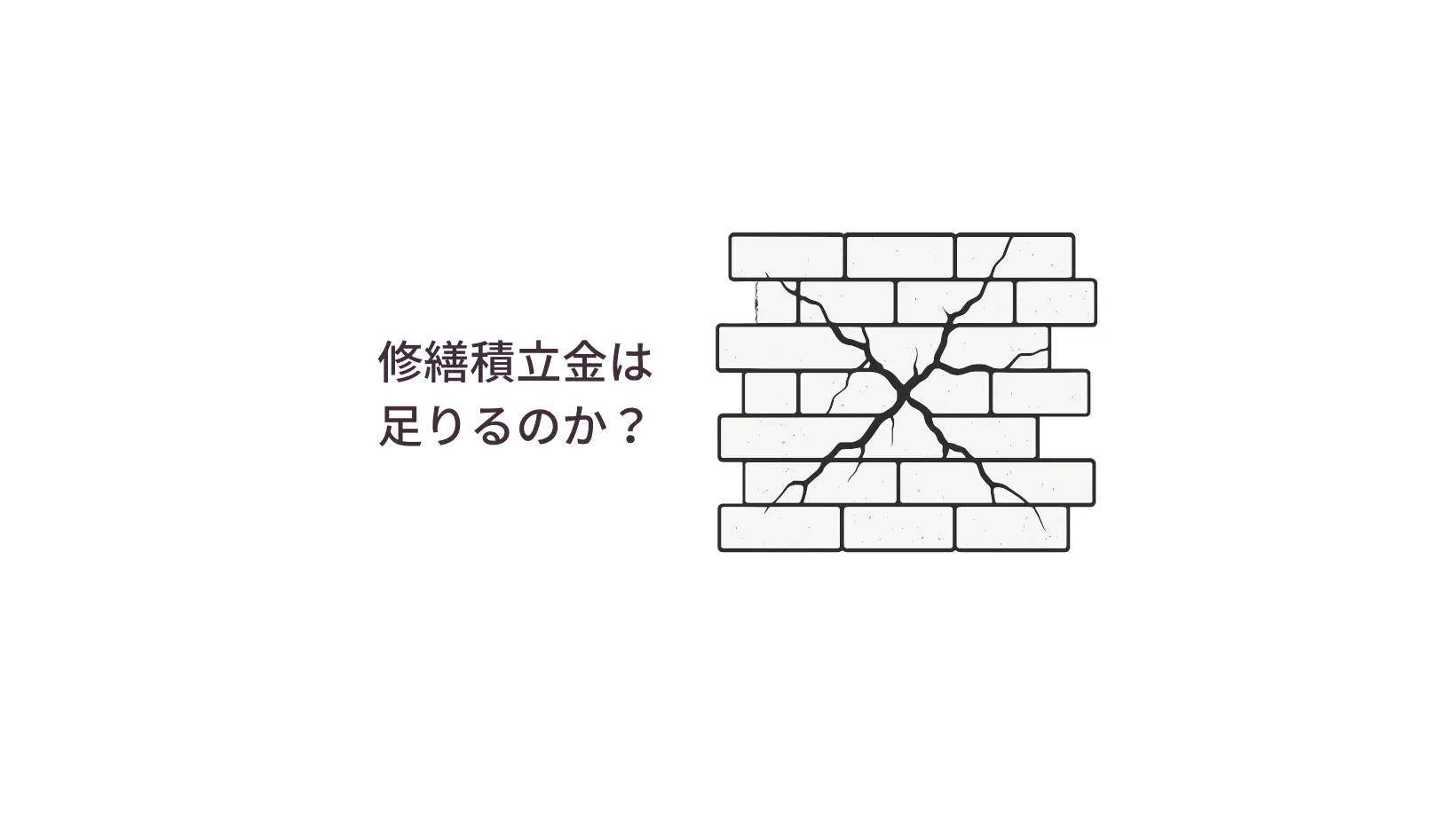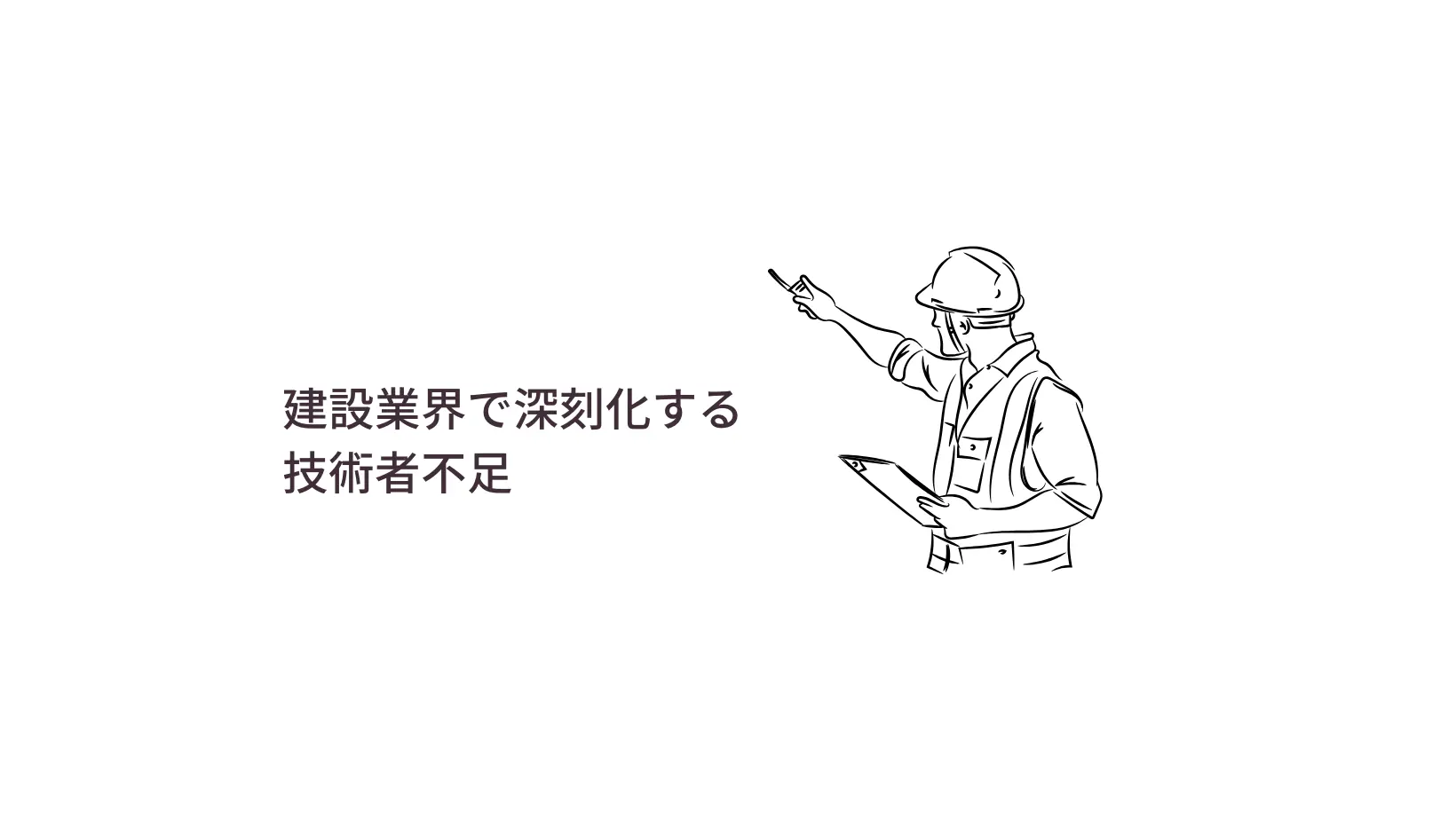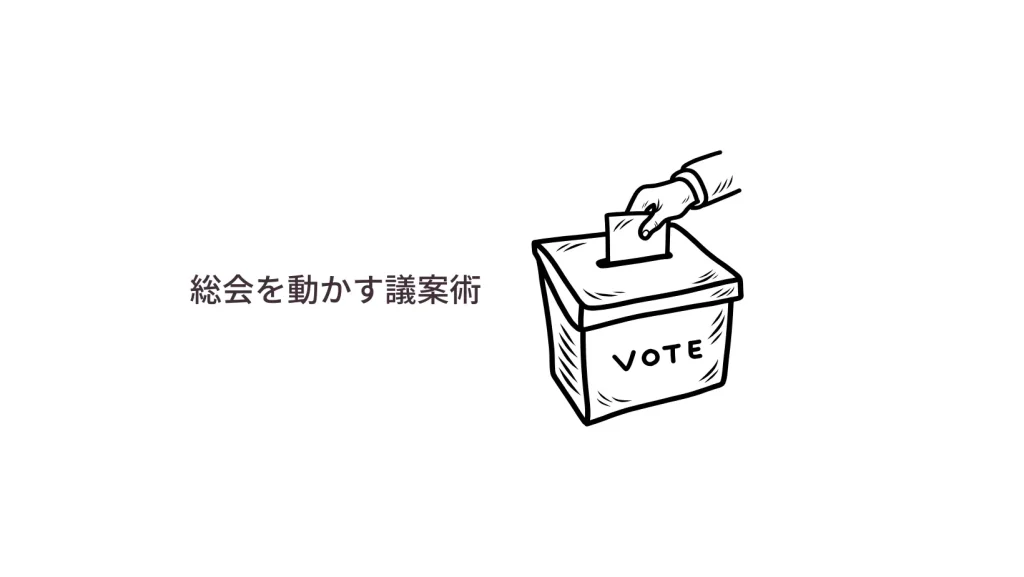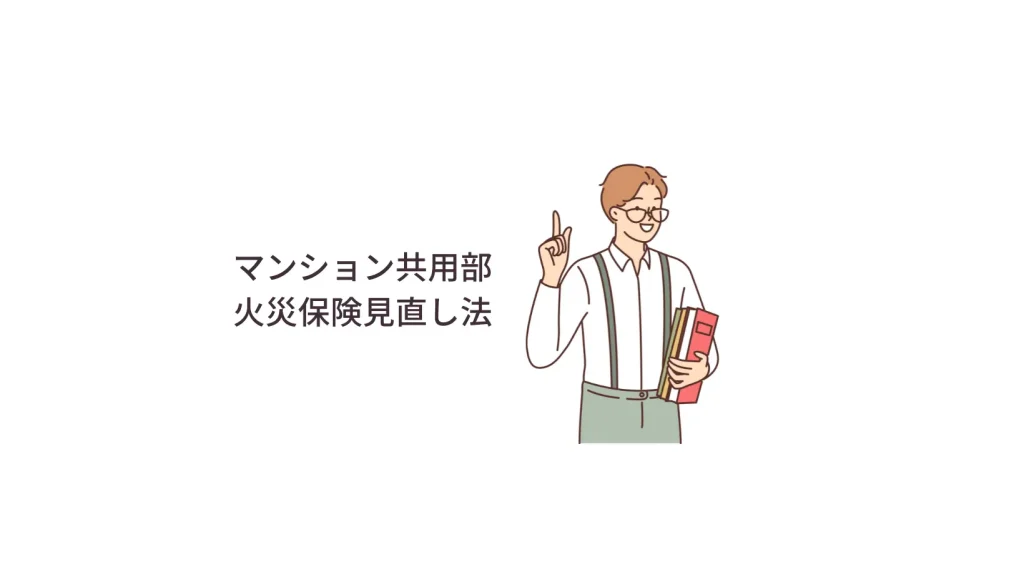こんにちは!事務所が渋谷にある、渋谷貴博です。
私は35年間マンション業界で働いてきました。またプライベートでは、マンション(埼玉県さいたま市・総戸数812戸)に住んで、修繕委員、副理事長、理事長経験があります。そんな私が管理組合役員の皆さまの役に立つ情報を発信します。
修繕周期を「固定」ではなく「長期化」する時代へ
マンションの大規模修繕工事といえば、長年「おおむね12年ごとに行う」というのが一般的な考え方でした。国土交通省がかつて発行したガイドラインにも12年周期が標準として記載されていたため、多くの管理組合が「12年でやるのが当たり前」と信じてきたのです。
しかし、ここ数年でこの“常識”は大きく変わりつつあります。近年の建材性能の向上、居住者負担の増加、工事費高騰、そして修繕積立金不足といった複合的な事情により、「年数を固定する修繕」から「建物の状態で柔軟に長期化する修繕」への転換が進んでいます。
かつてのように「経過年数=劣化進行」と単純に考える時代ではありません。例えば、同じ築15年のマンションでも、立地条件や形状、施工品質、管理の丁寧さによって劣化の進み方は大きく異なります。海に近い塩害地域では鉄部の腐食が早く、日当たりの悪い北面では防水層の寿命が長くなることもあります。建物を“年齢”で判断するのではなく、“健康状態”で判断する時代に入っているのです。
国土交通省が2021年に改訂した「長期修繕計画作成ガイドライン」でも、周期はあくまで目安であり、定期的な劣化診断をもとに柔軟に見直すことが推奨されています。つまり、12年周期という数字は「基準」ではなく、あくまでも「参考値」に過ぎず、各管理組合が自らの判断で周期を最適化することが求められているのです。
国土交通用ガイドラインの概要
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425184.pdf?utm_source=chatgpt.com
周期を延ばすことで得られる管理上のメリット
修繕周期を見直す最大の目的は、限られた資金をより効率的に活用することです。周期を延ばすことで、まず得られるのは修繕積立金の蓄積余裕です。多くのマンションで問題となっているのが「工事費は上がっているのに、積立金が足りない」という現実です。周期を15年程度に延ばせば、積立期間が3年分増えるため、財源に余裕が生まれます。資金にゆとりがあれば、突発的な補修費にも対応しやすくなり、組合会計の安定にもつながります。
また、周期を延ばすことで、過剰修繕を避けられるという利点もあります。周期を固定してしまうと、まだ使用可能な塗装や防水を早めに更新するケースが少なくありません。つまり、性能が残っているのに交換してしまう「もったいない修繕」が起こるのです。これを防ぐには、劣化診断による科学的な判断が不可欠です。状態を確認し、「あと何年持つか」を見極めてから修繕することで、工事コストの総額を抑えることができます。
さらに、周期を延ばすことで技術革新の恩恵を受けやすくなるという側面も見逃せません。近年の建材や防水材は、従来よりも耐久性が高く、20年以上の寿命を持つ製品も増えています。特にイニシャルコストの高い高耐久材ではなく、そういった期待耐用年数の長い一般防水材(材料)を使用しつつ、高品質の施工技術を活用すれば、将来的な修繕回数そのものを減らすことも可能です。つまり、「材料」よりも「施工技術」が大切なのです。
このように、周期を延ばす判断は単なる先送りではなく、「より合理的な修繕サイクルの設計」であり、資金・品質・持続性の三拍子を整えるための戦略的選択と言えます。それを実現することで、60年間で12年周期の場合は5回の大規模修繕工事を行うものも、15年周期にするだけで4回に減らすことができるのです。このように管理組合の限られた資金は有効に使用しましょう。
周期を延ばす際に注意すべきリスクと対処法
ただし、周期延長には明確な注意点も存在します。延ばすことばかりに意識が向くと、劣化の進行を見落とすリスクが高まるからです。防水層の亀裂や外壁タイルの浮きなどは、初期段階では目視では判断しにくく、放置すれば補修範囲が拡大し、結局次の修繕時に余分なコストが発生する可能性があります。
こうしたリスクを避けるために必要なのが、定期的な劣化診断です。目安として3年に一度は専門家による外観調査や赤外線診断、打診検査などを実施し、劣化傾向をデータで把握しておくとよいでしょう。点検の結果をもとに、「延長しても問題ない部位」と「部分補修が必要な部位」を分けて考えることが大切です。
もう一つのポイントは、周期延長の決定を理事会だけで行わないことです。管理組合全体で合意形成を図ることが重要であり、特に総会での説明が欠かせません。単に「積立金が足りないから延ばす」という理由では、居住者の理解は得られません。「劣化診断の結果、構造上問題がないことが確認されたため」「必要な補修を実施した上で延長する」というように、科学的根拠を示して納得を得ることが信頼を生みます。
さらに「周期延長」は数十年と続く取り組みとなるため、できるだけ多くの居住者で共有して進める必要があります。そのためには、総会だけではなく、毎年「周期延長」について翌年以降の理事会へ継承することが必須となります。
また、延長中は小規模補修の積極的実施が欠かせません。排水溝や手すり、防水端末などの軽微な部分を日常点検で補修しておけば、劣化の広がりを防げます。延ばすためには「何もしない期間」をつくるのではなく、「適度に手をかけながら持たせる」という意識が大切です。こういった対応方法についても翌年以降の理事会に引き継いでいくことが大切です。

周期を短縮すべきケースとその判断基準
一方で、すべてのマンションが周期延長に向いているわけではありません。建物の環境や過去の施工品質によっては、むしろ早めの修繕が必要なケースもあります。例えば、海沿いの地域では塩害による鉄部の腐食が早く、幹線道路沿いでは排ガスの影響で塗膜劣化が進みやすくなります。これらのマンションでは、12年を待たずに外壁や鉄部塗装を更新する方が、結果的にコストを抑えられることがあります。
また、初回の修繕工事が遅れたマンションや、施工時に品質上の問題があった場合も注意が必要です。防水層が薄かったり、下地処理が不十分だったりすると、想定よりも早く劣化が進行します。そのまま放置すると、漏水や構造部材の損傷につながる危険があります。
さらに、修繕周期の短縮を検討すべきもう一つの理由は、設備更新との重複です。共用部の給水ポンプや照明、インターホン設備などが同時期に寿命を迎える場合、外装工事と合わせて実施することで、足場費用などの重複支出を防ぐことができます。周期を「短くする」判断は、単なる緊急対応ではなく、総合的な工事効率を高めるための戦略でもあるのです。
周期見直しのための実践的な手順
周期見直しを実行する際は、まず建物の劣化診断を行うことが第一歩です。外壁や防水、鉄部など各部位ごとの劣化度を点検し、専門家の評価に基づいて延長・短縮の可能性を検討します。赤外線調査やコンクリート中性化試験などの科学的手法を用いれば、目視では見えない問題も早期に把握できます。
次に、診断結果を踏まえて長期修繕計画の見直しを行います。周期を15年に延ばすのか、14年に調整するのかなど、現実的な数値を設定し、工事項目ごとのスケジュールを再構築します。この段階で修繕積立金の収支も見直し、今後の資金繰りが安定するよう調整します。周期を延ばしたことで浮いた資金は、将来の外構改修や設備更新などに回すこともできます。
最後に、居住者全体への説明と合意形成を行います。周期の変更は管理規約上の大きな判断であるため、透明性を持ったプロセスが欠かせません。総会で修繕委員会や専門家の報告を提示し、劣化診断結果と判断理由を明確に示すことで、理解と信頼を得ることができます。この一連の流れを経ることで、「理事会が独断で延ばした」といった誤解を防ぎ、組合運営の健全性を保てます。
まとめ:周期の見直しは、未来への“投資判断”
大規模修繕工事の周期を見直すということは、単に工事の時期を変えることではありません。それは、建物の寿命を最大限に延ばし、修繕積立金を有効に使い、将来の安心を確保するための“投資判断”です。
周期を延ばすにしても、短縮するにしても、その根拠は必ず「劣化診断」に基づかなければなりません。勘や慣習ではなく、データと専門的評価をもとに判断することで、納得感のある意思決定が可能になります。
そして、管理組合が主体的に考え、透明なプロセスで住民に説明することが、最終的に資産価値を守る力になります。修繕周期を見直すという行為は、過去の常識を疑い、より良い未来を設計する知的な取り組みです。これからのマンション管理は、「何年ごとにやるか」ではなく、「建物の状態を見て、最適な時期を選ぶ」ことが成功の鍵になります。
周期を見直す勇気は、住民の暮らしと資産を守る最大の防衛策です。時間に縛られず、データに基づき、合理的に判断する。これこそが、これからの時代に求められる“賢い修繕計画”のあり方です。
マンションあんしんセンターの管理組合サポートブログはコチラ
https://mansion-anshin.com/blog/