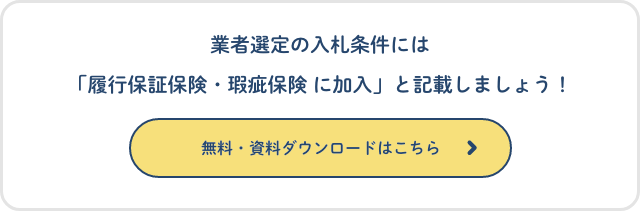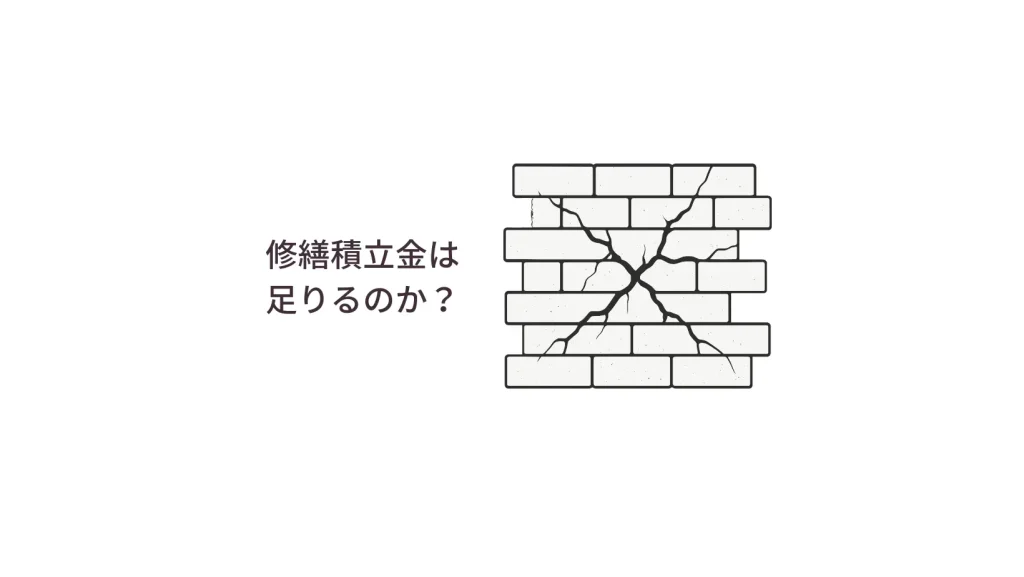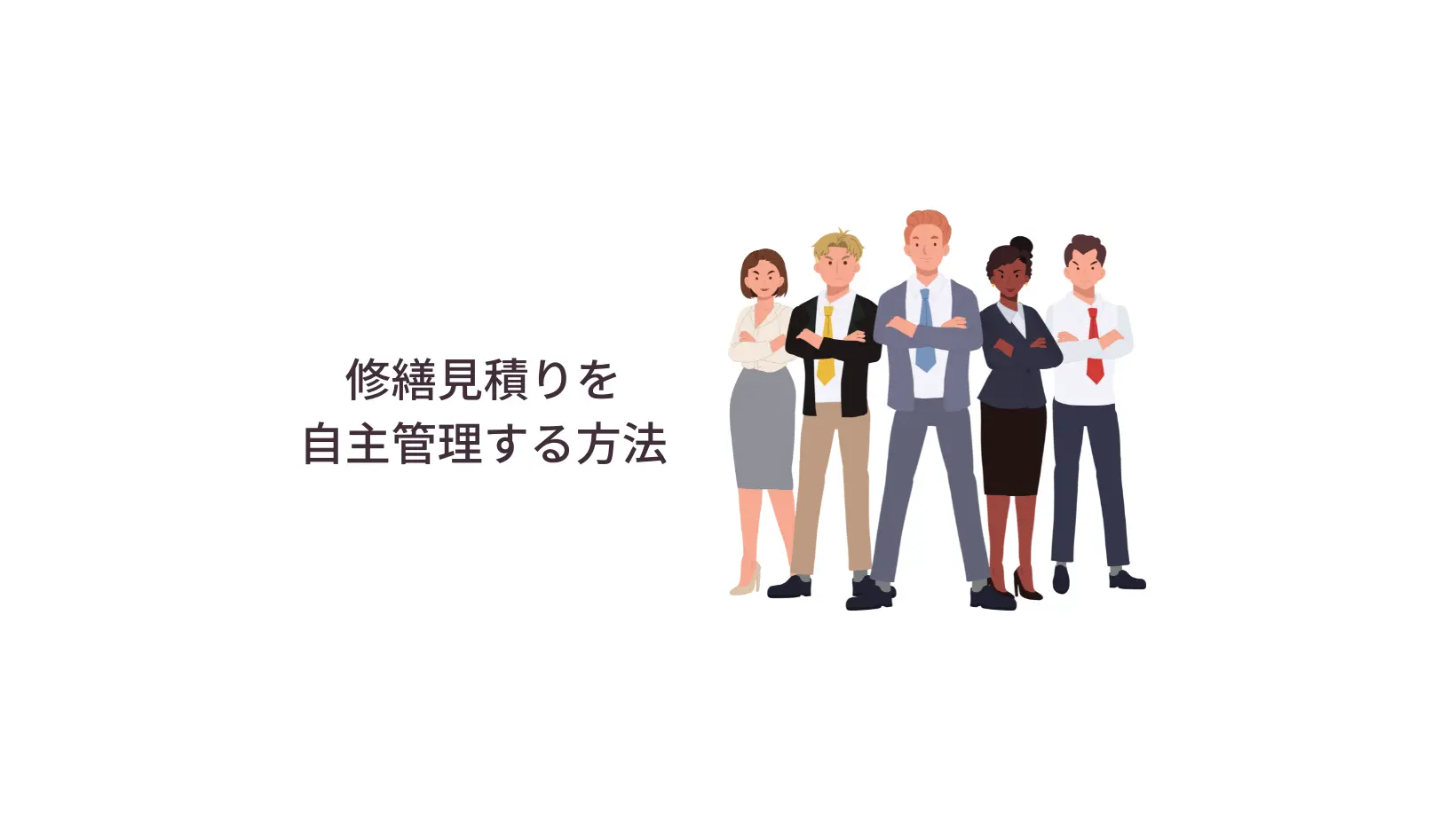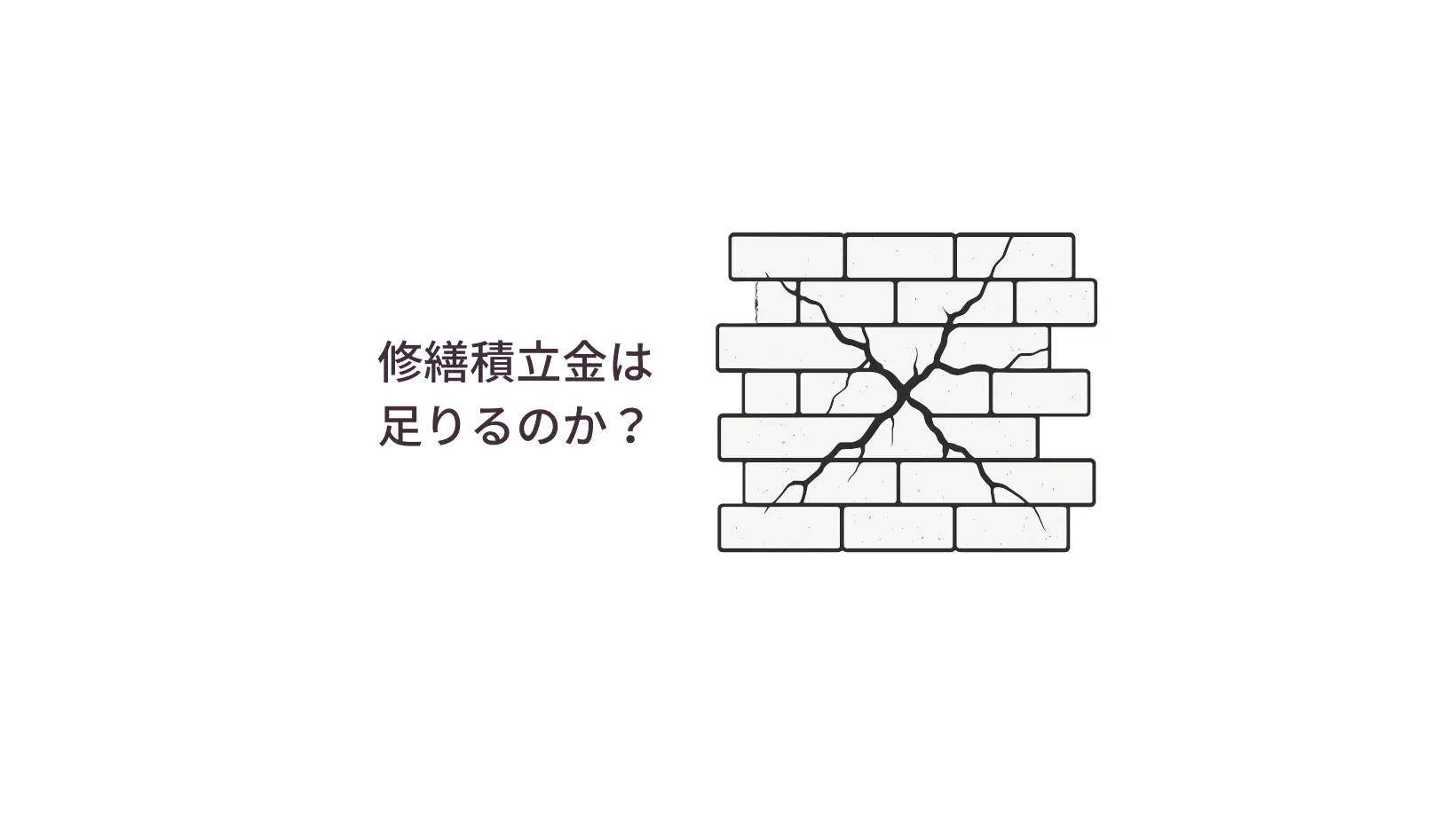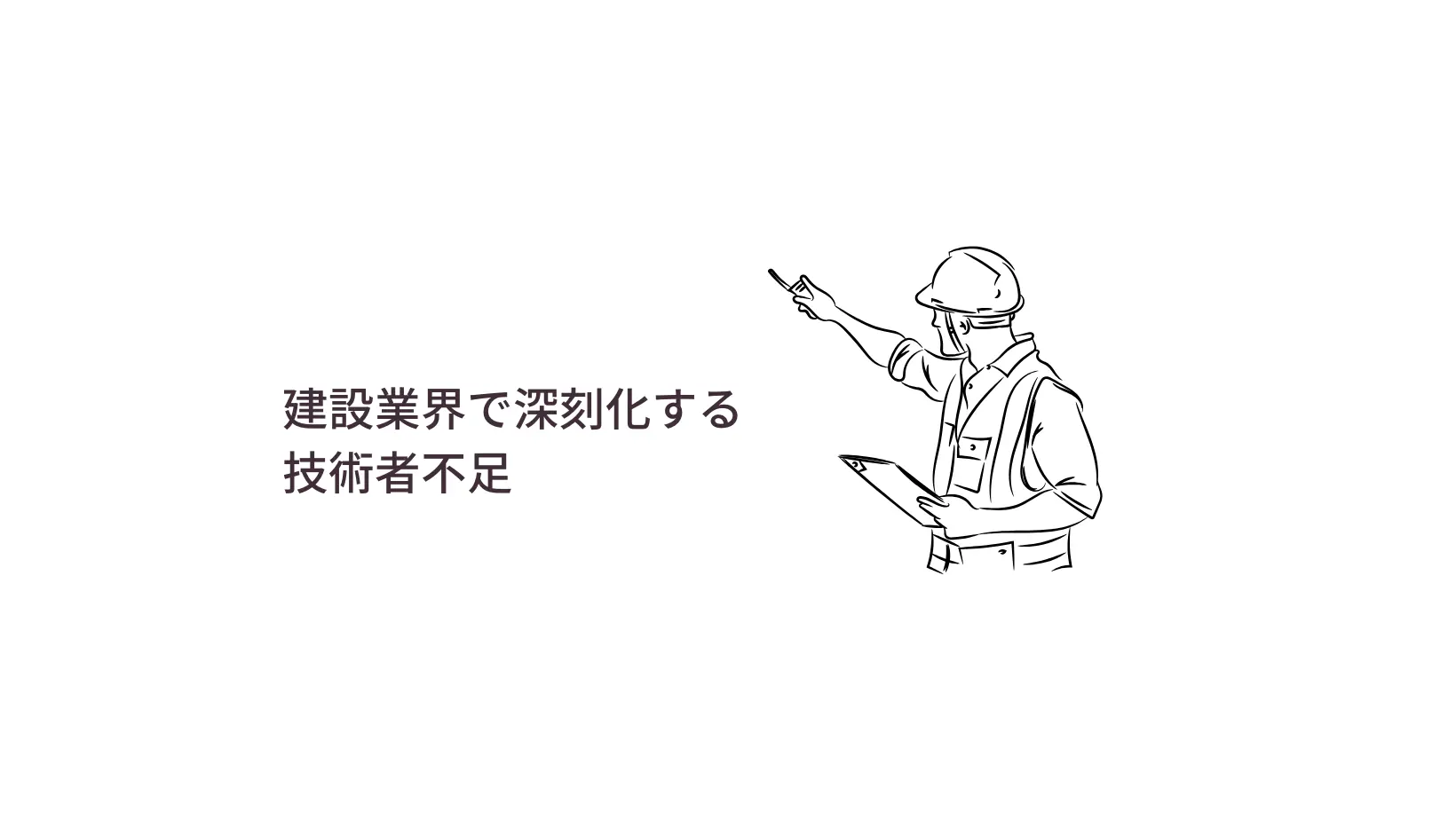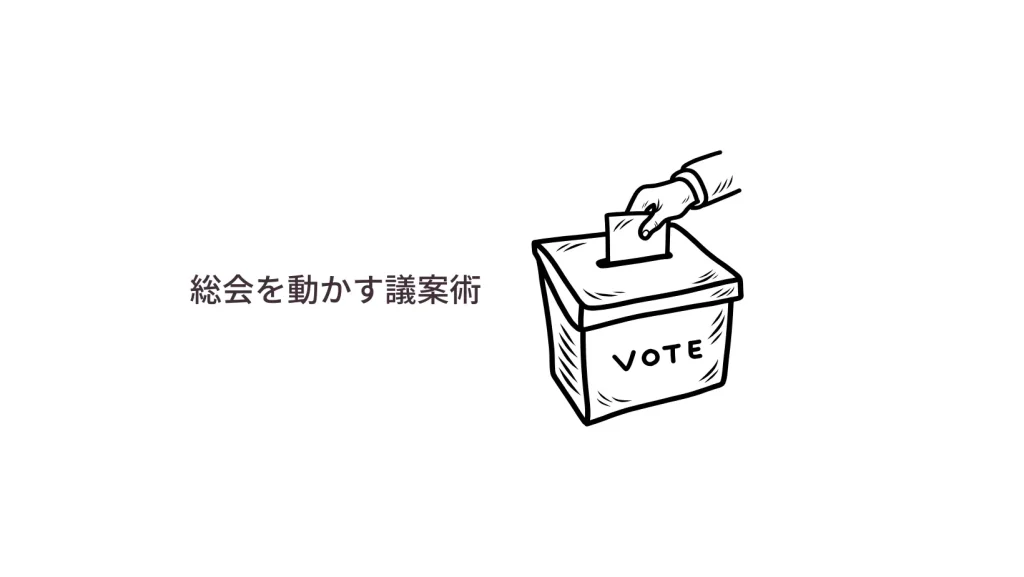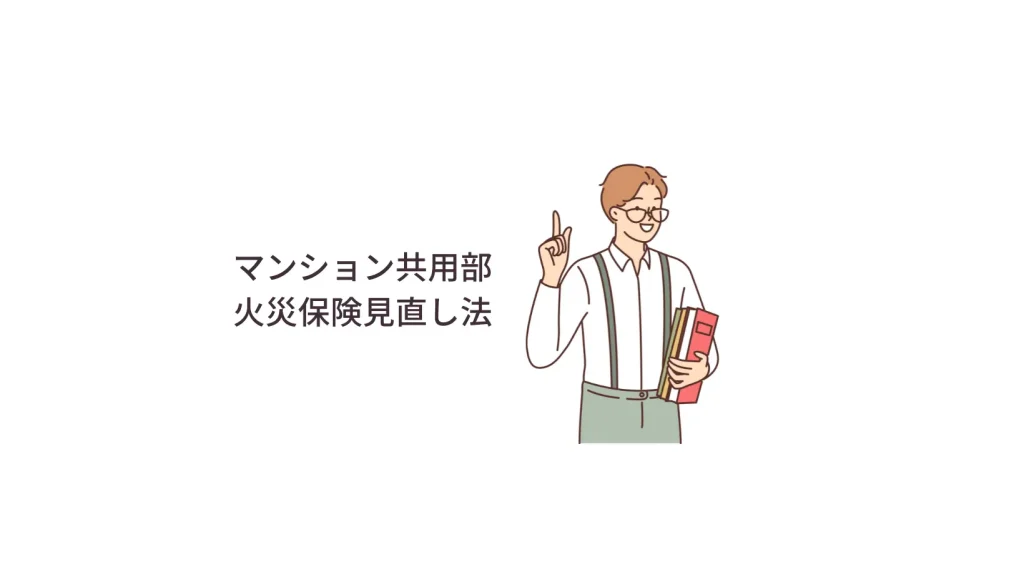こんにちは!事務所が渋谷にある、渋谷貴博です。
私は35年間マンション業界で働いてきました。またプライベートでは、マンション(埼玉県さいたま市・総戸数812戸)に住んで、修繕委員、副理事長、理事長経験があります。そんな私が管理組合役員の皆さまの役に立つ情報を発信します。
マンションの資産価値と住環境を守るうえで避けて通れないテーマの一つが「修繕積立金は将来足りるのか?」という問いです。購入当初は月々の負担額が妥当かどうかを深く考える人は少なく、むしろ「負担が軽いから助かる」と感じる方が多いかもしれません。しかし築10年、15年と時が経ち、最初の大規模修繕工事が近づいてくると、その安心感は一変します。修繕積立金の残高と大規模修繕工事の見積もり金額を比較して「まったく足りない」という現実に直面し、管理組合理事会が大きな課題を抱えることになるのです。
国土交通省の令和5年度マンション総合調査では、計画上の修繕積立金の積立額と、現在の修繕積立金の積立額の差は、現在の積立額が計画に比べて不足しているマンションが36.6%となっており、つまりこれは一部の管理組合だけの問題ではなく、日本中の分譲マンションが直面しているリスクだといえるでしょう。
令和5年度マンション総合調査結果概要
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001750093.pdf
修繕積立金不足が生じる背景
修繕積立金不足が生じる背景にはいくつもの要因が絡み合っています。まず大きいのは「分譲時の修繕積立金の設定が意図的に低すぎる」ことです。デベロッパーは販売時に月々のランニングコストが安く見える方が購入者にとって魅力的になるため、修繕積立金を低く設定する傾向があります。たとえば本来1万円程度が妥当な住戸で5,000円や7,000円に設定されているケースも珍しくありません。その結果、最初の数年間は「安くて助かる」と感じられますが、築10年を過ぎたあたりで計画と現実の乖離が顕著になります。
加えて近年は建設資材や人件費の高騰が深刻です。外壁塗装や防水材の価格は過去10年で2〜4割上昇し、人件費は技能労働者不足の影響で年々増加しています。2000年代前半に作成された長期修繕計画では「築30年時に1億円で大規模修繕を実施する」と見込んでいたものが、2020年代に長期修繕計画の見直しを実施すると「1.5億〜1.8億円必要になる」、といった事例が全国で報告されています。
さらに、計画時の想定と現実との乖離も要因です。長期修繕計画は「平均的な建物」を前提に作られることが多いため、立地条件や環境要因は十分に反映されません。海沿いのマンションでは塩害による鉄部腐食が早く、幹線道路沿いでは排ガスや振動で外壁劣化が進みやすく、山間部では凍害による影響もあります。こうした環境要因を無視して計画通りに積み立てていても、実際の修繕時期には前倒しが必要となり、資金不足に直面するのです。
また、住民合意形成の難しさも欠かせない要因です。修繕積立金の増額は総会での決議が必要ですが、現役世帯は教育費やローン返済で負担感が強く、高齢世帯は年金収入で生活しているため支出増に強く抵抗します。「今のままで何とかなるだろう」「まだ先のことだから」といった心理から増額が先送りされ、結果として積立不足が固定化していくのです。
修繕積立金不足を放置した場合のリスク
修繕積立金不足を「そのうち解決するだろう」と放置した場合、マンション全体に深刻な影響が及びます。最も直接的なのは「修繕工事の遅延や縮小」です。本来であれば築12年〜15年で行うべき外壁・防水の大規模修繕を延期すれば、外壁タイルの剥離落下や雨漏りが現実に発生します。外壁タイルの落下は通行人への事故につながり、管理組合の法的責任問題に発展する恐れもあります。
資金不足の穴埋めとして一時金徴収や借入を行う場合もありますが、これも大きな問題を生みます。一時金は1住戸あたり数十万円から100万円超を求めることが多く、特に年金生活者や単身者には大きな負担であり、支払いを拒否する住民が出ると工事そのものが進められなくなることもあります。借入に頼る場合も利息負担が加わり、返済が次回の修繕時期に重なれば「積立と返済の二重負担」という悪循環に陥ります。
さらに、マンションの資産価値下落は避けられません。中古マンション市場では、買主や金融機関がまずチェックするのが「修繕積立金残高」と「長期修繕計画の有無」です。これらが不十分な場合、「管理不全マンション」と評価され、相場よりも1〜2割低い価格でしか売却できない事例もあります。築30年を超えるマンションで、大規模修繕が実施されていない、または積立不足が顕著な場合は、売却希望者がいても買い手がつかないケースすら出てきています。
つまり、修繕積立金不足を放置することは、住民の生活環境だけでなく、マンションの資産価値という経済的基盤をも失わせるリスクをはらんでいるのです。
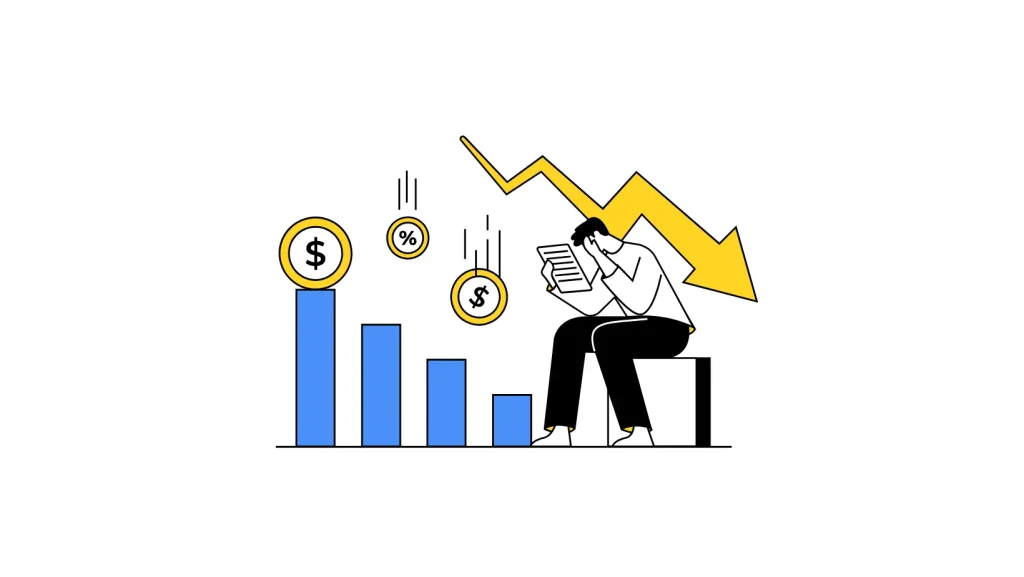
修繕積立金不足を解消するためのアプローチ
積立金不足を解消するためには、複数の対策を組み合わせて現実的に進めることが必要です。まず欠かせないのが「長期修繕計画の定期的な見直し」です。国交省の指針でも「5年ごとの見直し」が推奨されており、建物診断を実施して実際の劣化状況を反映させ、最新の工事単価や労務費を織り込みます。このとき第三者である「修繕コンサルタントを導入」すれば、工事仕様の妥当性や不要な工事項目を精査でき、コストを大幅に削減できる可能性があります。
次に重要なのが「積立金の段階的増額」です。国交省ガイドラインでは、築年数に応じて積立額を増やしていく「段階増額方式」を推奨しています。例えば築10年で1.2倍、築20年で1.5倍といったように少しずつ増額することで、住民の負担を急激に増やさずに将来の大規模修繕に備えることができます。増額は住民にとって不人気な議題ですが、早期に少額で調整することで「一時金徴収」という極端な負担を避けられるのです。
さらに「資金運用の工夫」も一つの手段です。多くの管理組合では積立金を普通預金に置いたままですが、金利のつく定期預金や公共性の高い信託商品を活用すれば、安全性を保ちながら効率的に資金を増やすことが可能です。海外では修繕基金を国債運用している事例もありますが、日本ではリスク回避の観点から慎重さが求められます。大切なのは「安全性を確保しつつ効率化を図る」という姿勢です。
また、「修繕周期の長期化」も有効です。従来の「修繕実施時期」では資金繰りが厳しくなるため、建物診断結果が良好であり、工事実施時期を先延ばしすることができれば、その年数分の積み増しが可能となります。これにより積立金が不足していても工事を進められます。12~15年周期にこだわらず、自身のマンションの劣化状況を客観的に把握することや、全体工事を一気に実施するのではなく、劣化状況に応じて工事着手することで、個々の工事別に先延ばしができる可能性も出てきます。
こうしたアプローチを複合的に取り入れることで、修繕積立金不足は「解決不可能な壁」ではなく「計画的に解決できる課題」へと変わるのです。
修繕周期を延ばして修繕積立金を有効活用する大規模修繕工事
https://mansion-anshin.com/archives/20250905/
まとめ
「修繕積立金は足りるのか?」という問いは、すべてのマンション管理組合に共通する現実的かつ切実な問題です。積立金不足の背景には分譲当初の低い設定、建設コストの高騰、計画と現実の乖離、住民合意形成の難しさといった要因があり、放置すれば修繕の遅延、一時金徴収、借入、マンションの資産価値下落といった深刻な結果につながります。
しかし定期的な長期修繕計画の見直し、段階的な積立増額、資金運用の工夫、修繕周期の長期化などを組み合わせれば、不足を計画的に解消することは十分可能です。修繕積立金は単なる数字ではなく、住まいの未来を守るための命綱であり投資です。管理組合と住民が現実を共有し、早めに行動を起こすことこそが、安心・安全で資産価値の高いマンションを次世代に引き継ぐ唯一の道といえるでしょう。
さらに万全の工事実施とするために、施工業者が加入する「履行保証保険」「瑕疵保険」がおすすめです。工事中の倒産や工事後の瑕疵・不具合に備える保険制度です。詳しくは以下のURLをご覧ください。
マンション修繕の保証制度 ※「履行保証保険」「瑕疵保険」について
https://mansion-anshin.com/system/