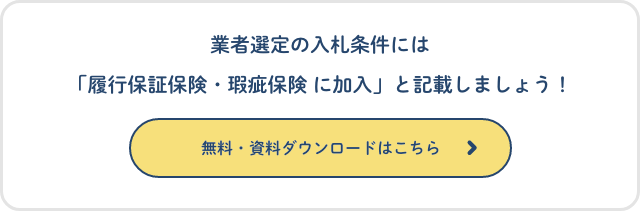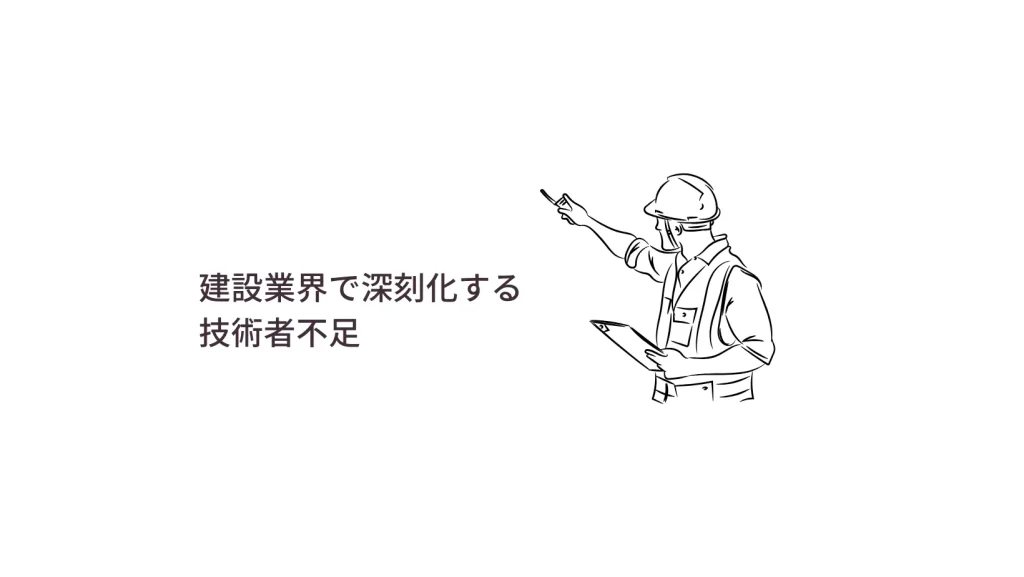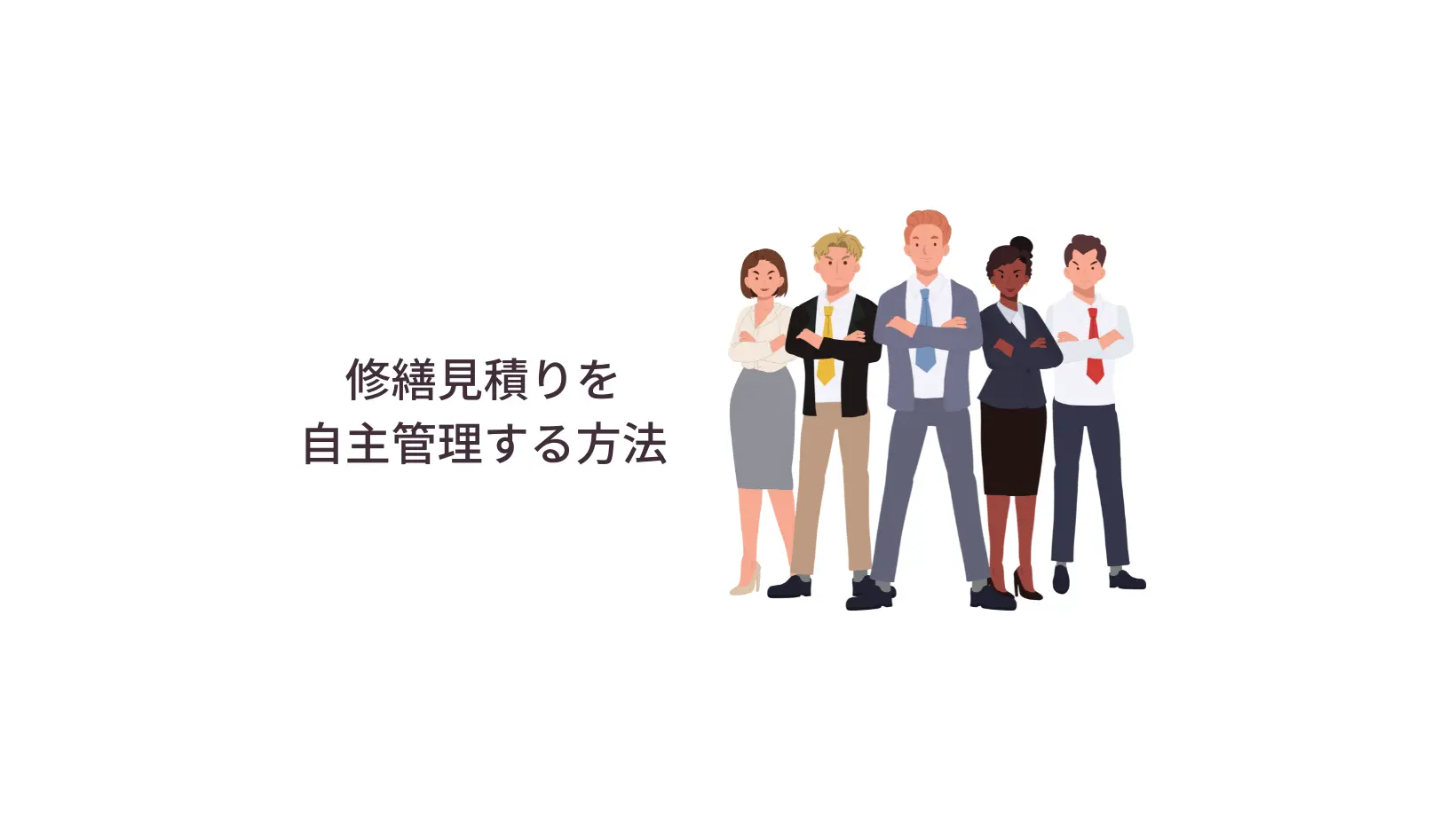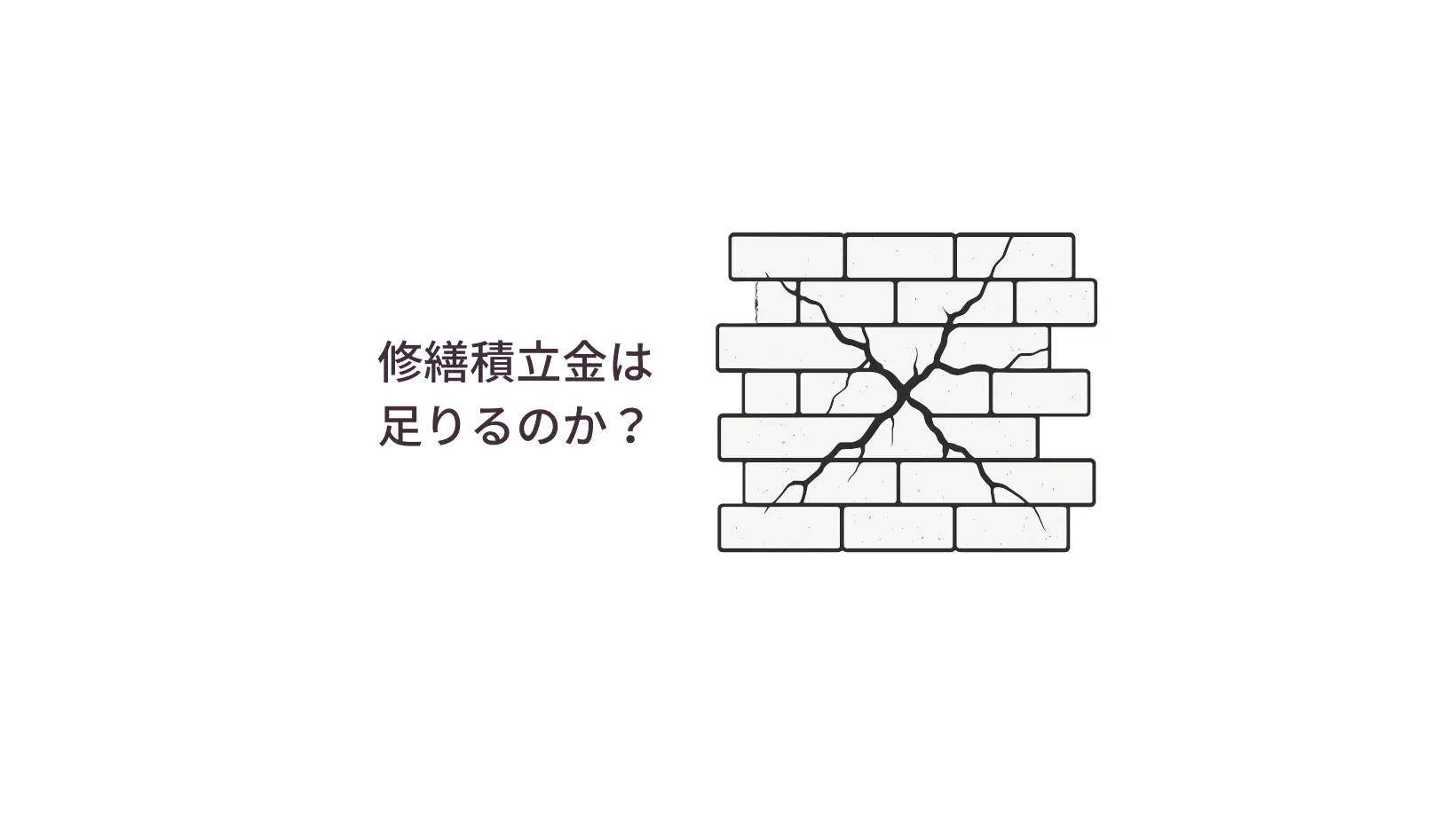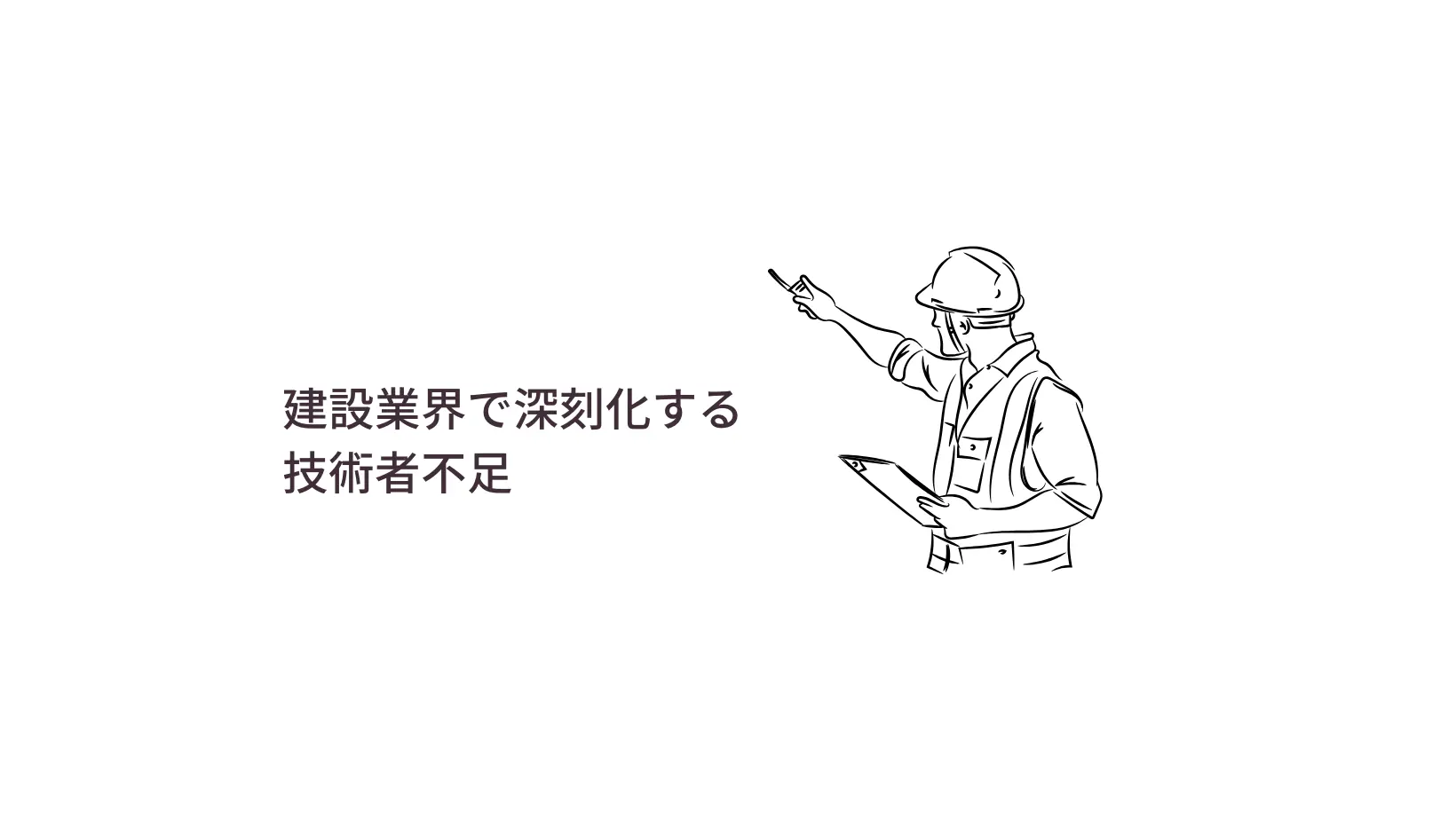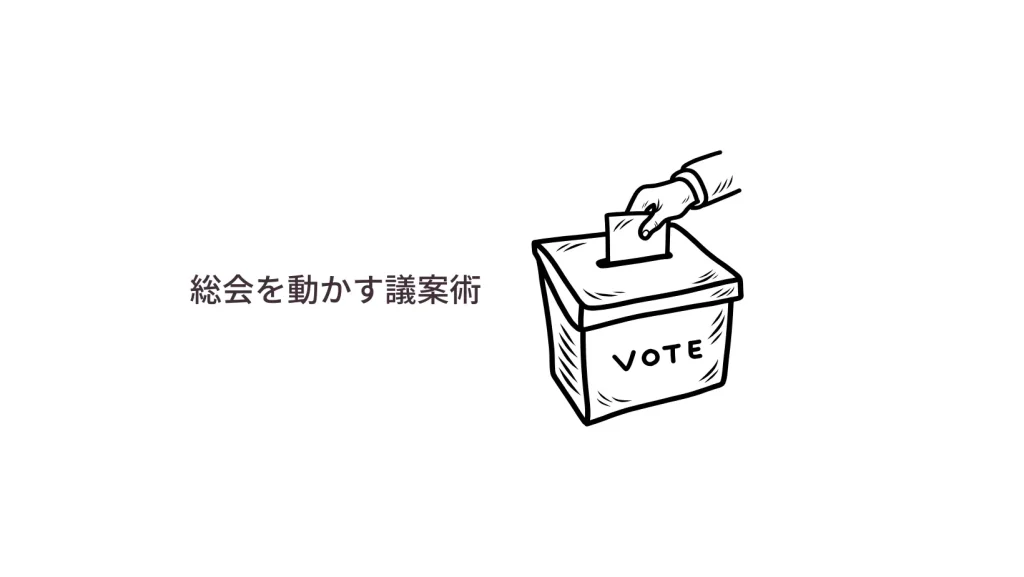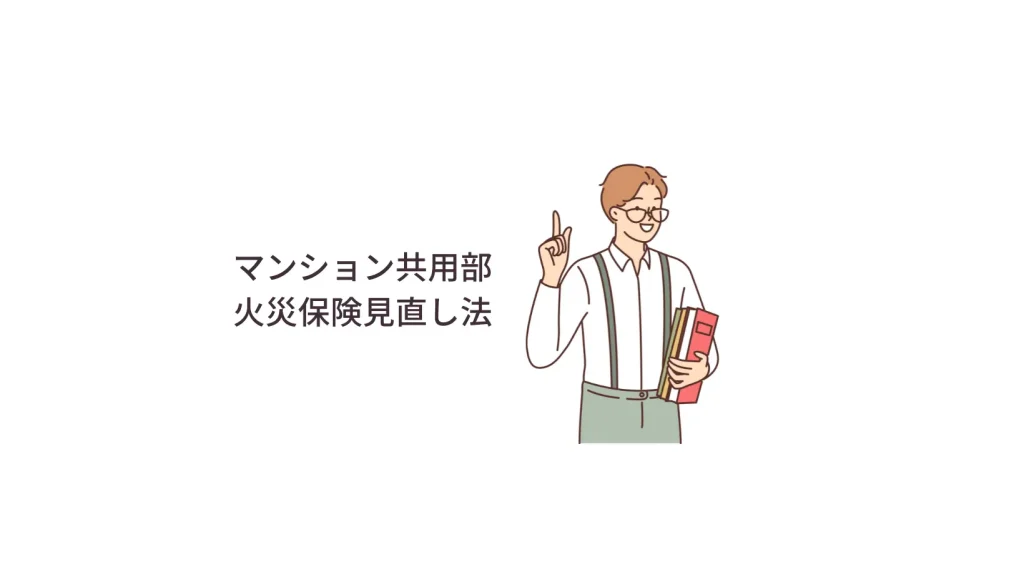こんにちは!事務所が渋谷にある、渋谷貴博です。
私は35年間マンション業界で働いてきました。またプライベートでは、マンション(埼玉県さいたま市・総戸数812戸)に住んで、修繕委員、副理事長、理事長経験があります。そんな私が管理組合役員の皆さまの役に立つ情報を発信します。
倒産件数の増加と工事中断リスクの拡大
建設業界全体を見渡すと、今ほど不安定な時代はありません。帝国データバンクの調査によれば、2024年に建設業で発生した倒産件数は1890件に上り、過去10年間で最も多い数字を記録しました。この事実は、大規模修繕工事を発注するマンションの管理組合や理事会にとって重大な警鐘です。なぜなら、発注した工事が途中で止まってしまうリスクが現実のものになっているからです。
倒産が相次ぐ背景には、資材価格や人件費の高騰といった外的要因があります。たとえば、外壁修繕で必須となる足場材や防水シートはここ数年で数割値上がりしており、さらに鉄鋼製品や塗料類も円安や国際市況の影響を受けて価格上昇が続いています。
一方で、発注者である管理組合は「相見積もり」で価格を比較するため、業者は価格転嫁を十分に行えず、利益率がどんどん削られていきます。さらに深刻なのは人材不足による人件費の高騰です。職人不足の影響で一人当たりの人工単価は上がり続け、従来の工事費水準では採算が取れなくなりつつあります。
こうした状況に追い込まれた施工会社は、利益確保のために質を落とすか、あるいは事業継続を断念するかという二択を迫られます。その結果が倒産件数の増加に表れています。大規模修繕工事の現場で実際に起こり得るのは、工事が半分まで進んだところで業者が資金ショートし、現場から撤退するという事態です。追加の業者を探す必要が生じ、足場の再架設や再契約の事務手続きに余計なコストと時間がかかり、住民にさらなる負担を与えます。
では、発注者ができる備えは何でしょうか。第一に、施工会社の財務状況を調べることです。経営状況審査に合格した業者や、履行保証保険を取り扱える施工会社を優先的に候補に挙げるべきです。第二に、契約書の支払い条件を工夫することです。前払い金や一括払いは避け、必ず「出来高払い方式」を導入し、工事進捗に応じて支払う仕組みを整えます。第三に、履行保証保険や完成保証制度を導入することで、万一倒産しても後継業者による工事続行が可能となります。
これらの対策は理事会にとって手間に見えるかもしれませんが、万一の損失を考えれば極めて合理的な投資です。
【帝国データバンク】人手不足倒産の動向調査(2024年) https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250109-laborshortage-br2024/
技術者の高齢化とノウハウ喪失の深刻化
次に挙げるべきリスクは、建設業界全体を覆う「2025年問題」に直結する技術者の高齢化です。日本社会全体で5人に1人が後期高齢者となる中、建設現場を支えてきたベテラン技術者の引退が現実の課題となっています。ある調査では、81%の技術者が「ベテランのノウハウは失われる」と危惧しており、その中でも44.5%は「今後5年以内に喪失が進む」と答えています。
大規模修繕工事は、教科書通りの知識だけでは対応できません。外壁タイルの浮きや漏水の原因特定などは、現場経験の積み重ねが不可欠です。たとえば、同じひび割れでも「下地モルタルの収縮によるものか、構造的な欠陥によるものか」を見極める判断は、経験豊富な技術者でなければ難しいのです。さらに、工事現場では住民対応や近隣調整といった対人スキルも必要であり、これも経験から身につくものです。
しかし、技術継承の現状は心もとないものです。半数以上が「不十分」と感じており、指導方法も口頭指導や現場での打ち合わせが中心で、記録やマニュアルとして残されることはほとんどありません。つまり、技術者が現場を去れば、その知識も一緒に消えてしまうのです。このままでは、大規模修繕工事の品質を担保する力が業界全体で急速に失われてしまいます。
発注者の立場からできる対策は、業者選びの際に「どの人材が現場を担当するか」を確認することです。会社の規模やブランドだけではなく、現場代理人や監理技術者の経歴・実績を具体的にチェックすべきです。また、設計監理方式を採用し、第三者コンサルタントに監理を依頼することで、経験豊富な外部の目を常に現場に入れることが可能になります。さらに、DXの活用も重要です。工事写真や検査記録をクラウドで管理し、共有することで、ノウハウが蓄積され、世代交代による断絶を緩和できます。
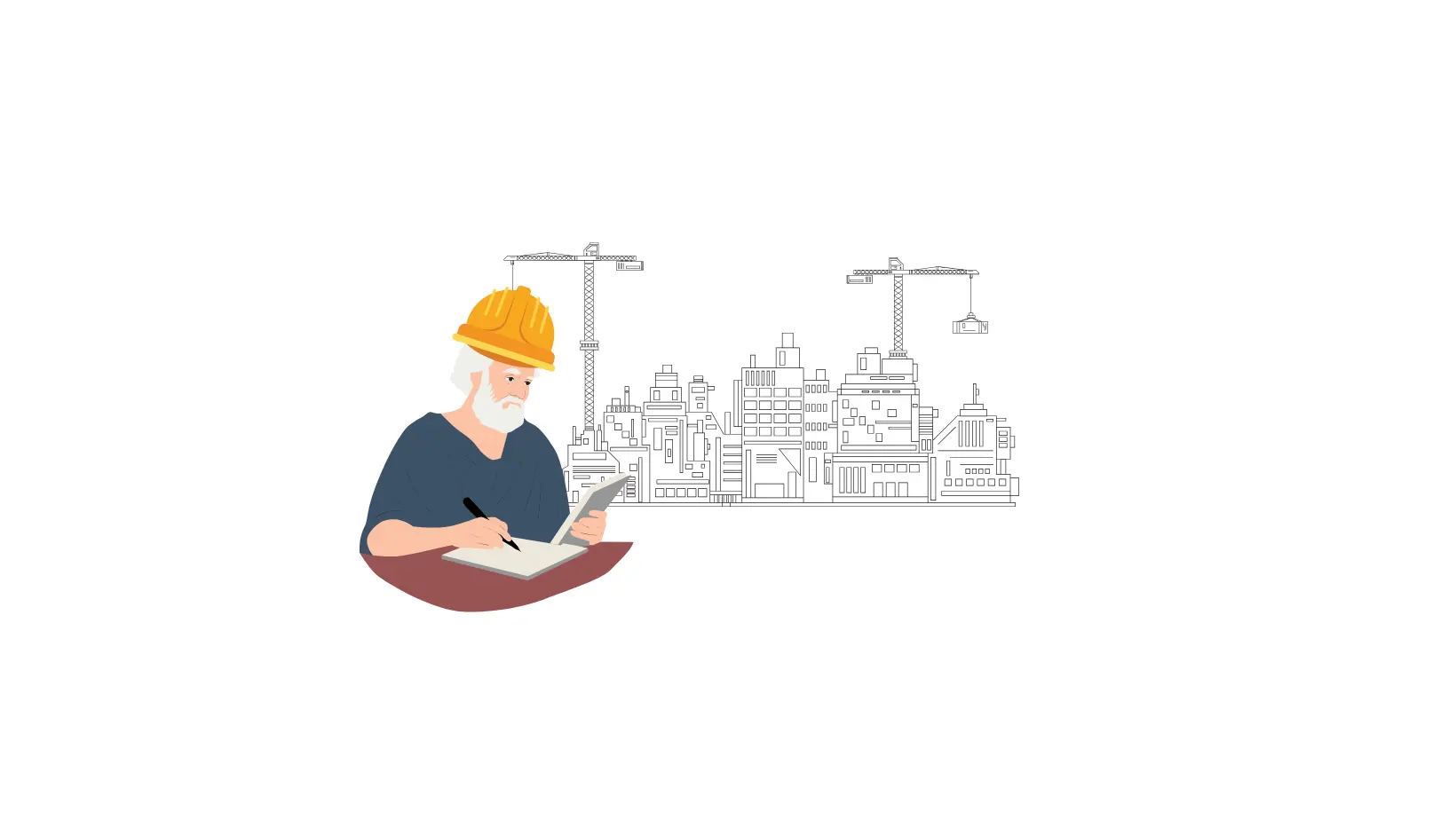
人材不足と品質確保の難しさ
建設業界では人材不足が慢性化しており、それが大規模修繕工事にも深刻な影響を与えています。若者の入職が減少する一方で、既存の人材に業務が集中し、過労や安全意識の低下につながっています。事故リスクの増加や、工期を守るための突貫工事による品質低下は、居住者にとって大きな不安材料です。
さらに、ノウハウ伝承がアナログに依存していることも品質低下を助長しています。経験の浅い職人が重要な作業を任され、監督が不十分なまま進むことで、施工不良や不具合が後々発覚するケースも増えています。実際に「外壁の補修が数年で再劣化した」「防水工事を行ったのに再び漏水した」といった事例は全国で報告されています。
発注者ができる対策は、下請業者まで含めた労務体制の確認です。単に元請業者の信用度だけで判断するのではなく、どの職人が実際に作業するのか、下請・孫請がどのように管理されているかを確認することが重要です。また、理事会や修繕委員会のメンバーが定期的に現場を見学することで、施工の透明性を高められます。加えて、第三者コンサルタントや建築士から定期報告を受ける仕組みを作れば、理事会は専門的な知見を得ながら工事の進行を把握できます。
さらに、発注者自身が学び続けることも欠かせません。大規模修繕工事の契約形態や保証制度、最新の施工技術について知識を得ておくことで、業者に依存しすぎることなく、主体的に判断を下せるようになります。この姿勢こそが、品質を守る最強の武器になります。
まとめ|発注者の知識と主体性が未来を左右する
大規模修繕工事を取り巻く環境は、倒産件数の増加、技術者の高齢化によるノウハウ喪失、そして慢性的な人材不足という三つのリスクが同時進行しています。これらの課題は業界全体の構造的問題であり、発注者が「任せきり」にしてしまえば必ず住民の不利益につながります。工事中断や品質低下、追加負担といったトラブルは、今後ますます増える可能性が高いのです。
しかし、発注者には選択肢があります。業者の財務状況を見極め、契約条件を工夫し、保証制度を導入し、監理体制を強化する。さらにはDXの導入を後押しし、ノウハウの蓄積を促進する。こうした主体的な行動こそが、リスクを未然に防ぎ、安全で高品質な大規模修繕工事を実現する鍵となります。
結論として言えるのは、これからの大規模修繕工事は「業者任せの時代」ではなく、「発注者が知識を武器に自ら守る時代」へと移行しているということです。理事会や管理組合が主体性を持って準備し、判断し、監督する。その積み重ねこそが建物の資産価値を守り、居住者全員の安心につながるのです。
また、万全の工事とするためには、最低限のリスク対策が必要です。施工業者の倒産、工事後の瑕疵・不具合の発生の対策です。そのためには、施工業者が加入する「履行保証保険」「瑕疵保険」を活用することをお薦めします。施工業者選定の入札条件には「履行保証保険、瑕疵保険に加入すること」としっかり記入して、リスク対策の保険への加入リクエストをしましょう。
「履行保証保険」「瑕疵保険」に関する説明はコチラ ↓ ↓ ↓ https://mansion-anshin.com/system