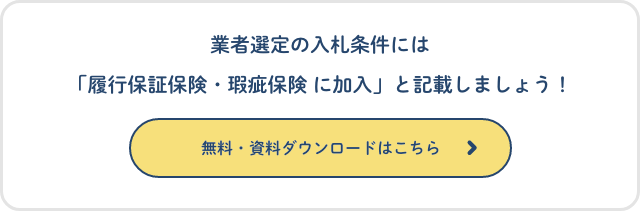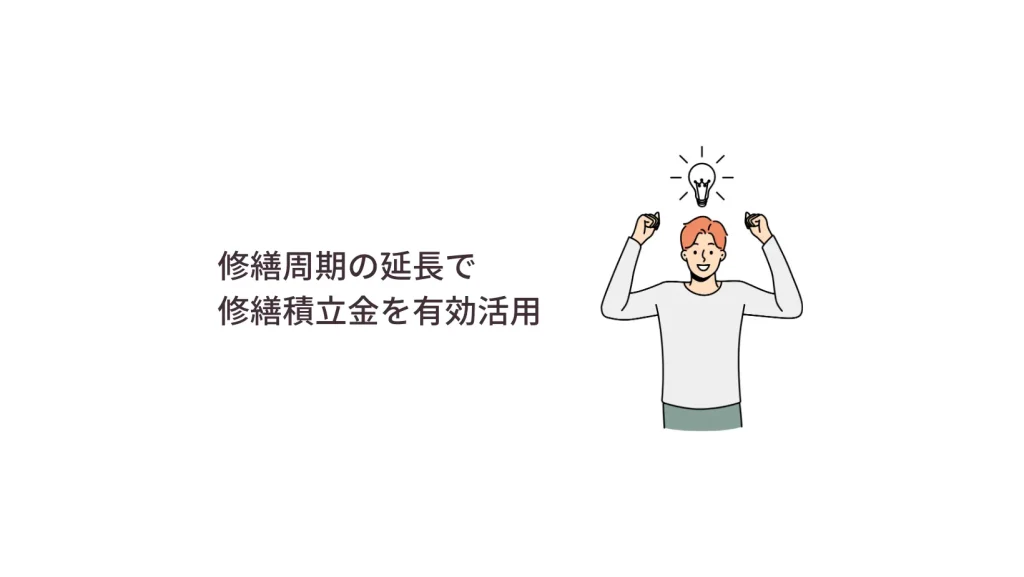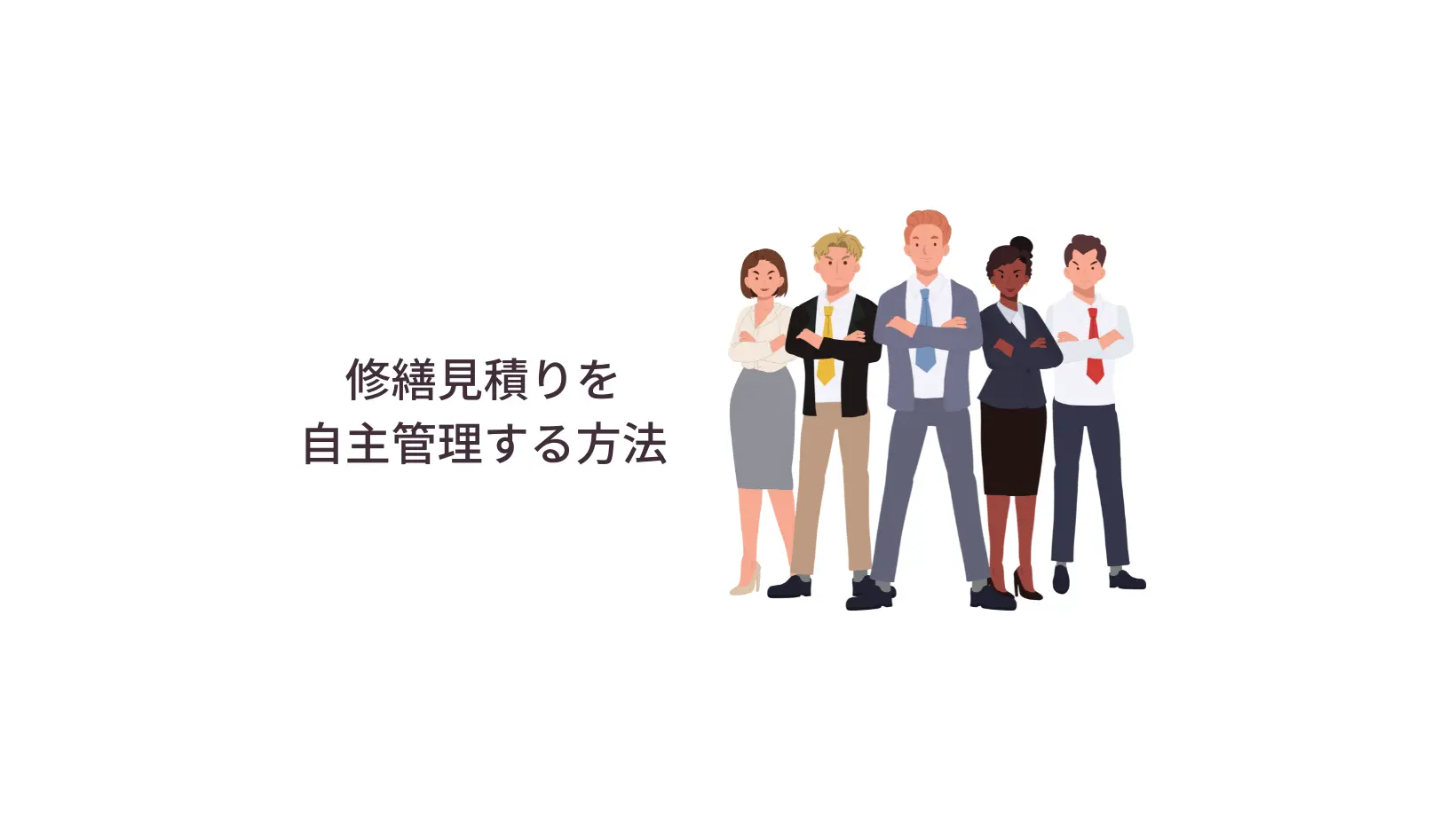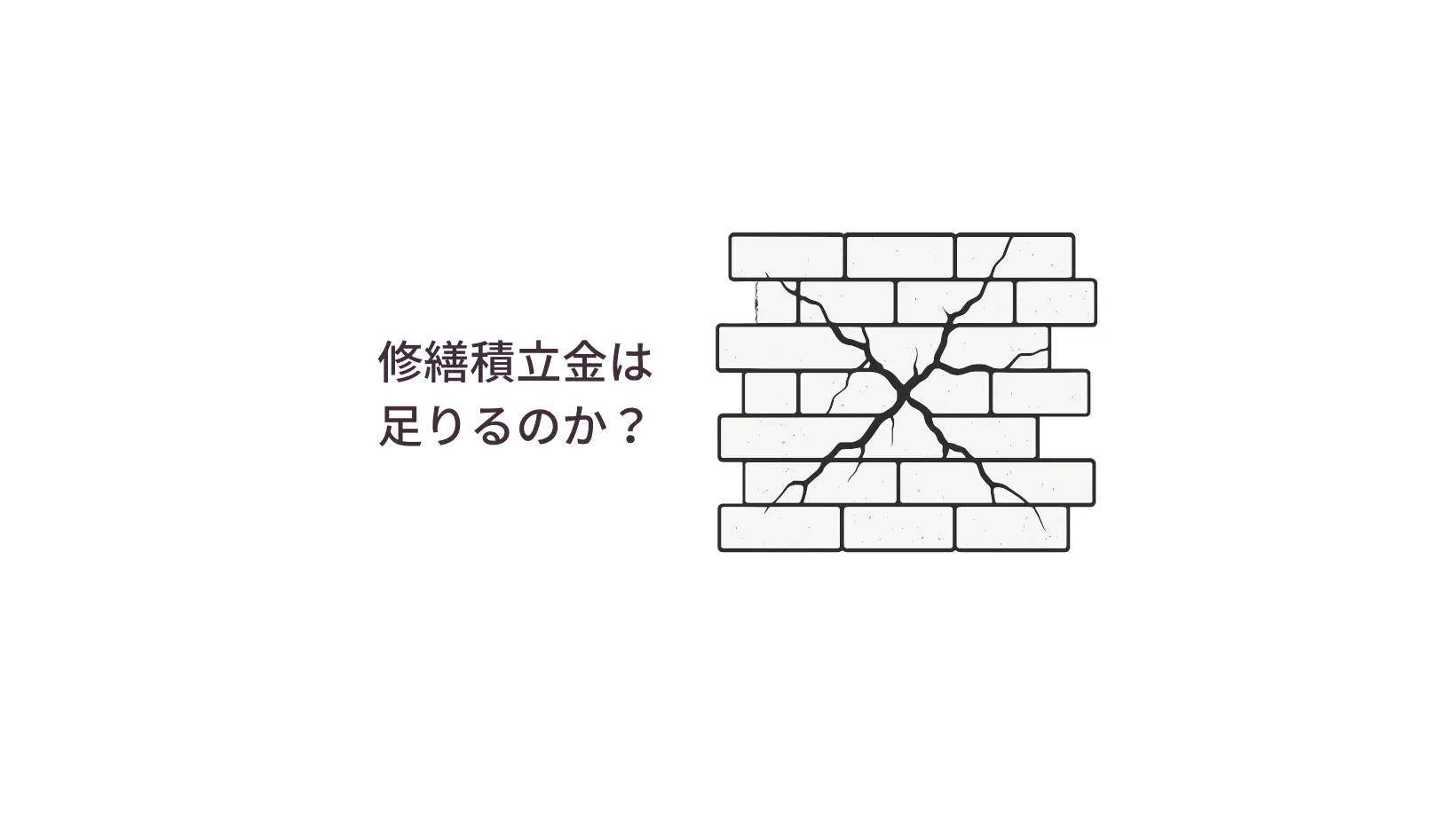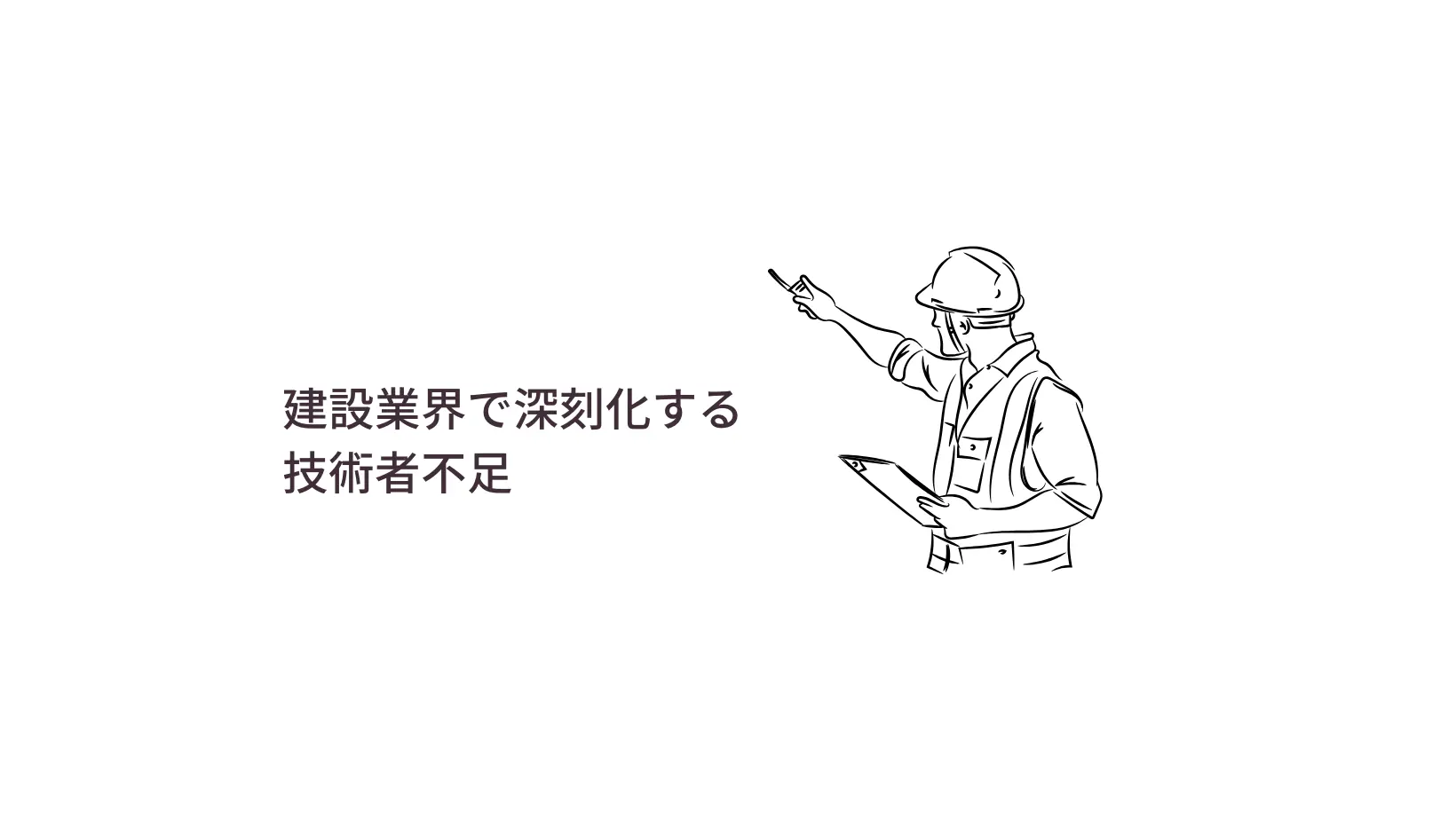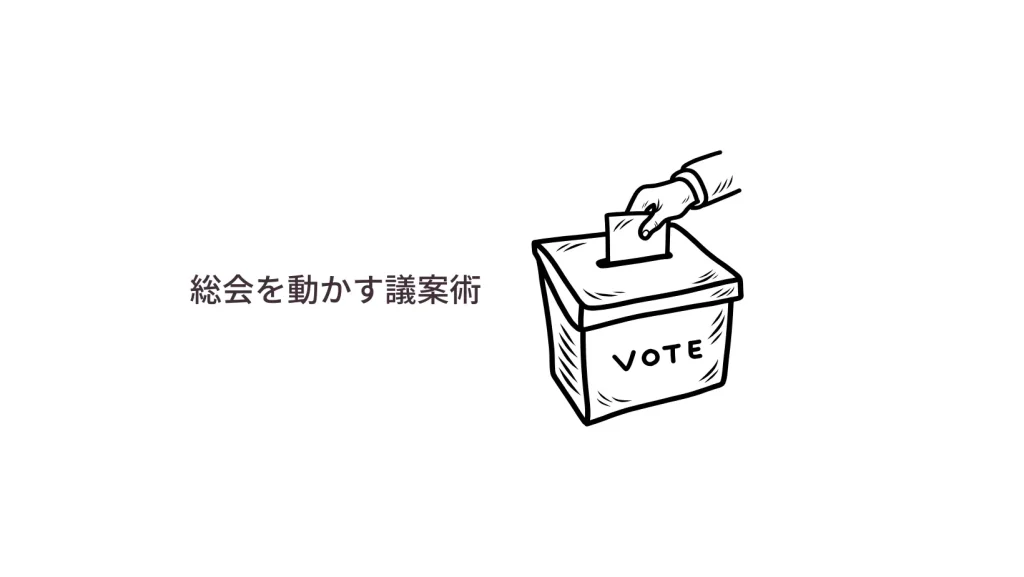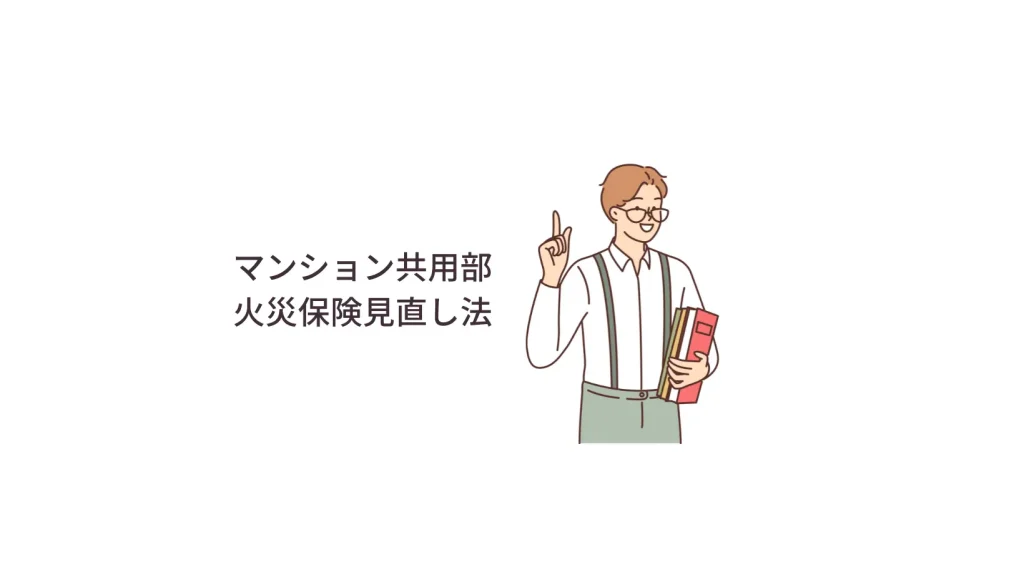こんにちは!事務所が渋谷にある、渋谷貴博です。
私は35年間マンション業界で働いてきました。またプライベートでは、マンション(埼玉県さいたま市・総戸数812戸)に住んで、修繕委員、副理事長、理事長経験があります。そんな私が管理組合役員の皆さまの役に立つ情報を発信します。
修繕周期の考え方と管理組合が直面する課題
マンションの大規模修繕工事は、建物の資産価値を維持し、安全で快適な住環境を守るために避けては通れない重要な事業です。国土交通省のガイドラインでは12年から15年を目安とした修繕周期が示されており、多くの管理組合もこの基準を参考に長期修繕計画を策定しています。外壁の塗装や屋上防水、鉄部の塗装、給排水設備の更新、共用廊下や階段の補修など、対象となる工事項目は広範囲に及び、その工事費用は数千万円から数億円にのぼることも少なくありません。
国土交通省のガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425184.pdf?utm_source=chatgpt.com
しかし、この「12年から15年」という一律的な周期設定が必ずしもすべてのマンションに適しているとは限りません。立地条件や施工当時の工事品質、日常の管理状態、さらには材料や仕上げのグレードによって、建物の劣化速度は大きく異なります。海沿いの塩害を受けやすい立地と内陸の乾燥地帯では、劣化進行のスピードはまったく違いますし、同じ築年数であっても管理が行き届いたマンションとそうではないマンションとでは、外観や設備の健全度に大きな差が見られます。
さらに昨今は、建設資材価格の高騰や職人不足による人件費の上昇など、社会的な要因が工事費用を押し上げています。長期修繕計画を策定した当時の想定金額と、実際に工事を発注する際に提示される見積額が大きく乖離するケースも増えています。その結果、修繕積立金が不足して金融機関からの借入を検討せざるを得なかったり、管理組合が区分所有者に一時金の徴収を求めざるを得なくなるなど、住民にとって大きな経済的負担が発生する事態も多いのです。
このような状況において、管理組合にとって有効な選択肢となるのが「修繕周期の延長」です。周期を延ばすという考え方は単に工事を先送りするという意味ではなく、建物の実際の劣化状態を精査したうえで、必要に応じて修繕を柔軟に行いながら、全体的な大規模修繕工事の間隔を合理的に伸ばすことを意味します。周期を延ばすことで、修繕積立金を効率的に蓄える時間的余裕が生まれ、資金計画をより健全で持続可能なものにすることができます。
ただし、周期を延ばすことには当然ながら条件があります。劣化の進行が深刻であれば延長はできませんし、材料の選定や小規模修繕の積み重ね、適切な建物診断の実施といった前提条件を満たさなければなりません。それでも、多くのマンションで修繕周期の延長が現実的な選択肢となりつつあり、この戦略的な判断が修繕積立金の有効活用という大きなメリットにつながっていくのです。
修繕周期を延ばすことで得られる資金活用のメリット
修繕周期を延ばすことによる最大のメリットは、修繕積立金を効率的に使えるという点にあります。12年で工事を行う場合と18年で行う場合とでは、同じ金額を積み立てていても準備できる資金に大きな差が生じます。周期を6年間延ばせば、その間に追加で積み立てが可能となり、資金不足で借入や一時金徴収に頼るリスクを回避できます。これは、管理組合にとっても住民にとっても大きな安心材料となるでしょう。
また、修繕周期を延ばすことで、長期修繕計画の資金収支全体に余裕が生まれます。資金繰りに余裕があれば、突発的な設備更新や災害復旧への対応も容易になりますし、次回以降の工事計画にも柔軟性が生まれます。たとえば、給排水管の劣化が進んだ場合に臨時に更新工事を行うといった判断も、資金に余裕があればスムーズに実行できるのです。
一方、周期延長を可能にするためには、工事の質そのものを高めることが前提となる、として外壁塗装において高耐久塗料を使用したり、防水層の工法に長寿命型の材料を採用することで、修繕サイクルを確実に延ばすことができるとPRする施工業者が昨今増えています。「初期費用は割高であっても、長い目で見れば工事回数を減らせるため、結果的にトータルコストは下がります。」という謳い文句でPRをします。
当センター調べでは、一般的な防水層の材料の耐用年数は20年以上あります。高い初期費用を負担して高耐久塗料や長寿命型の材料を使用する必要はないのです。一般的な防水層の工事を適切に実施すること、またその後に保護塗装を施工することで15年~18年は耐えられるものと考えています。こうすることによって、初期費用も低廉化させ、また修繕周期も長期化して、修繕積立金をより効率的に活用することが可能になるのです。
また、周期を延ばすことで住民の心理的・経済的な負担も軽減されます。12年ごとに1億円規模の工事が行われると、住民は生涯の間に複数回の大規模修繕に直面する可能性があります。しかし18年ごとであれば、同じ世代の居住者が経験する工事の回数を減らすことができ、負担感は確実に小さくなります。これは長期的な居住満足度にも寄与する重要な要素です。
実際に、周期を延ばすことで資金の有効活用に成功した管理組合の事例は少なくありません。ある築15年のマンションでは、当初12年目で大規模修繕を予定していましたが、専門家による診断の結果、外壁や防水の劣化が軽度であったため、工事を18年目に実施することを決断しました。その結果、6年間の追加積立が可能となり、工事費用を一時金徴収なしで賄うことができただけでなく、余剰資金を将来の設備更新工事に回す余裕まで生まれました。

周期延長を実現するための条件と工夫
修繕周期を延ばすことは決して「工事を先延ばしにして負担を軽くする」という安易な発想ではありません。むしろ、より高いレベルでの管理や計画が求められます。そのための条件や工夫にはいくつかの重要なポイントがあります。
まず大切なのは、定期的な建物診断です。周期を延ばすためには、劣化の進行状況を正しく把握し、緊急性の低い部分については修繕を後回しにする判断が必要となります。外壁のひび割れや鉄部の錆の状況、防水層の劣化度合いなどを継続的にチェックすることで、大規模修繕工事の最適なタイミングを見極めることが可能になります。
次に、長寿命化を可能にする高品質の施工技術です。設計監理方式を採用すること、一定の施工技術力のある施工業者を選定すること、そして施工後に保護塗装やメンテナンスなどを適切に実施する実行性、これらを積極的に採用することが、修繕周期を伸ばすことになるのです。
また、小規模修繕の積み重ねも重要です。周期を延ばすという方針をとる場合でも、放置してはいけない劣化部分は必ず出てきます。バルコニーの部分的な防水補修や鉄部の再塗装など、小規模な修繕を適切に行うことで、大規模修繕全体の先送りが可能になるのです。これらは一見コストがかかるように見えますが、長期的には建物全体の健全性を維持し、トータルコストの削減につながります。
決して忘れてはならないのが、信頼できる専門家の存在です。周期延長は建物の寿命を賭けた戦略的判断であり、専門家の診断や助言なくして実現することは困難です。特に経済的な裏付けのある施工業者や、修繕積立金の資金計画に精通したコンサルタントのサポートは不可欠です。適切なパートナーを選定することで、周期延長は初めて現実的な選択肢となるのです。
まとめ|柔軟で戦略的な修繕計画こそが資産価値を守る
大規模修繕工事の周期を一律に「12年ごと」と決めてしまうのは、現代のマンション事情には適していません。むしろ、建物の個別事情に合わせて柔軟に周期を延ばすことこそが、修繕積立金を有効に使い、住民の負担を軽減し、資産価値を守るための最善の戦略です。
修繕周期を延ばすという選択肢は、決して怠慢ではなく、建物の状態を正しく診断し、高品質な工事と小規模修繕を組み合わせ、専門家と連携して戦略的に実行するものです。周期延長によって資金的な余裕が生まれれば、将来の不測の事態にも柔軟に対応でき、住民の安心感も高まります。
これからの管理組合に求められるのは、定型的なマニュアルに従うことではなく、自分たちのマンションの現実を見極めた柔軟で賢明な判断です。その判断が、長期的な資金計画の安定化、住民の負担軽減、そして建物の資産価値の維持につながっていくのです。
また、そもそも大規模修繕工事を万全に実施することは最低限の条件となります。そのためには、工事中の倒産対策や、工事後の瑕疵・倒産対策として、施工業者には履行保証保険、瑕疵保険に加入してもらうことが望ましいです。詳しくは以下URLで内容をご確認ください。
履行保証保険、瑕疵保険の概要
https://mansion-anshin.com/system/