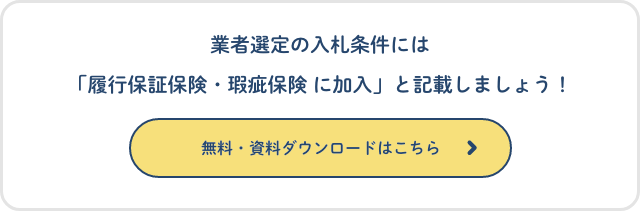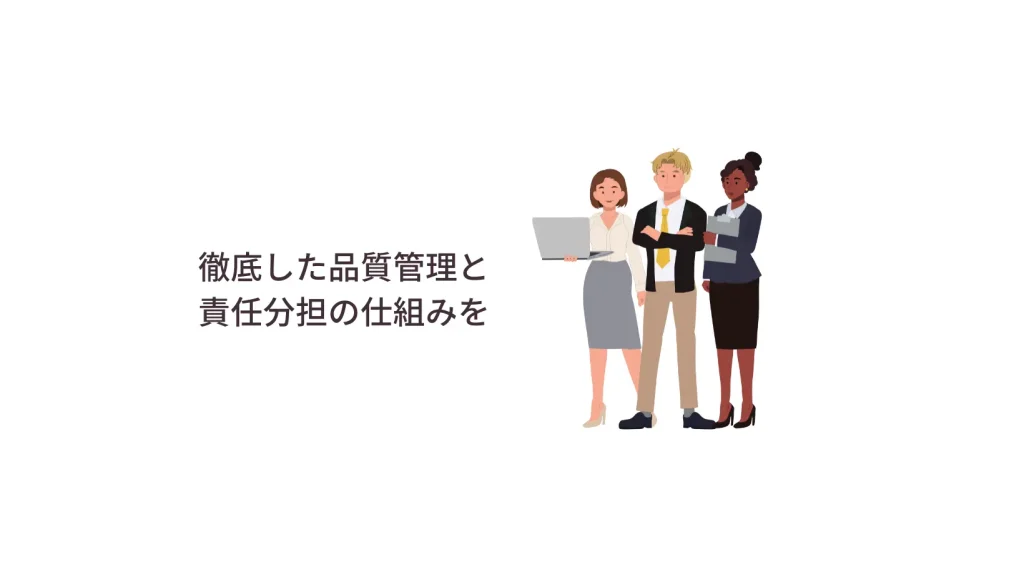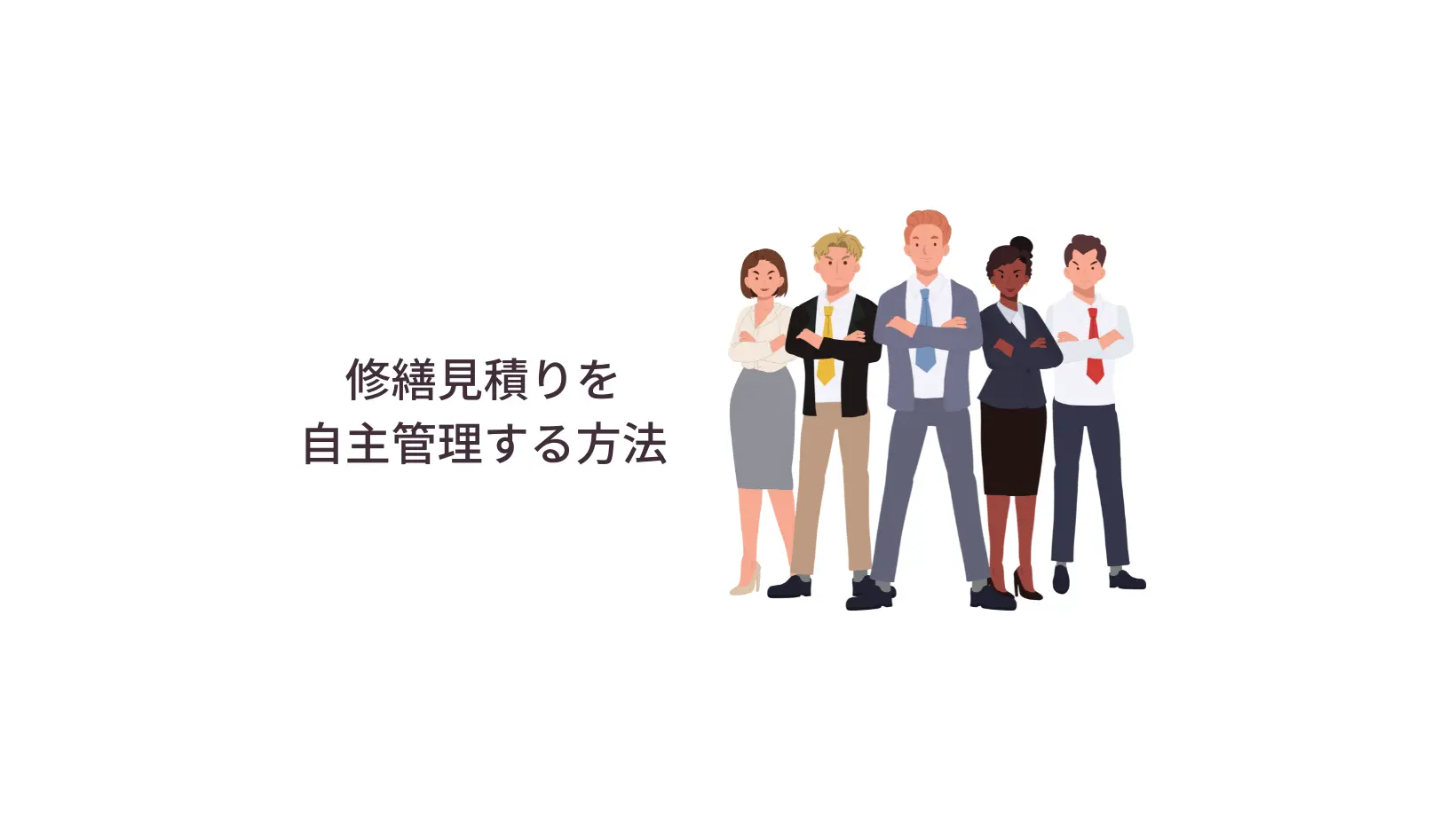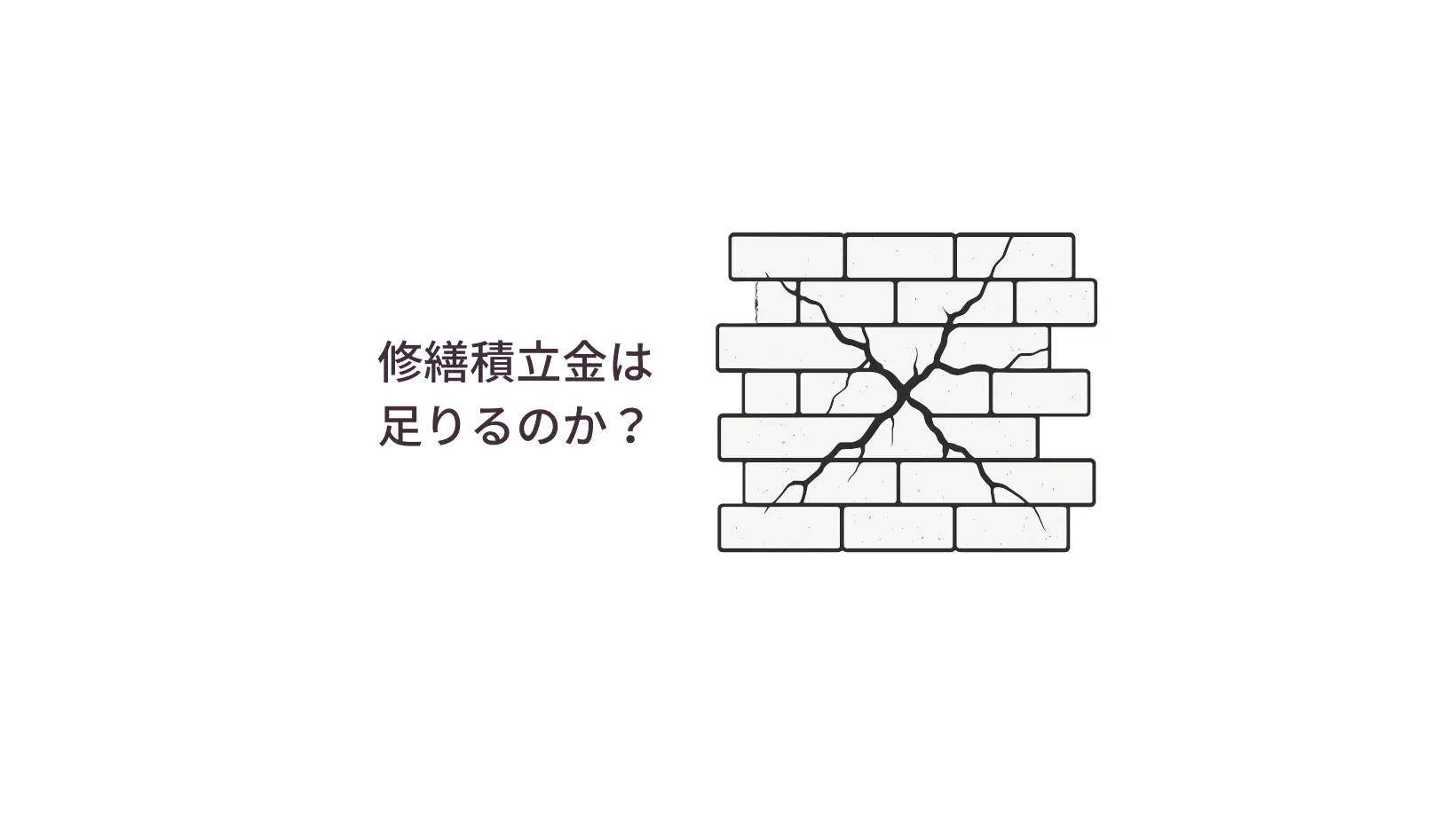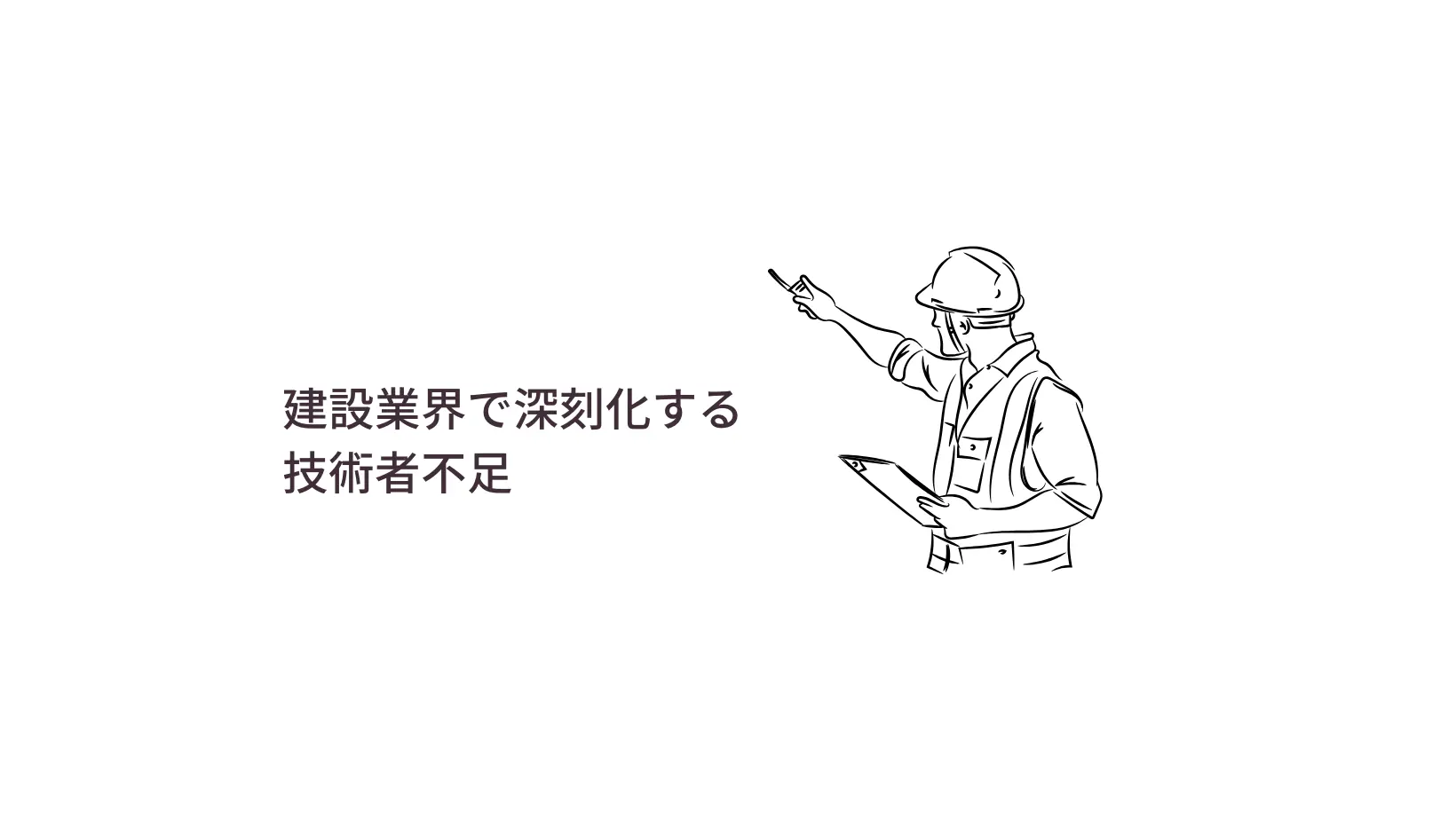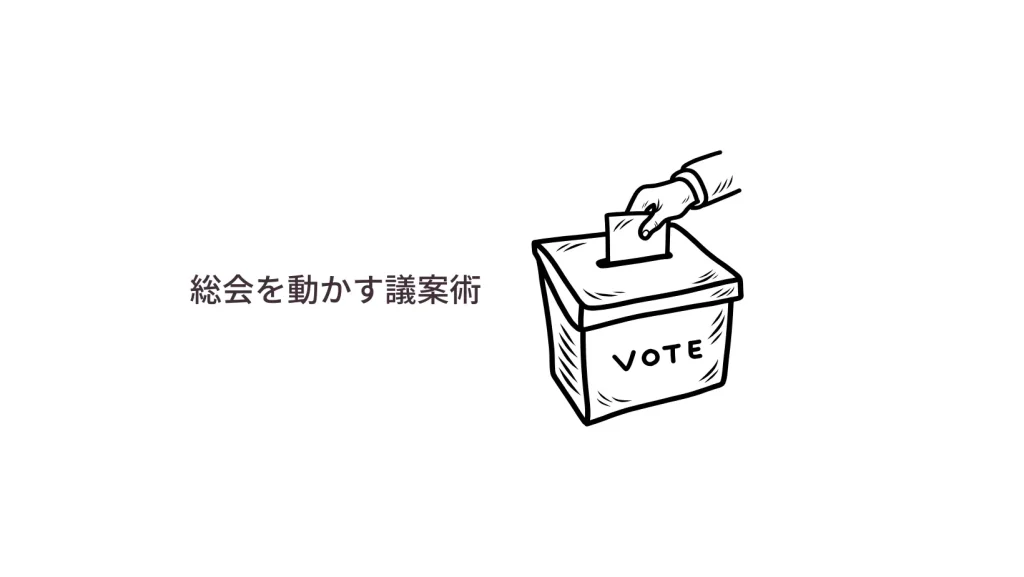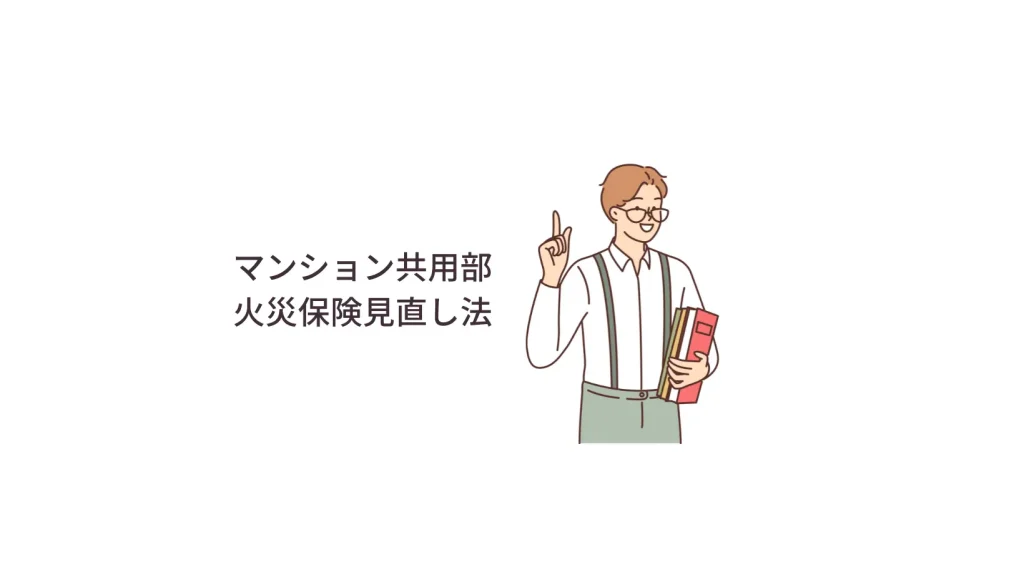こんにちは!事務所が渋谷にある、渋谷貴博です。
私は35年間マンション業界で働いてきました。またプライベートでは、マンション(埼玉県さいたま市・総戸数812戸)に住んで、修繕委員、副理事長、理事長経験があります。そんな私が管理組合役員の皆さまの役に立つ情報を発信します。
マンションの大規模修繕工事は、建物の資産価値を維持し、安全で快適な暮らしを将来にわたって守るために不可欠な取り組みです。しかし、その重要性とは裏腹に、施工不良や瑕疵、さらには手抜き工事による深刻なトラブルが後を絶ちません。数千万円から数億円単位の費用がかかる大規模修繕工事において、施工ミスや瑕疵(かし)、品質不良が発生すれば、住民にとって大きな負担となり、管理組合の信頼も損なわれてしまいます。
こうしたリスクを未然に防ぐためには、計画段階から工事終了後に至るまで、徹底した品質管理と責任分担の仕組みを整備することが求められます。
設計監理方式の導入で施工不良と手抜きを防ぐ
大規模修繕工事において施工品質を確保するうえで、もっとも有効とされるのが「設計監理方式」の採用です。これは、工事の設計と監理を第三者である専門設計事務所が担い、施工業者とは分離して契約を行う方式です。つまり、設計・監理を行う設計者と、実際に工事を行う施工業者の利害関係を切り離すことで、中立的かつ客観的な立場から品質をチェックできる仕組みです。
従来の「責任施工方式」では、施工会社が設計から工事、管理までを一括で行うことが多く、品質管理が自己完結的になりがちです。その結果、発注者である管理組合は、施工内容の適否を正確に把握できず、手抜きや仕様違反があっても気づかないまま工事が進んでしまう恐れがあります。一方、設計監理方式では、設計者が工事中に現場を定期的に確認し、設計通りに工事が進んでいるか、材料の選定や下地処理が適切か、必要な検査が実施されているかなどを詳細に監理するため、施工不良や瑕疵のリスクが大幅に低減されます。
特に外壁補修や防水工事といった、見えなくなる部分の作業にこそ設計監理の効果が発揮されます。たとえば、防水層の厚みやコンクリートの中性化処理、鉄筋の被り厚さなどは、見た目では判断がつかず、第三者の専門家による記録・検査・写真保存が欠かせません。また、設計監理者は住民説明会にも立ち会い、工事の内容や進捗について丁寧に説明する役割も担います。これにより、理事会や修繕委員会が専門知識を持たなくても、住民に対して透明性のある情報発信ができ、合意形成も円滑に進みます。
設計監理方式のもう一つの利点は、施工業者の選定プロセスにおいて「相見積もり」が可能になることです。設計図に基づいて複数の施工業者から見積もりを取り、公平な比較を行うことで、価格の妥当性を確保し、談合や不透明な価格調整のリスクを防げます。つまり、設計監理方式は「品質」と「価格の妥当性」の両方を担保する、最も合理的な発注方法といえるのです。しかし、昨今では施工業者の談合問題に悪質な設計コンサルタントが関与しているとも言われています。そこで、設計監理方式を採用する際には、設計事務所の選定には十分な注意をはらいましょう。

瑕疵保険と履行保証で万一の事態に備える
施工不良や瑕疵を完全にゼロにすることは不可能です。だからこそ、万一の事態に備えて「瑕疵保険」や「履行(りこう)保証保険」を活用することが、管理組合にとって極めて重要なリスクヘッジ手段となります。
まず、瑕疵保険とは、工事完了後に判明した重大な瑕疵に対して、修補にかかる費用を保険会社が補償する制度です。この保険に加入するのは施工業者です。たとえば、屋上防水の不良による雨漏り、外壁の剥離、鉄筋腐食など、建物の安全性や耐久性に影響を及ぼす瑕疵が対象となります。民間の損害保険会社では扱っていないため、国土交通省指定の住宅専門の保険会社に問い合わせをして大規模修繕工事瑕疵保険に加入するのが一般的です。
瑕疵保険に加入することで、施工業者が瑕疵を認めない場合や、施工業者が工事後に倒産して対応不能となった場合でも、管理組合は直接保険会社に補修費用を請求することができます。これにより、住民への追加負担を回避し、早期の補修実施が可能となるのです。ただし、保険の適用には一定の条件があり、工事の各工程での検査記録や報告書等が必要となるため、保険加入時から記録管理体制を整えておく必要があります。
また、もう一つ注目されているのが「履行保証保険」です。この保険に加入するのは施工業者です。これは、工事期間中に施工業者が倒産した場合など、工事の継続が困難になった際に、他の業者への引継ぎ費用や工事再開に必要な関係諸経費を補償する制度です。特に、マンション修繕工事においては、工期中の倒産リスクが無視できず、履行保証保険の有無が業者選定の一つの基準ともなっています。
履行保証保険は、日新火災海上保険という大手損保が提供しており、保険に加入できる業者は、事前に経営審査や施工実績の審査を通過しているため、その意味でも信頼性の高い企業に絞ることができます。管理組合としては、保険加入の有無を施工業者の選定条件に加えることで、より安全性の高い契約が可能となります。
まとめ「万全の備えが大規模修繕工事の成功を左右する」
大規模修繕工事は、管理組合にとって12~15年に一度の一大プロジェクトであり、その成否がマンションの寿命や資産価値、さらには住民の安心・満足に直結します。施工不良や瑕疵、業者の倒産といったリスクを回避するためには、発注方法、監理体制、契約内容、保険の整備といったすべての段階で、リスクマネジメントを徹底する必要があります。
特に「設計監理方式」は、施工業者と独立した立場の設計者が品質をチェックする体制を築くことで、手抜き工事や施工ミスの早期発見に大きく寄与します。また、「瑕疵保険」や「履行保証保険」は、施工不良や業者倒産といった最悪のケースに備えるための強力なツールです。保険制度の活用により、万一の際にも管理組合と住民が被害を最小限に抑えることが可能になります。
理事会や修繕委員会が、こうした仕組みを理解し、信頼できる専門家の助言を得ながら主体的にプロジェクトを進めることが、大規模修繕工事を成功に導く最大の鍵です。価格や納期だけでなく、品質と安全性、そして万全の備えを重視した判断が、将来のトラブルを防ぎ、安心できるマンション運営を実現します。