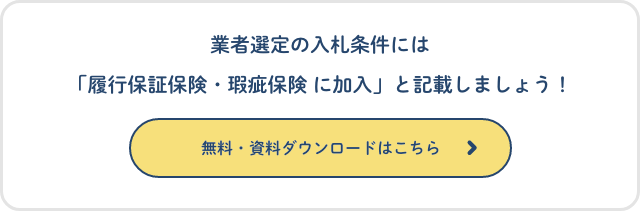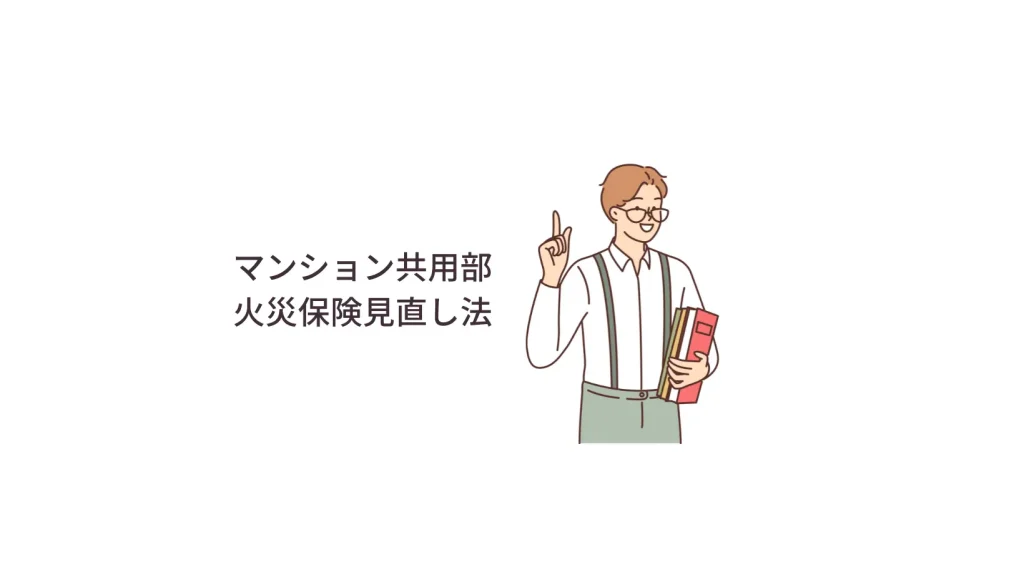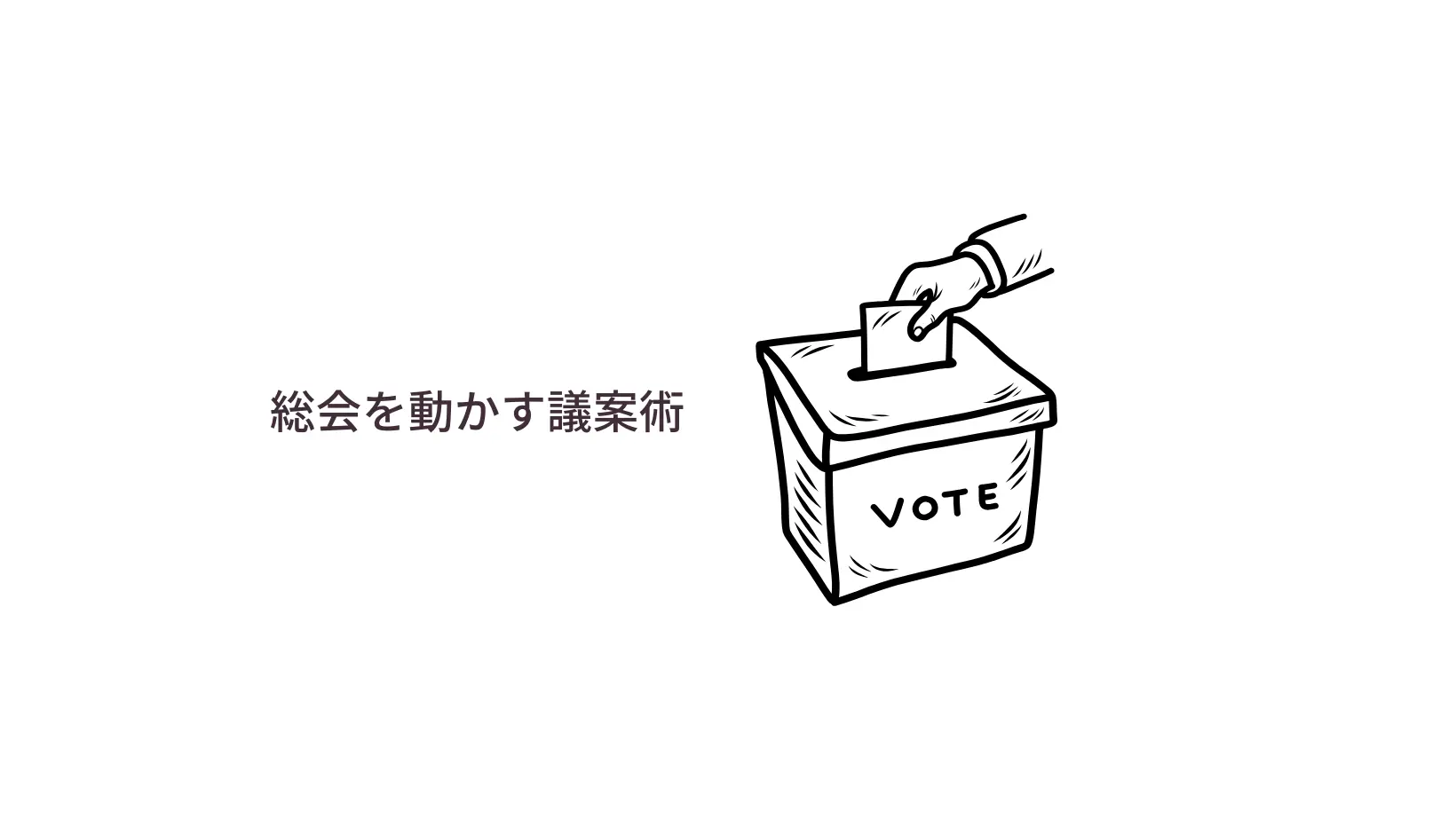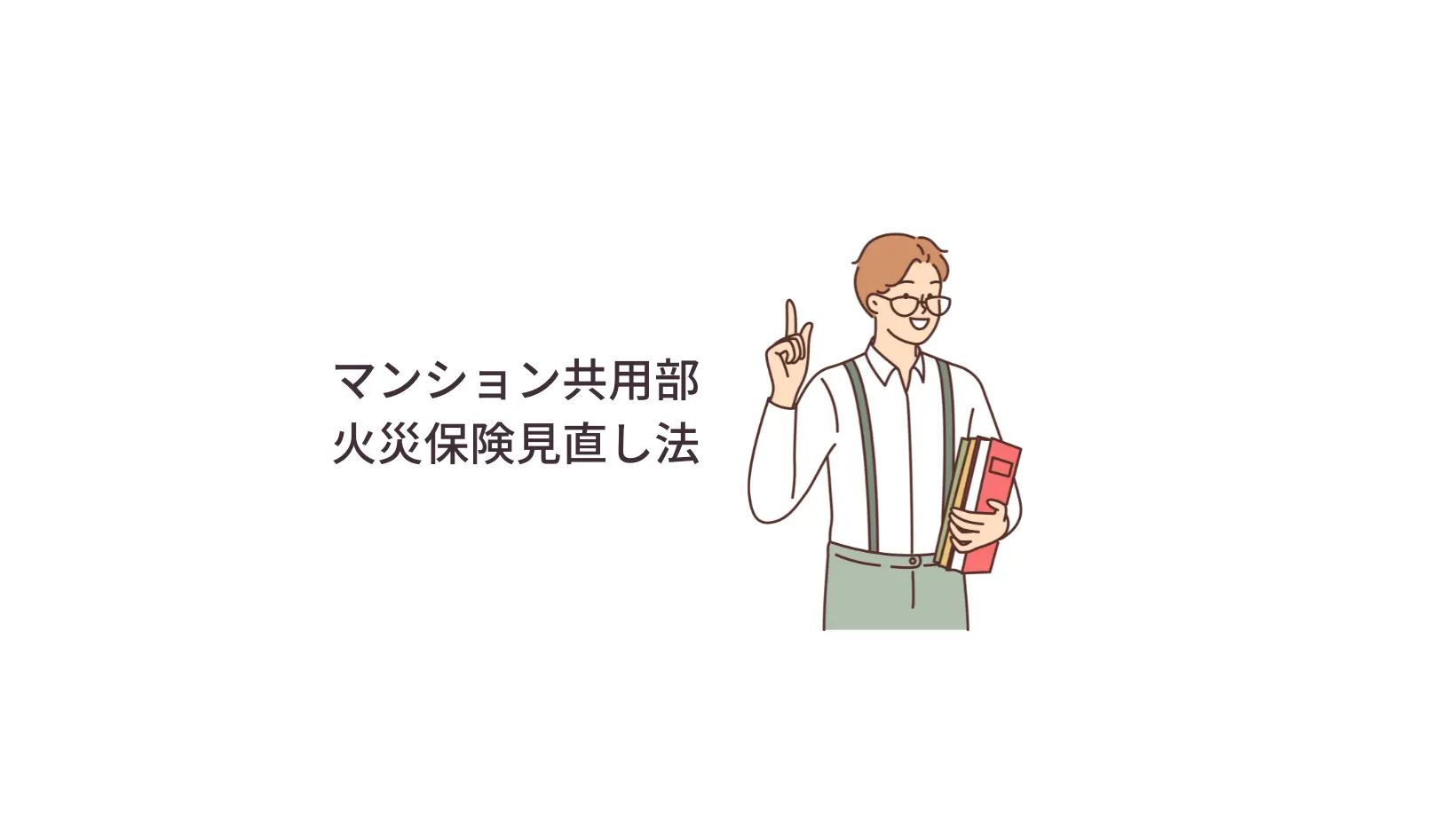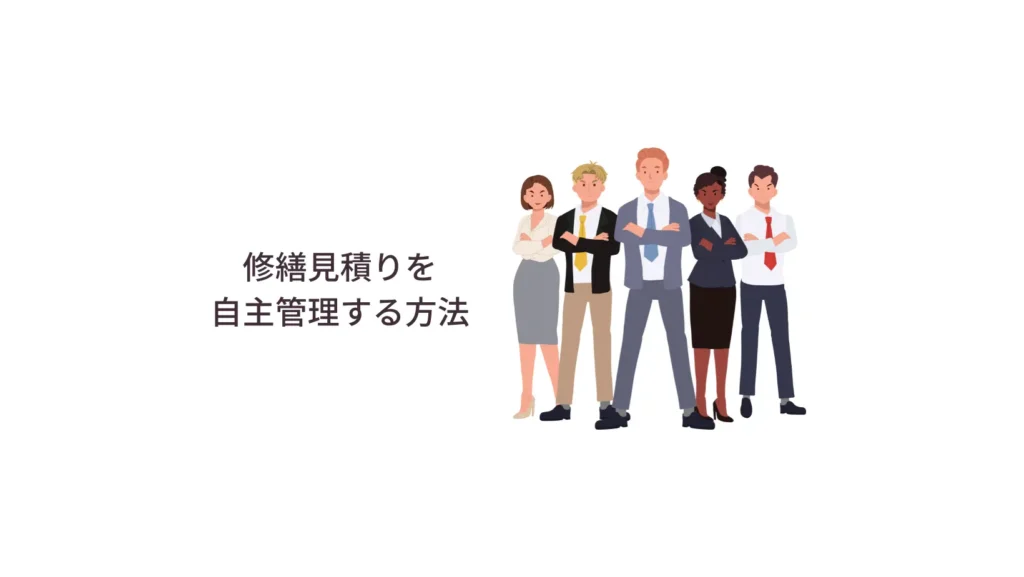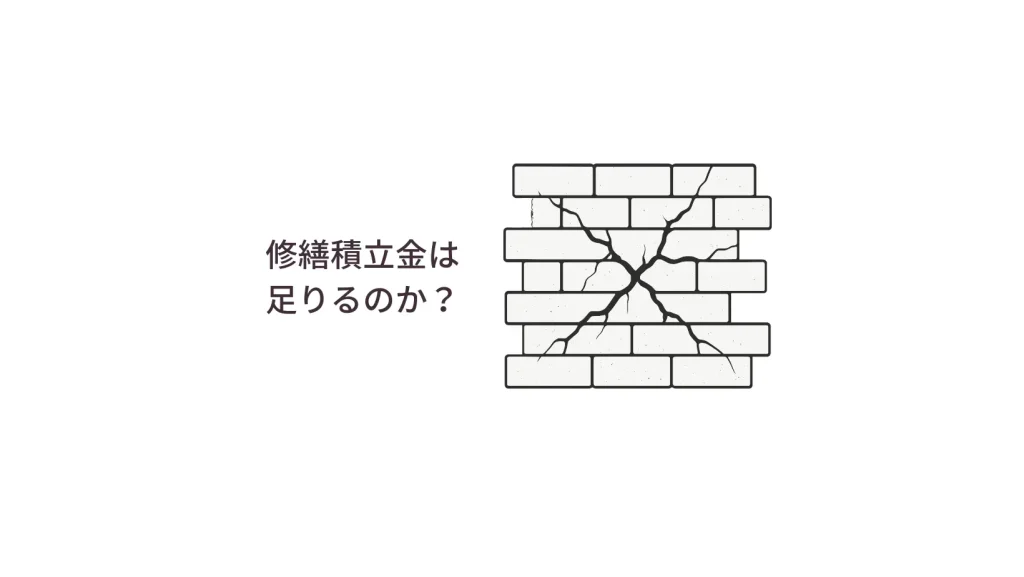皆さま、こんにちは!事務所が渋谷にある、渋谷貴博です。
35年間マンション業界で働いてきました。またプライベートでは、マンション(埼玉県さいたま市・総戸数812戸)に住んで、修繕委員、副理事長、理事長経験があります。そんな私が管理組合役員の皆さまの役に立つ情報を発信します。
分譲マンションにおける「共用部の火災保険」は、建物全体を守るための経済的な安全装置です。火災や風災、水災、落雷、地震などの災害が発生したときに、建物の修繕費や復旧費をカバーするこの保険は、管理組合にとって“第二の修繕積立金”ともいえる存在です。
しかし、実際には多くの管理組合が契約更新を「前年踏襲」で済ませており、補償内容を把握せずに放置しているケースが少なくありません。その結果、災害が発生した際に「補償範囲が狭くて保険金が下りなかった」「再建築費に対して保険金額が足りなかった」といったトラブルが多く報告されています。
一方で、火災保険を見直すことで、補償内容を強化しながら保険料を抑えられるケースも多くあります。契約内容を適正化することは、管理組合の財務健全性を高めると同時に、住民全体の安心にもつながります。ここでは、共用部火災保険を見直すうえで押さえるべきポイントを、3つの視点から詳しく解説します。
1.共用部の火災保険は“建物全体の安全装置”と理解する
まず前提として理解しておきたいのは、分譲マンションには「専有部保険」と「共用部保険」の2種類が存在するということです。専有部保険は各区分所有者が個人で加入する保険であり、主に室内の壁クロスや床、設備、家具などを守るものです。一方、管理組合が契約する共用部保険は、建物全体を構成する共用部分を対象にしています。
たとえば、エントランスホール、廊下、階段、外壁、屋上防水、エレベーター、受水槽、機械室、駐車場、フェンス、ゴミ置き場、照明設備などがこれに該当します。これらの部分で火災や台風、漏水、破損といった事故が発生した場合、修繕費用を保険金でまかなうことができます。
ところが、多くの管理組合では、この保険を「火災対策だけ」と誤解しています。実際には火災保険といっても、火災だけではなく「落雷、破裂、爆発、風災、水災、雪災、盗難、破損、汚損」など、多くのリスクをカバーできる仕組みになっています。契約内容によってオプションを付けた場合は、外壁タイルが落下して人がケガをした場合や、集中豪雨によって機械室が浸水した場合にも補償を受けることができます。特に近年は気候変動の影響で「想定外の自然災害」が増加しており、以前よりも多様なリスクへの備えが求められています。
さらに注意したいのは、共用部の火災保険が「専有部分の保険とは独立している」という点です。たとえば共用配管からの漏水で住戸内部が被害を受けた場合、専有部の火災保険では補償されないことが多く、共用部保険の対象となるケースがあります。このように、専有・共用の境界を正確に理解していないと、どちらの保険で対応できるか分からず混乱を招きます。管理規約や図面に基づき、共用部に該当する範囲を明確にしておくことが、トラブル防止の第一歩です。
また、地震保険についても検討すべきです。地震による外壁のひび割れや設備の損傷は、火災保険だけでは補償されません。地震保険は火災保険とセットでしか加入できませんが、建物全体の再建や部分修繕の際に重要な資金源となります。特に首都圏や南海トラフ地震の影響が想定される地域では、地震保険の有無が復旧のスピードを左右することもあります。共用部の火災保険は、単なる契約書上の形式ではなく、「建物全体を守る安全装置」であると再認識することが大切です。
2.補償範囲・保険金額・特約を定期的に点検する
火災保険を見直す際の第一歩は、契約内容の把握です。特に重要なのが「補償範囲」「保険金額」「特約」の3つです。これらを定期的に見直すことで、万が一のときに「保険金が足りない」「対象外だった」というリスクを防ぐことができます。
まず補償範囲ですが、古い契約では建物本体のみが対象になっていることがあります。たとえば、エレベーター、ポンプ室、フェンス、外灯、駐車場、看板、掲示板などが対象外となっている場合、災害時に修理費を自己負担しなければなりません。契約書の「保険の目的欄」を確認し、建物附属設備まで補償対象になっているかをチェックしましょう。
次に保険金額です。保険金額とは「建物を再建するのに必要な金額(再調達価格)」のことであり、これが実際の再建築費と大きくずれていると、災害時に十分な保険金を受け取れません。たとえば10年前に1億円で設定した保険金額をそのままにしていると、現在の建設コスト上昇を反映できていません。
鉄筋コンクリート造のマンションでは、資材や人件費の高騰により、再建築費が3割から5割程度上昇しているケースが多く見られます。この場合、保険金が実損額に比例して減額される「比例てん補」が適用されることがあります。つまり、損害額が1,000万円でも、保険金は700万円しか支払われないという事態です。これを防ぐためには、最新の再調達価格をもとに保険金額を設定し直す必要があります。
また、火災保険には数多くの特約が存在します。たとえば「漏水による他室損害補償特約」は、共用配管の漏水で住戸に損害を与えた場合に対応します。「機械設備補償特約」は、エレベーターやポンプなどの突発的な故障に対応し、「臨時費用特約」は災害後の仮設フェンス設置や瓦礫撤去、応急処置費用を補います。これらの特約は、建物の構造や過去のトラブル履歴に合わせて選択することがポイントです。不要な特約を外し、本当に必要な補償だけを残すことで、保険料の最適化も図れます。
さらに、契約更新の時期にも注意が必要です。5年契約が一般的なため、更新時期に手続きをする管理組合が多いです。最近は保険会社各社の保険料改定が毎年のように行われているため、できるだけ1~2年おきの見直しが必要です。「自動更新のタイミングで、内容はそのまま確認していない」とならないように見直しは、短期間ごとにチェックして更新時期がこなくても契約期間中に切り替えなど行うことが大切です。

3.保険料を抑えながら補償を強化する工夫と実践法
火災保険の見直しというと、「保険料が上がるのでは」と懸念する管理組合も多いでしょう。しかし、補償を削らなくても保険料を抑える方法はあります。最も効果的なのは、複数の保険会社から見積りを取得し、内容を比較することです。同じ補償内容でも、会社によって保険料が10〜30%異なる場合があります。
特に、マンション共用部向けの専用プランを持つ保険会社が増えており、複数社比較を行うだけで年間数十万円の節約が実現することもあります。そのためには、適切な保険代理店を選び、複数の保険会社から見積もりを取得する必要があります。多くの管理組合では管理会社任せの火災保険選定をしていますが、管理会社のほとんどは1~3社程度の保険会社しか取り扱っていません。これでは多くの見積もりを比較することができません。管理組合は5社~7社の保険会社の火災保険を問い扱っている保険代理店を見つけることが保険料を抑えるために大切な第一歩となります。
次に注目したいのが、管理状況診断付きの火災保険です。これはマンション管理組合の管理状況診断をマンション管理士が実施し、劣化状況・修繕履歴・管理体制などを評価したうえで、状態が良好であれば保険料を割引する仕組みです。実際に、適正な維持管理を行っているマンションでは、最大10%以上の保険料削減が可能となるケースもあります。逆に、管理状態が悪いと割増となることもあるため、日常の清掃や修繕体制の整備がコスト削減にもつながるのです。
また、契約期間を短くすることで市場動向に合わせた保険料見直しが可能です。保険料は建設費や自然災害リスクに応じて毎年変動しており、長期契約では不利になることもあります。1年契約で定期的に比較・交渉することで、常に最新かつ合理的な条件を維持できます。
さらに、補償を「一部自己負担型(免責設定)」にすることで、保険料を下げる方法もあります。軽微な損害は自己負担とし、大きな災害に備えるスタイルです。これにより、保険料を20〜30%削減しながら、必要な補償を確保できます。
火災保険の見直しは、節約のためだけではなく、管理組合のリスクマネジメントそのものを見直す機会でもあります。災害や事故が起きたとき、迅速に保険金を請求できる体制を整えることも大切です。保険証券や契約内容を整理し、理事会内で共有しておくことで、いざというときの初動が早くなります。保険代理店や専門コンサルタントと定期的に面談し、建物の状態や補償内容を一緒に点検することも有効です。
まとめ|火災保険の見直しは“管理の成熟度”を映す鏡
分譲マンションの共用部火災保険は、建物を守るだけでなく、管理組合の意思と体制を映し出す「鏡」のような存在です。補償範囲を理解せずに漫然と更新を続けると、いざという時に十分な補償を受けられず、結果的に修繕積立金を取り崩す羽目になります。逆に、契約内容を定期的に点検し、建物の状態に合わせて最適化する組合ほど、将来の修繕負担を軽減し、居住者全体の安心を維持できます。
火災保険の見直しは、最低でも2~3年に一度は行うのが理想です。築年数の経過、資材価格の上昇、自然災害の多発など、環境変化に応じて保険内容を更新していくことが大切です。特に、建物診断付き火災保険を活用すれば、割引と補償強化の両立が可能になります。
また、理事会任せにせず、総会などで契約内容を共有し、区分所有者全員が「保険の仕組み」を理解しておくことも重要です。管理組合が自ら情報を収集し、必要に応じてマンション管理士や保険コンサルタントの意見を取り入れることで、より合理的で透明性の高い保険運用が実現します。
火災保険は、もしもの時に「入っていてよかった」と実感できる数少ない制度のひとつです。建物の価値を守り、修繕積立金を保全し、住民の安心を支える仕組みとして、今こそ見直しを進めるべき時期です。管理組合の主体的な判断が、マンションの未来の安全と信頼を支える最大の力となるのです。
一般社団法人マンションあんしんセンターでは、マンション共用部の火災保険に関して取り扱いをしています。どのようなご相談でも対応いたします。下記までお気軽にご相談ください。
マンションあんしんセンター・なんでも相談コーナー
https://mansion-anshin.com/support/