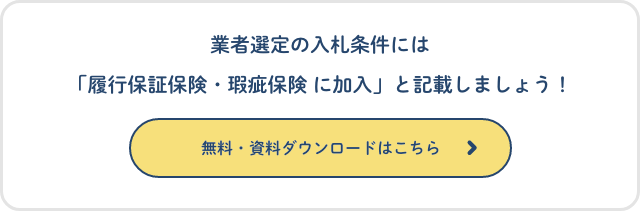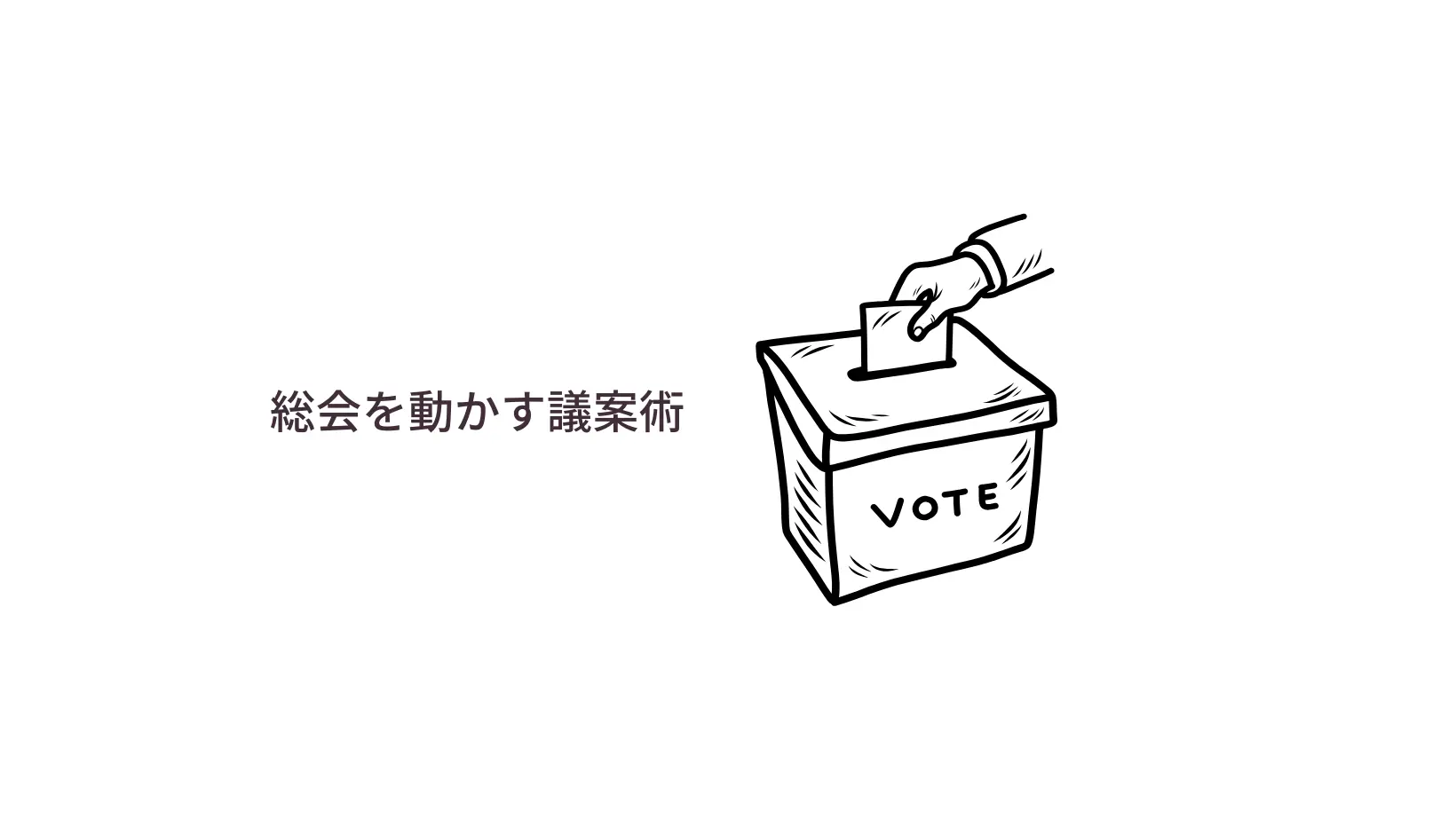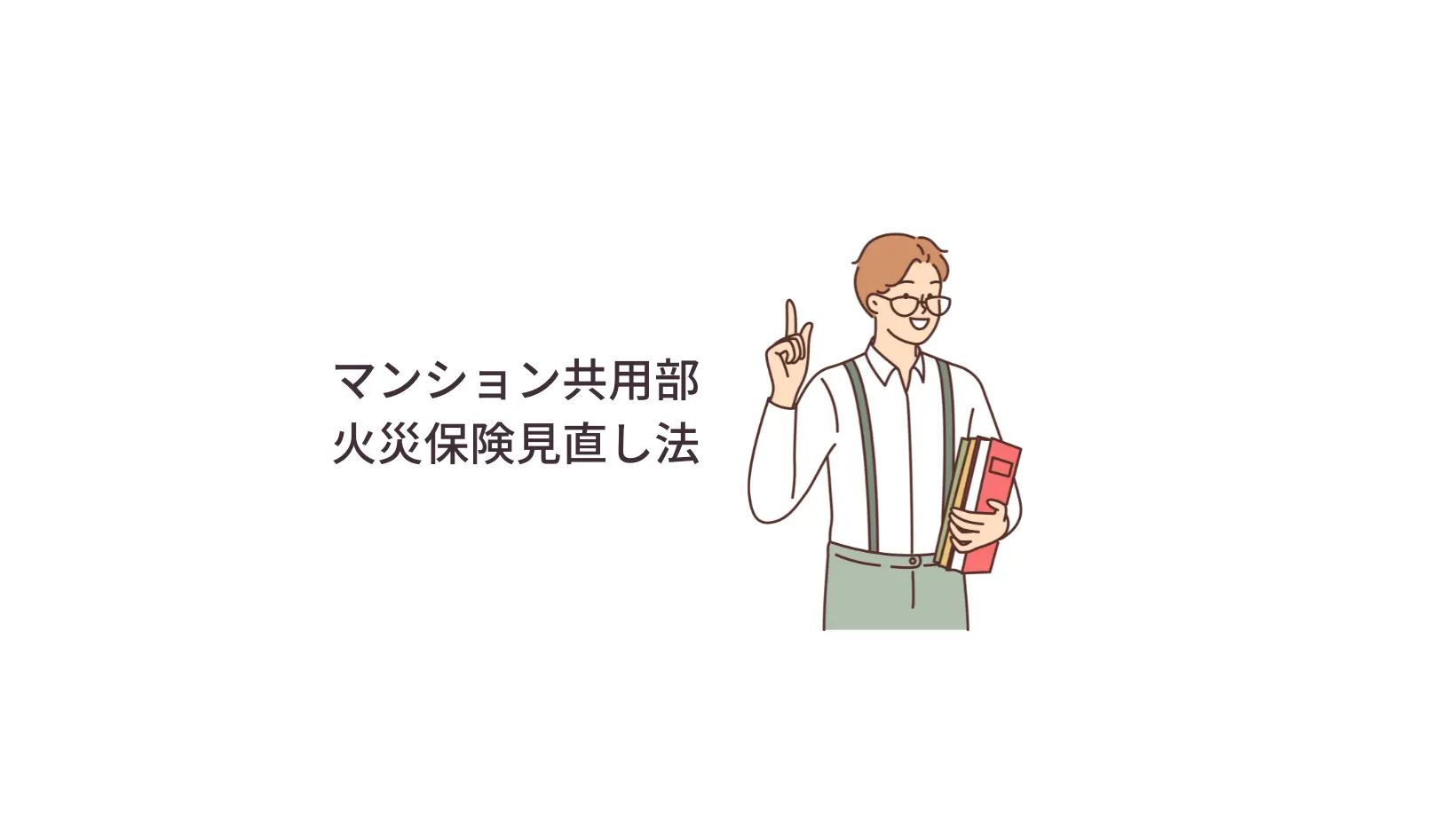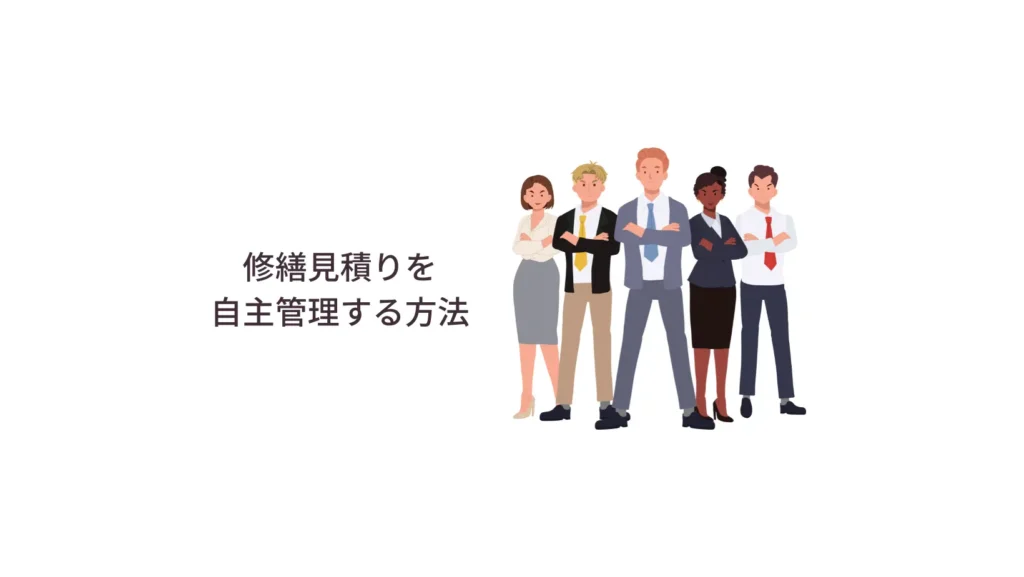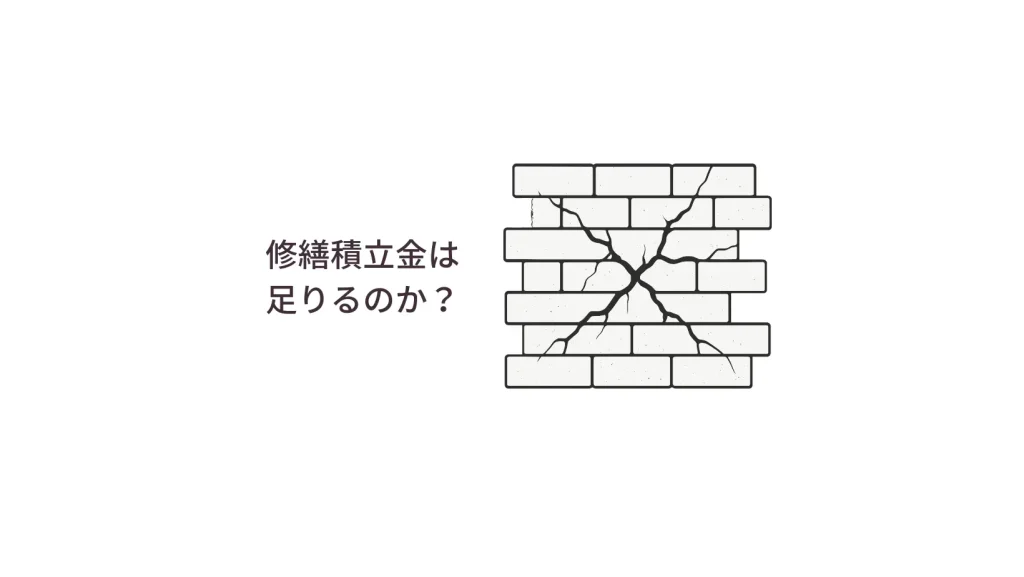皆さま、こんにちは!事務所が渋谷にある、渋谷貴博です。
35年間マンション業界で働いてきました。またプライベートでは、マンション(埼玉県さいたま市・総戸数812戸)に住んで、修繕委員、副理事長、理事長経験があります。そんな私が管理組合役員の皆さまの役に立つ情報を発信します。
マンションの管理組合が加入している「共用部分の火災保険」は、建物全体を災害や事故から守るための重要な仕組みです。それにもかかわらず、「どこまで補償されるのか」「費用はどのくらいかかるのか」「見直しのタイミングはいつが適切なのか」といった基本的な内容を十分に理解していない管理組合も多く見られます。
実際、契約当初の内容のまま何年も放置しているケースは珍しくありません。その結果、火災や風災・水災などの自然災害が発生した際に、保険金が思ったほど支払われなかったり、そもそも補償の対象外だったという問題が発生しています。
共用部の火災保険は、マンションの資産を守る「経済的な防衛手段」であり、適切に活用すれば修繕積立金を保全し、居住者の負担を最小限に抑えることができます。
ここでは、共用部分の火災保険の仕組み、補償範囲と費用の考え方、そして見直しの際に押さえるべきポイントを、管理組合の視点からわかりやすく解説していきます。
1.共用部分の火災保険とは?管理組合が契約する“建物を守る防衛線”
まず、共用部分とは何かを正しく理解しておく必要があります。
分譲マンションでは、各住戸の区分所有者が専有している部分(住戸内の床・壁・天井・キッチン・浴室など)と、所有者全員で共同利用する部分(エントランスホール・階段・廊下・外壁・屋上・受水槽・エレベーター・駐車場・フェンスなど)に分かれています。このうち、後者の共用部分に対して加入するのが「共用部火災保険」です。管理組合が契約者となり、建物全体の共用部分に発生する損害を補償します。
火災保険という名称から「火事の時だけの保険」と思われがちですが、実際にはそれ以上の幅広いリスクをカバーしています。火災や落雷、爆発はもちろん、台風や突風などによる風災、積雪やひょうによる雪災、河川氾濫や集中豪雨による水災、さらには外部からの衝突や飛来物、いたずらや盗難による破損、設備の故障や漏水といった事象まで、契約内容に応じて補償される範囲は多岐にわたります。
たとえば、近年では強風や線状降水帯の影響による被害が全国で増加しています。屋上防水の破損や外壁タイルの落下、機械室の冠水、エレベーター設備の故障など、火災以外の災害で被害が発生するケースが年々多くなっているのです。こうした状況を踏まえると、「火災保険=火事のためのもの」という古い認識は通用しません。むしろ、異常気象や自然災害の増加に対応するための“包括的リスク保険”と捉えることが適切です。
また、共用部保険と専有部保険の関係も整理しておく必要があります。専有部の火災保険は、各区分所有者が個別に加入し、室内の損害をカバーするものです。一方、共用部の火災保険は、共用配管や構造体、共有設備などを対象としています。たとえば、共用配管からの漏水によって住戸の天井・壁・床が濡れた場合には、共用部保険で修繕費をまかなうことがあります。
ただし、専有部である住戸内で洗濯機が壊れて水が室内に溢れて、下階の住戸の天井・壁・床が濡れた場合には、専有部保険で修繕費をまかなうことになります。この取り扱いの境界線を明確に理解しておくことが、トラブル防止の第一歩です。
さらに、地震保険の活用も重要です。火災保険だけでは地震による被害は補償されません。外壁の亀裂やエレベーターの損傷なども、地震由来であれば火災保険の対象外となるため、火災保険とセットで地震保険に加入することで初めて安心が得られます。管理組合としては、建物全体の復旧を想定した現実的なリスクマネジメントを行う必要があります。
「地震保険の活用について」はこちらから
https://www.mof.go.jp/policy/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm

2.補償範囲と費用の考え方を理解することが、損をしない第一歩
共用部火災保険の補償範囲は契約によって異なりますが、基本となるのは「建物本体」「付属設備」「外構」の3要素です。
建物本体には、外壁・屋根・柱・梁・床などの構造体が含まれます。付属設備には、エレベーターや受水槽、ポンプ室、電気設備、照明、掲示板などが該当し、外構にはフェンスや門扉、駐輪場、機械式駐車場などが含まれます。これらすべてを補償対象とすることで、建物全体を包括的に守ることができます。
契約時に注意すべきは、「補償を外してしまっている部分がないか」という点です。古い契約では、コストを抑えるために風災や水災などの補償を外していることがあります。しかし、近年の異常気象を考えると、水災補償を外すのは極めて危険です。実際に、低地に建つマンションで地下の電気設備や機械室が冠水し、修繕費が数千万円規模にのぼったケースもあります。補償内容を安易に削ることは、結果的に管理組合の財政リスクを高めることにつながります。
また、火災保険の費用(保険料)は、建物の構造、築年数、延床面積、立地条件、災害リスクなどによって大きく異なります。鉄筋コンクリート造(RC造)で築15年・30戸規模の一般的なマンションであれば、年間保険料はおおよそ13万円前後が目安といわれています。
ただし、自然災害リスクが高い地域や、設備が多く高額なマンションでは、25万円を超える場合もあります。
さらに注目すべきなのが、管理状態の診断を活用した保険料割引制度です。この制度では、マンション管理士による管理状態の診断を受け、その結果に応じてリスク評価が行われます。管理状態が良好であると判断されれば、保険料の割引が適用される場合があります。
つまり、日常の維持管理を適切に行っているマンションほど、保険料を抑えられる仕組みになっているのです。これは、単なる保険契約ではなく、「良好な管理が報われる制度」として注目を集めています。
共用部の火災保険は、保険料だけで比較するのではなく、「補償の内容」「建物の現況」「将来の修繕計画」とのバランスを踏まえて選ぶことが何より重要です。保険は建物維持のための“もうひとつの修繕資金”であり、短期的な節約ではなく、長期的な安心を買うという視点で検討すべきでしょう。
3.見直しのタイミングと管理組合が取るべき対応策
火災保険の契約は、一度締結したら終わりではありません。実際の建物は年々老朽化し、災害リスクも変化していきます。したがって、定期的な見直しこそが、保険を「生きた制度」として機能させる鍵になります。最も重要なのは、保険金額の妥当性を確認することです。火災保険の支払い限度額である「保険金額」は、建物を再建するための費用、すなわち「再調達価格」を基準に設定します。
ところが、築年数が経過してもそのまま据え置いているケースが多く、建設資材や人件費の上昇により、実際の再建費用に追いついていないことが少なくありません。この状態で災害が起きた場合、損害額の一部しか保険金が支払われない「過少保険」状態に陥る恐れがあります。
保険金額は5〜10年ごとに見直し、再調達価格に見合う金額を設定し直すことが大切です。また、特約の見直しも欠かせません。共用配管の漏水に備える漏水損害補償特約、エレベーターやポンプなどの突発的な故障に対応する機械設備補償特約、災害後の仮設フェンスや撤去作業費を補う臨時費用特約など、特約を適切に組み合わせることで、実際のリスクに即した補償体系を構築できます。とくに築20年以上のマンションでは、設備劣化に伴うトラブルが増えるため、こうした特約の有無が大きな違いを生みます。
契約更新時には、必ず複数社の見積りを取得して比較しましょう。同じ補償内容でも、保険会社によって保険料や免責金額が異なります。最近では、マンション共用部向けの専用プランを提供する保険会社も増えており、条件を比較することで無理なくコストを削減できます。また、保険代理店やマンション管理士、修繕コンサルタントなど、専門家の意見を取り入れることも有効です。管理組合の理事だけで判断するのではなく、専門家のサポートも取り入れましょう。
火災保険の見直しは、単なる経費削減ではなく、管理体制の健全性を示すものでもあります。契約内容を理解し、建物の現状や修繕計画に合わせて適切に調整することが、管理組合の責任であり、結果的には居住者全員の利益を守ることにつながります。
まとめ|共用部火災保険の見直しは、建物の“未来を守る行為”
共用部分の火災保険は、マンションの資産価値を守り、災害発生時の経済的ダメージを最小限に抑えるための不可欠な制度です。しかし、契約内容を長年見直していない管理組合では、補償が実態に合っておらず、いざというときに保険が機能しないというリスクがあります。補償範囲や保険金額を定期的に見直し、建物の状態に合わせて最適化することこそが、最も確実な「備え」といえるでしょう。
また、保険料の節約を目的とするだけでなく、管理状況の診断付き保険の活用や特約の見直しなど、リスク管理の一環として火災保険を戦略的に運用する視点も重要です。管理組合が主体的に契約内容を理解し、議論し、更新していく姿勢があれば、災害時にも慌てず、修繕積立金を守りながら早期復旧を実現できます。
火災保険は、もしものときに「加入していて本当に良かった」と実感できる数少ない仕組みです。そして、その安心は、今この瞬間の“見直し”によってしか得られません。
管理組合が責任をもって契約内容を把握し、時代に合わせて最適化を続けることが、マンション全体の安全と信頼を長期的に支える最大の力になるのです。
当ブログ配信の「マンションあんしんセンター」HPはこちらから
https://mansion-anshin.com/